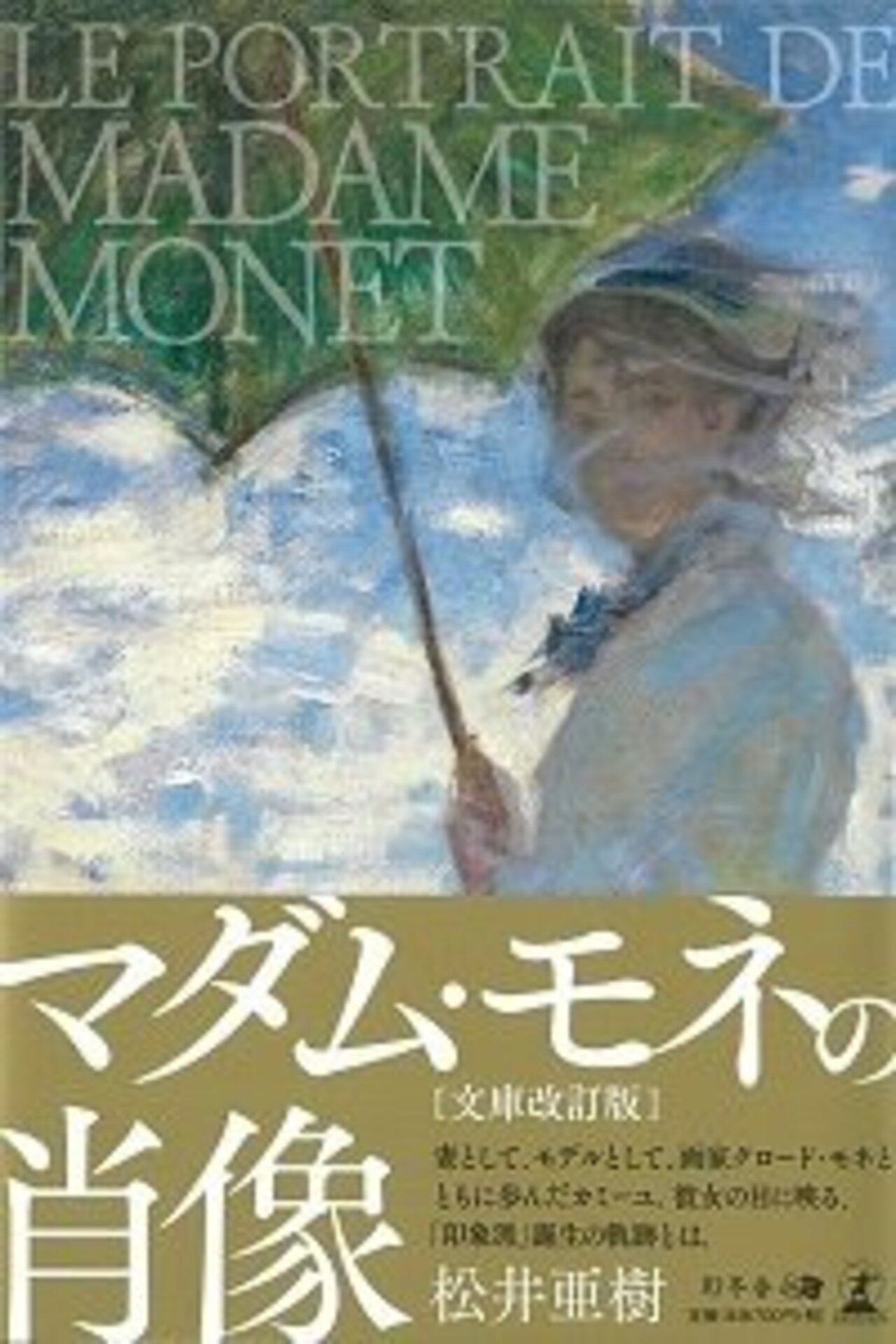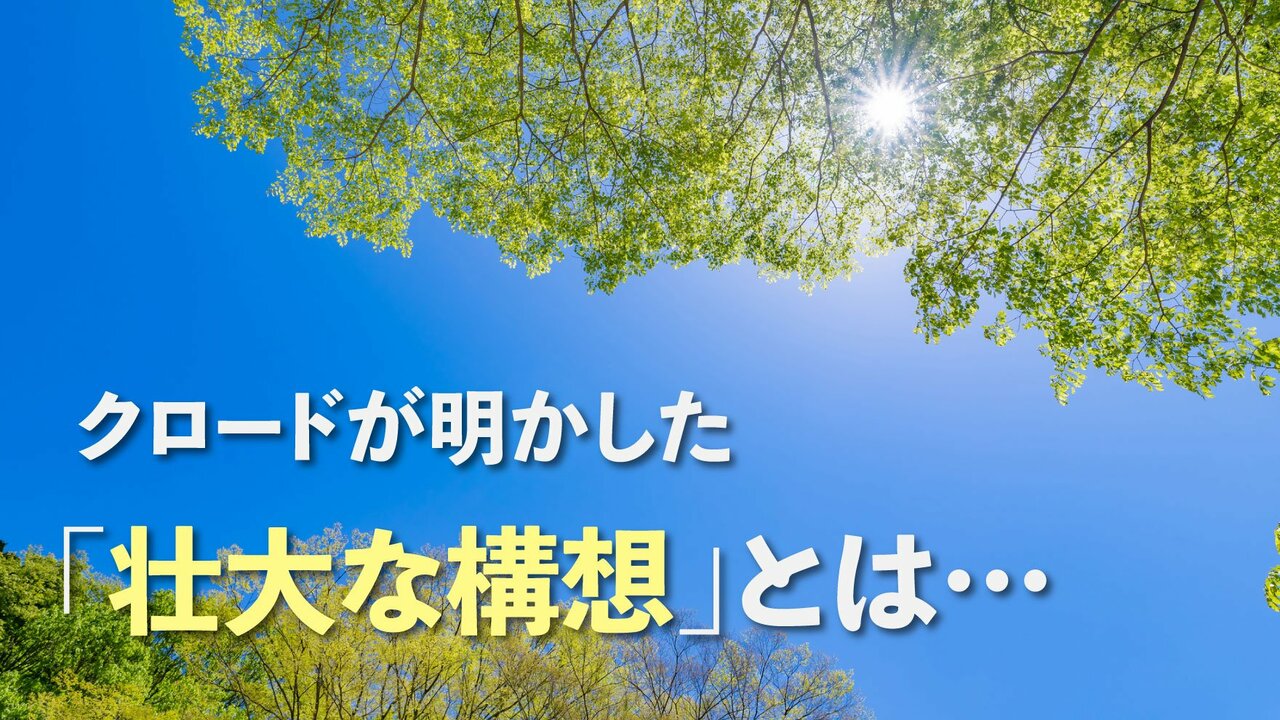クールベはこのときすでに四十代も半ばだったが、彫りの深い、目鼻立ちの大きな男で、若いころは相当に女たちの心を騒がせたのではないかと容易に想像された。
けれどカミーユにとっては、あまり得意なタイプではない。紹介されたカミーユに挨拶をしてくれたときも、見つめる視線がべったり体に張り付くようで、生理的にどうしても受け付けられない部分があった。
それでも彼はクロードやフレッドの友人、それも大先輩にあたる人なのだから失礼があってはいけない。クールベは、『草上の昼食』が自然の中に一団の現代人を描くものだと知ると、自分もモデルを務めようと言い出した。
「男がバジールばかりでは不自然だろう」
レアリストらしい発言をしながら、一方では面白がっている風にも見えた。
「それはありがたい! ぜひお願いします」
クロードの方も、大先輩に向かって遠慮もせずに言うと、皆はアトリエに入った。さすがに炎天下で先輩にポーズを取らせるわけにもいかないのだろう。
それに、スケッチならアトリエで描いた方がクロードも楽だ。
「お好きな格好で」
とクロードが言うと、クールベは床の上に片膝を立てて座った。カミーユはクールベのことをよく知らないのに、それはとても彼らしいポーズのように思えた。
フレッドが申し訳なさそうに敷き物を持ってくると、クールベはその上に座り直し、にっこり笑った。
「ワインもあるといいがなぁ」
軽口を叩きながらも、クールベは最初の姿勢を小一時間ほど保った。
やはりこの人も画家なのだとカミーユは思った。