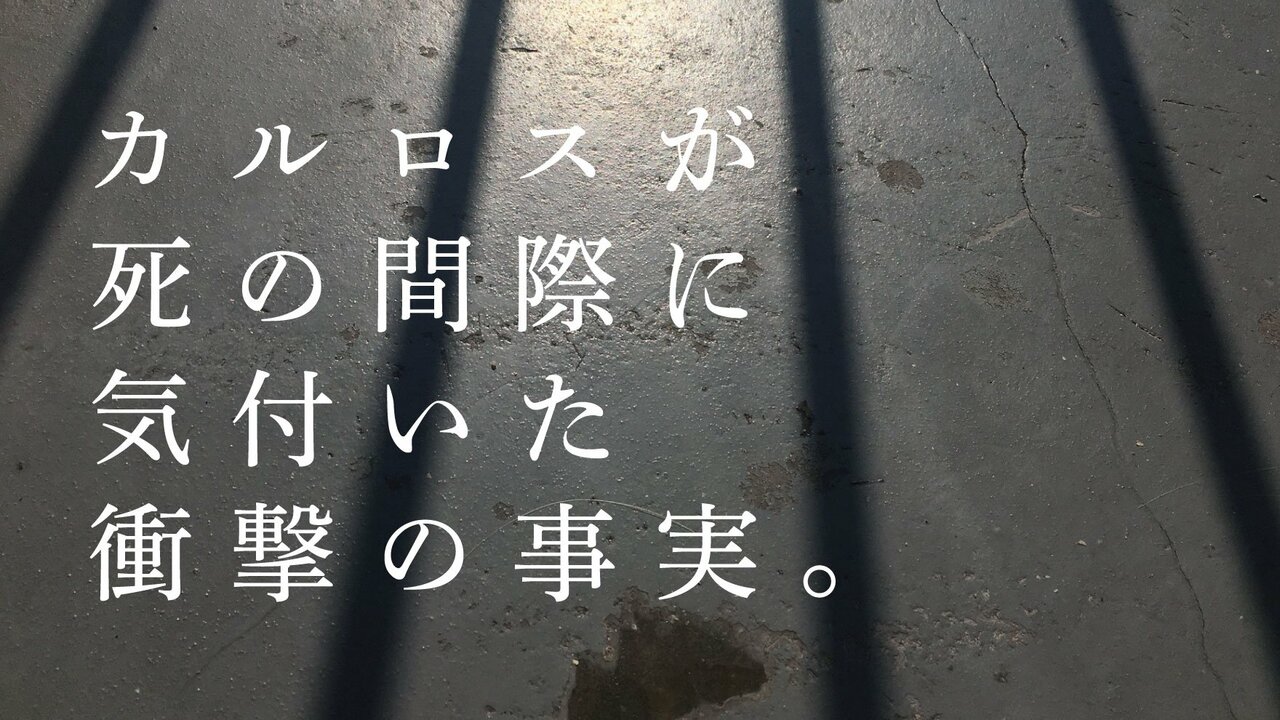カルロスが家に帰り着いたとき、コンスエラは家の外で洗たく物を取りこんでいるところだった。
「フィオリーナが……蛇にかまれた」
やっとこれだけ言うと、カルロスはワッと泣きだした。コンスエラは紫色になった傷口を見て、フィオリーナが毒蛇にかまれたことが分かったので、すぐに傷口を消毒して包帯を巻き、床に置いたマットにそっと寝かせた。
フィオリーナは横倒しになったまま、目をつぶって苦しそうに息をしている。今にも死んでしまいそうに見えた。
「カルロス。神様にお祈りしましょう。フィオリーナを助けてくださるように」
二人はひざまずいて長いあいだ祈った。
「天にましますわれらが父、イエス様、どうかフィオリーナの命をお助けください」
夜になるにつれて、少しずつフィオリーナは呼吸が楽になってきたようで、二人はいつのまにか眠くなってきた。フィオリーナのそばに毛布をしいて眠っていた二人は、ブルブルという音で目を覚ました。外はすでに明るくなっている。はっと起きあがると、フィオリーナが元気よく立ち上がって、のびをしているのが目に入った。
「ママ、フィオリーナが元気になったよ」
カルロスはうれしそうに大きな声をあげた。コンスエラもうれしさのあまり、フィオリーナとカルロスをかわるがわる抱きしめずにいられなかった。このことがあってから、カルロスはますますフィオリーナを大切に思うようになった。
カルロスが一番好きな場所は、遠くにアンデス山脈(1)が見える牧場の小高い丘だった。そこに、フィオリーナと座って、夕日をながめた。フィオリーナの毛は風に吹かれてふわふわと柔らかくゆれた。
カルロスの父親はカルロスが三歳のときに亡くなったので、父親の顔は写真でしか知らない。けれども、夕日をながめていると、父親がどこかで自分を守ってくれているような気がした。
カルロスは毎晩、寝る前に母と一緒にお祈りをする習慣だった。
「神様、いつまでも、ママとフィオリーナをお守りください」
お祈りの最後には、そう付け加えることを忘れなかった。カルロスはこうして、動物の大好きな優しい子供に育った。十歳になったカルロスは、亡くなった祖母からもらって大切にしていた銀のメダルに、ナイフとくぎを使って、ていねいに「F」の花文字を彫り、皮ひもを通してフィオリーナの首飾りを作った。
「F」はフィオリーナの頭文字だ。このころには、フィオリーナはもう子犬ではなく、カルロスの胸ぐらいまであるおとなの犬になっており、その銀のメダルを首にかけた姿はとても美しかった。