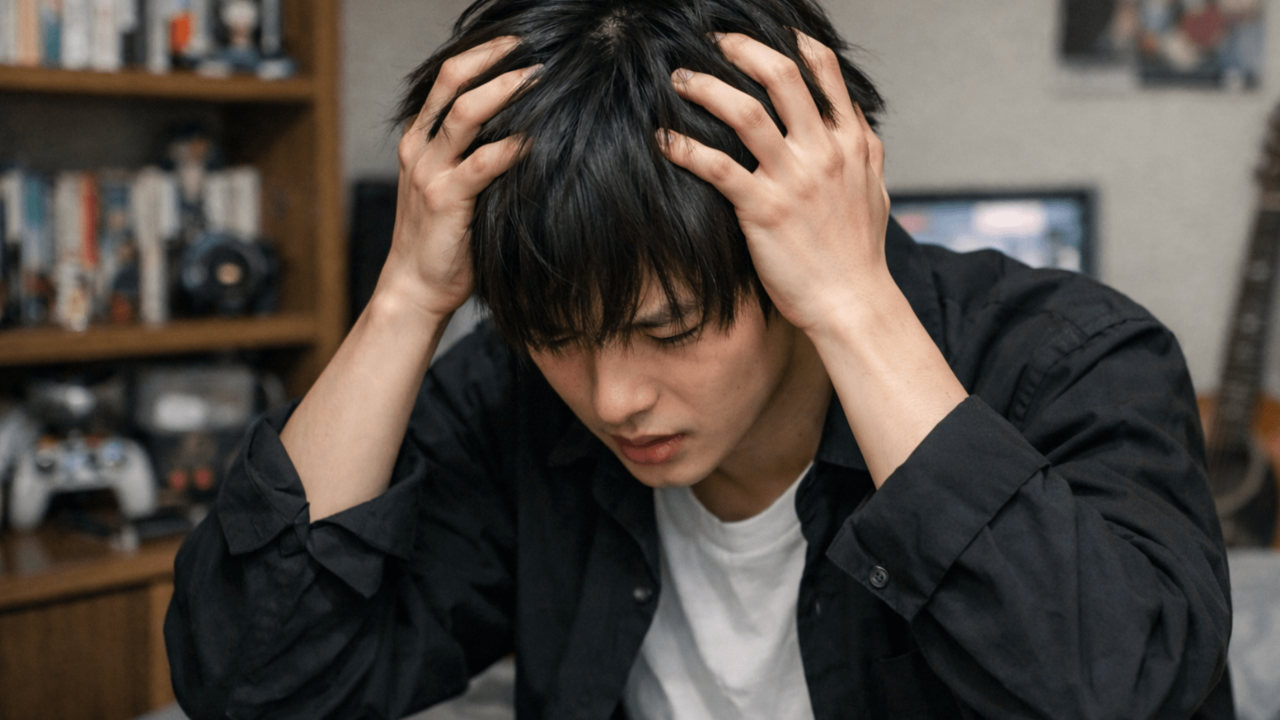漁場に着くと自慢の高性能魚群探知機のスイッチを入れた。しかし、辺りを走り回っても魚影はなかなか現れなかった。他に漁船は出ておらず取り放題だというのに不甲斐無いとの思いが登を焦らせ熱くもした。
船は蛇行しながら魚影を追っていつしかかなりの沖に出ていた。見回すと遙か遠くにしか陸影は見えない。半島沖の外海は黒潮の流れる太平洋であり、台風の接近でかなり荒い波が立ちいつもと違ううねりを見せていた。それでも探し回った御陰か先程から魚群探知機がチラチラと魚群の尻尾を捉え出した。
しかし、南空に黒い雨雲が急速に発達し大粒の雨を降らせて甲板を叩くようになり風も吹き出した。船は荒い波に大きく揺れるようになった。
この魚群さえ捕獲できればここしばらくの落ち込みを取り戻せる。登はためらうことなく荒れる海に網を入れた。落ちている御宝を拾わぬ手はない。何も獲らず港に引き返すことなどできるものか。そんな思いが登の判断を狂わせた。
網は魚群を見事に捉え、登はウインチで巻き上げ始めた。その間にも海はうねりを増した。
重い網に小さな船が右に傾きうねりを受けて上下に揺れた。さらに船は台風のもたらす横風も受け今にも転覆しそうである。
登は出しなに呷った焼酎の酔いもとっくに冷め、船を立ち直らせようと舵にしがみついた。
厚い雲が空を覆い、昼間なのに薄暗く陸は見えない。さらに雨のため視界は三〇メートルも無いほどになった。
度を増す嵐の風で操舵の効かなくなった船は木の葉のように波間で揺れた。海に放り出されたら一溜まりもない。しかし、今更網を切ってもこの嵐の中、漁港まで無事には帰れる見込みは無い。いや、戻るにはもう遅すぎる。ならば、漁師の意地を掛けても仕掛けたこの網だけは放すものか。山のようなうねった波に上下する船の上で登はそう思った。死が頭を過ぎり、小さな二人の息子たちの顔が浮かんだ。
暴風雨が吹き荒れる中、康代は休校となって家に戻って来た長男と次男の世話をしていたが、午後を大きく回っても帰って来ない夫を心配して漁協に連絡を入れた。
「こんな日に船を出したんですか。あれほど注意をしたやないですか」
電話に出た若い漁協の職員は怒りを含んだ声でそう言った。それでも職員は受けた連絡からことの重大さを認識し、テキパキと各方面に救助支援の連絡を入れてくれた。康代はその日一睡もせずに漁協から連絡が入るはずの電話の前で夜を明かした。
漁船の捜索は、夜が明け暴風雨が収まった早朝から実施された。昼過ぎ、空から捜索した第四管区海上保安部から転覆した漁船が見つかったとの連絡が漁協に入った。そのあとの船内捜索で、登は操舵室の舵にしがみついたままの遺体で見つかった。痛ましい事故は地元新聞の記事にもなり、神式の葬儀が自宅でしめやかに行われた。