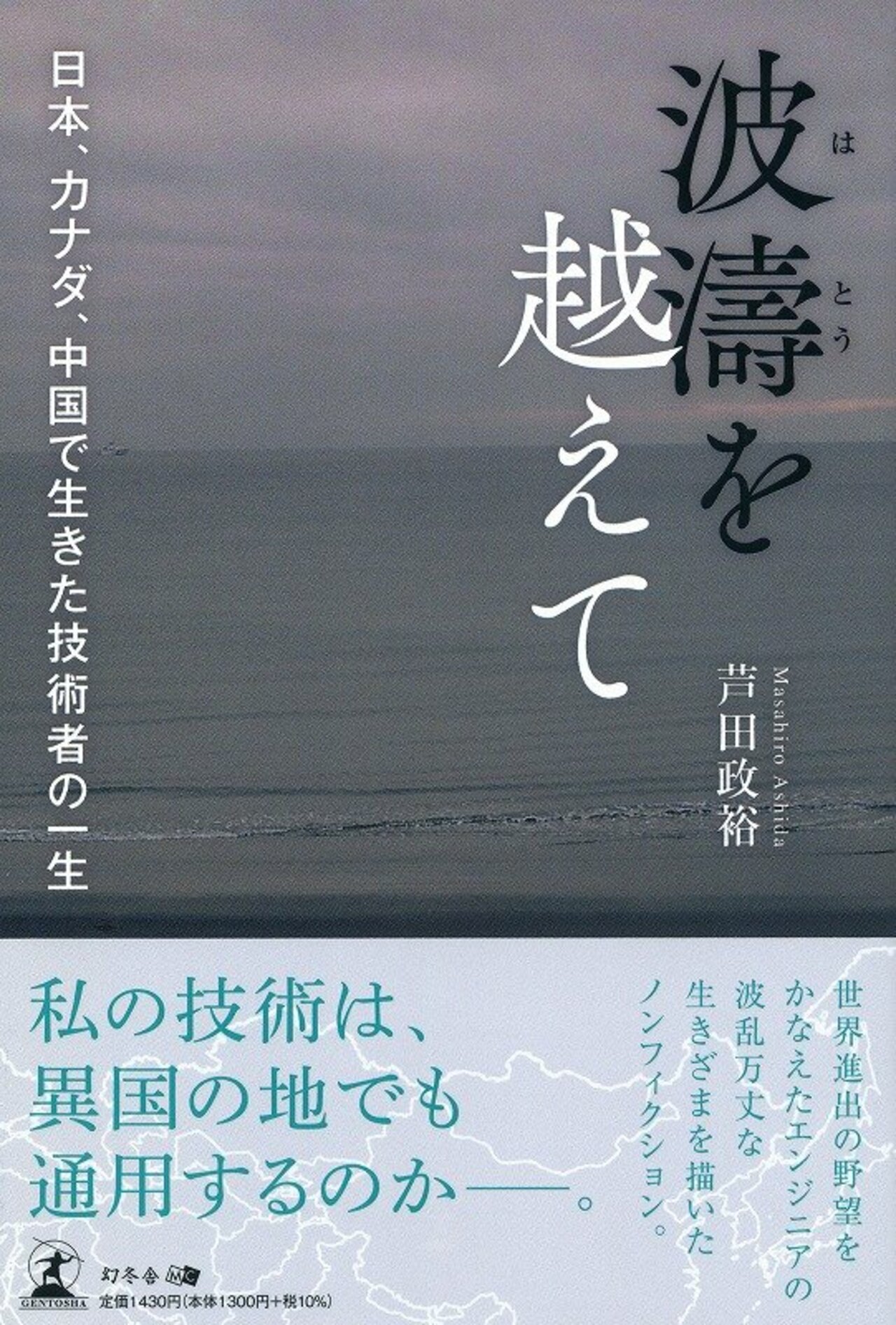政裕はこのテーマに関する予備知識が皆無だったので、プロセスについての説明文書や参考文献の理解に時間を費やした。それにより、必要な実験計画を立て機材、薬品類などの購入計画を立てた。
この新技術の基本プロセスの中に化合物の熱分解があり、これに関連して大学の卒論実験で多少の経験があったのが助けになった。
プロセスの出発原料は市販の工業薬品ではなかった。この薬品は特殊な化学反応で合成する必要がある。これは一つの問題点だと思った。計画を立て、実験設備ができ、多忙な毎日が始まった。徹夜実験の日もあった。
ある日、徹夜実験で、中間体の化学合成を始めたが、その過程で臭素ガスが発生したのが漏れて、中毒、失神して床に倒れていたのを翌朝出勤してきた別の会社からの研究員が発見した。
救急車を呼び病院に搬入された。酸素吸入などの治療を受け、数日入院して回復することができたが危なかった。弥生寮の寮母さんや住人が心配して待ってくれていた。単独でそのような実験をするのは無謀なことではあった。その研究員には恩義を感じた。以後昵懇な関係になった。
実験は計画通り着実に進んだが月日の経つのは早く、東京に木枯らしが吹き始めたころ、ようやく最終段階を迎えた。
出来上がった熱分解生成物は結晶ではなく、薄褐色の粉末だった。
一晩それを見ながらこれは一体何だろうかと考えた。電気炉で熱分解中に空気が侵入して酸化したのか? 政裕はこの技術の出どころを最初の段階で調査しておくべきだったか。原料は有機ケイ素化合物である。
有機物には炭素原子が含まれている。熱分解で炭素は切り離されるのか? 失敗かと不安がよぎった。
組成分析のため、母校、九州工大の恩師、長池助教授を訪問、分光分析とX線解析を依頼した。結果、その生成物はシリコンではなくシリコンカーバイドだった。酸化はされていなかった。やはり炭素が残っていたのだ。予感はしていたがこんな当然を見過ごしていた。
アルゴンガス雰囲気の石英管の中、摂氏一六〇〇度で熱分解させた生成物はケイ素と炭素の結合が切れていなかったのだ。水素だけが消えていた。ケイ素と炭素の結合エネルギーを文献で調べたところ、それは簡単に切れるものではないことを発見した。
最初の計画段階でこれに気付かなかったのは最初からこのアイデアを頭から疑っていなかったからだ。手順として文献調査など裏付け調査をしておく原則を省いたのは自分の責任かもしれない。基礎知識の不足も感じていた。
年の暮れに政裕は本社の社長室で研究所の吉川院長と霧谷専務に最終報告を行い、結果と失敗の根拠を説明した。
一年の特別任務は終了、年明けに埼玉工場に復帰した。