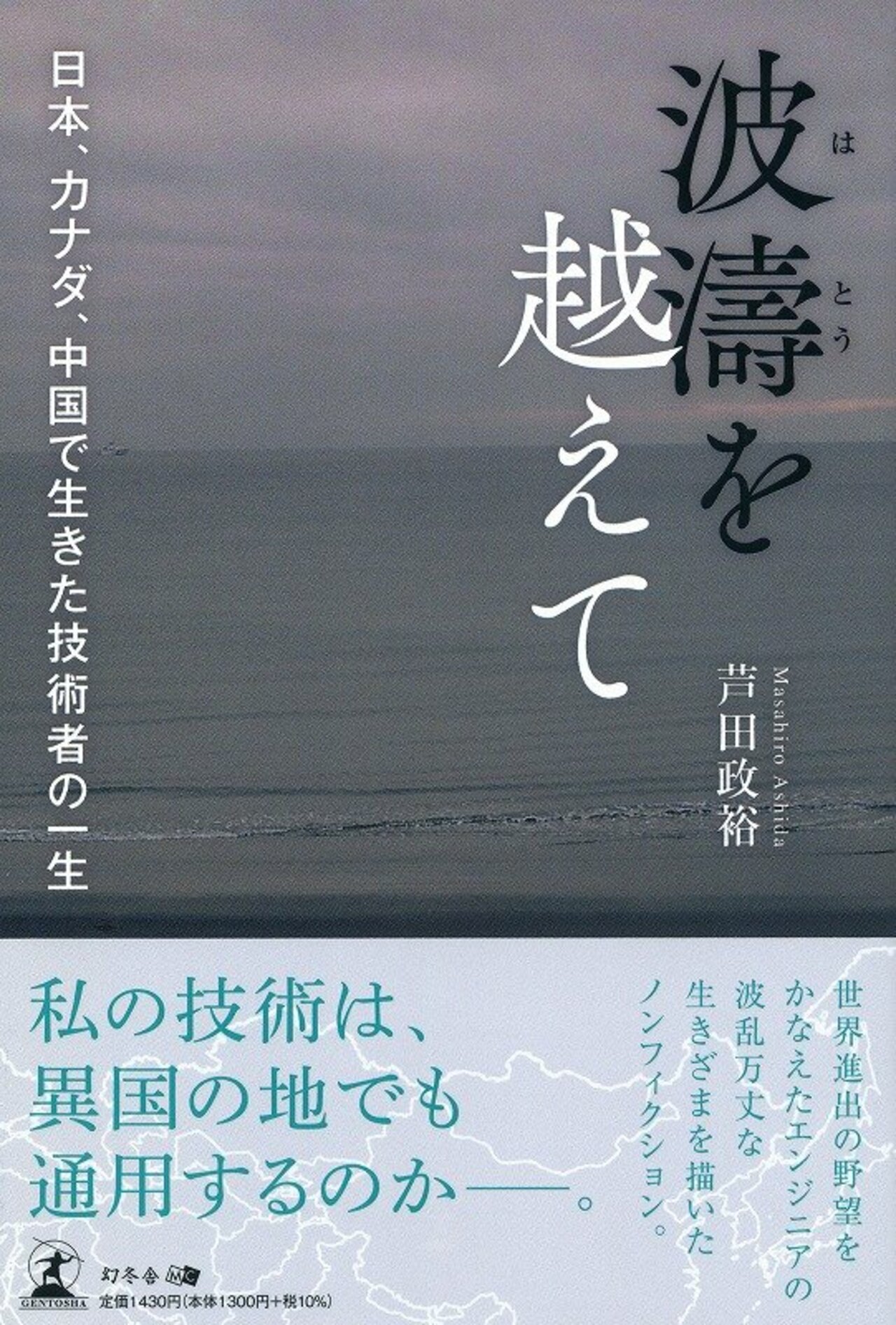火薬類製造業界には東大と九州工大の学閥があった。政裕の大学の専門課程も同じ系統の学閥に属していた。その工場に政裕の大学の先輩が四人いた。配属された研究室に一年前に入社した東大出のエンジニア、根岸氏がある開発テーマに没頭していた。
政裕は研究室の連中の仕事を眺めるだけの日が続いた。
政裕は入社試験で採用されたものの研究要員としては期待されていなかったのではと思うようになっていた。
在学中は金を払って知識を買う関係の中に自分の存在があったが、これからは反対に学校で得た知識を僅かばかりではあっても、それを売ってお金を頂戴する関係の存在になる。
何もしないでいいわけはないだろう。政裕は研究テーマを自分で探し出さなければならない状況におかれていた。
毎日、残業もなく定時で空腹を抱えて十五分歩いて寮に帰ると、おばさんが台所で調理していた。
新入社員の政裕は天麩羅をあげたりして、神妙に手伝いをしていた。料理を食卓に並べて待っていると、七‐八人ほどいた寮生たちも出そろって夕食が始まる。毎日、刺身が付いていた。学生時代どころか、そのずっと以前からそんな夕食にありついたことがなかった。
政裕は大学の機械工学科で三年先輩の梅田さんと八畳間に同室していた。彼は、夕食後はバスで町に出かけていき、飲み歩いていた酒豪だった。寮生活は和気あいあいで楽しかった。
その工場在任中、電気雷管の仕上げ工室で爆発事故が起きた。
その工室の損壊が激しく一人の女子作業員が、目に破片が突きささり盲目になる重傷を負った。
政裕は当時、労組の青年婦人部の役員だったので、彼女を見舞いに何度か病院に出向いたが励ましの言葉がうまく出せなかった。死者が出なかったのは幸いだったが。事故の原因究明に時間がかけられたが推測の域を出ないままだった。
入社以来、政裕は火薬工場という聞いただけでも危険な印象を受ける会社に就職したことについて心の片隅に後悔の念があったことは否定できない。
だが政裕は就職浪人する経済的余裕はなく、就職難で他社からはねられたあと、何とか就職できただけでも有難いと思うべきであった。
火薬工場のみならず、工場とか工事現場とかの名の付く場所は事故発生のリスクがついて回るのが一般であり、工学部を選んだ選択肢にこのような条件が付けられていたのは致し方なく、新入社員の政裕にその現実を知らされたのだった。
政裕は事故現場で冷静な態度で調査していた先輩技術者たちを見た。
いずれ政裕にもその任務が回ってくるのだろう。