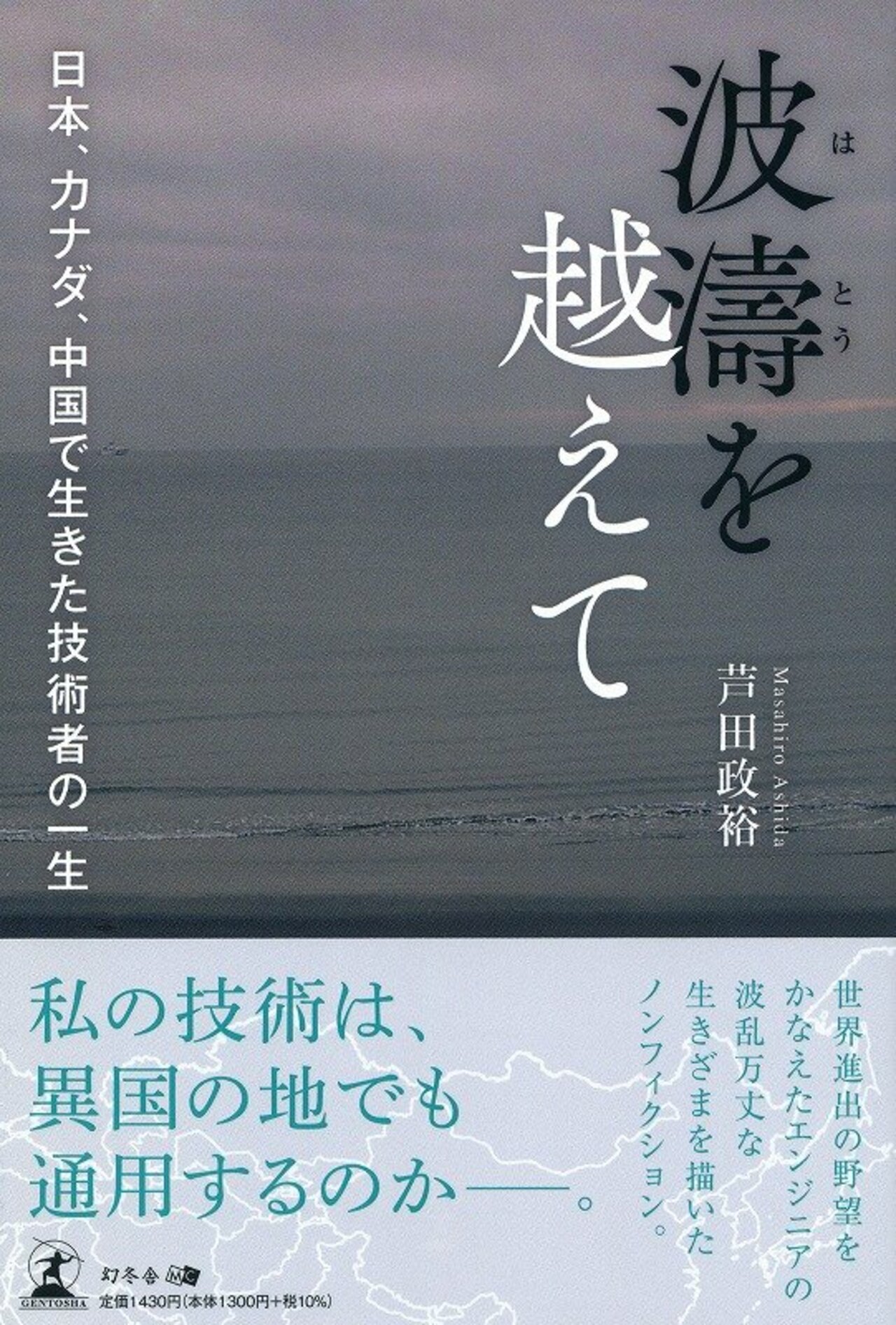父は三十歳台後半と思われる時期に満州、朝鮮、西日本の支配人になり、実の弟(孝三と宅弥)二人に奉天と大連の支店を任せ、朝鮮の京城(今のソウル)を義理の弟(純造)を当てた。
父が京城に滞在中に政裕の二人の兄が生まれ、福岡に帰国してS社の九州工業部を開設したころ政裕が生まれた。
その後、一九三七年に日中戦争勃発、日本に対するアメリカの経済封鎖政策のためS社極東から引き揚げることになり父はその後処理と販売網を引き受けることになった。これは政裕が四歳の時だった。
ある日、二人の出征兵士が我が家に宿泊するために現れた。
中国出陣の集合地である福岡市内の私宅に分散して数日を過ごすことになっていたのだ。父がその宿の提供を申し出ていたらしい。母が酒肴で接待しているのを政裕ら兄弟は正座して見ていたことも覚えている。
博多港で乗船の日、父は政裕を連れて岸壁まで見送りに出向いたが、あまりにも大勢の兵士たちで泊まった二人に会うことができなかった。碇泊していた大きな貨物船に兵士の乗り込みが始まっていた。軍馬が網で釣り上げられ甲板に降ろされているのも見えていた。
兄から聞いたことでは、この二人の兵士から便りが届いていたが、その一人は戦死したそうだ。戦争が身近に感じられる状況になりつつあった。
あとでわかったのは、戦後民主党が政権を取った際、首相になった芦田均が父と同時期に近隣の住民であったことと、政裕の中学の先輩だったことで、政裕が中学三年の時、帰郷の際、母校を訪れ、講堂で全生徒に講演したことがあった。
それと、大戦末期に海軍の神風特攻隊を創設し多くの特攻隊員を死に追いやった大西瀧次郎海軍中将もその同じ村の出身だった。
終戦の年、その屋敷で割腹自殺した。
終戦直後はそのような高官の自殺が相次いだ。敗戦の形勢が色濃くなり、アッツ島で始まった占領していた外地での玉砕が常習化して多くの人命が軍事政権の主導の下で消耗されていったことは言及するまでもない。
その父が肝臓がんにかかり床に臥せるようになったのは支那事変が勃発したころのことだった。
父は西中洲にあったS社のオフィスをたたんで下名島町に店を構え、地行西町の家も整理して家族共々引っ越した。その店は二階が住居になっていて三所帯が住めるほどの部屋があった。