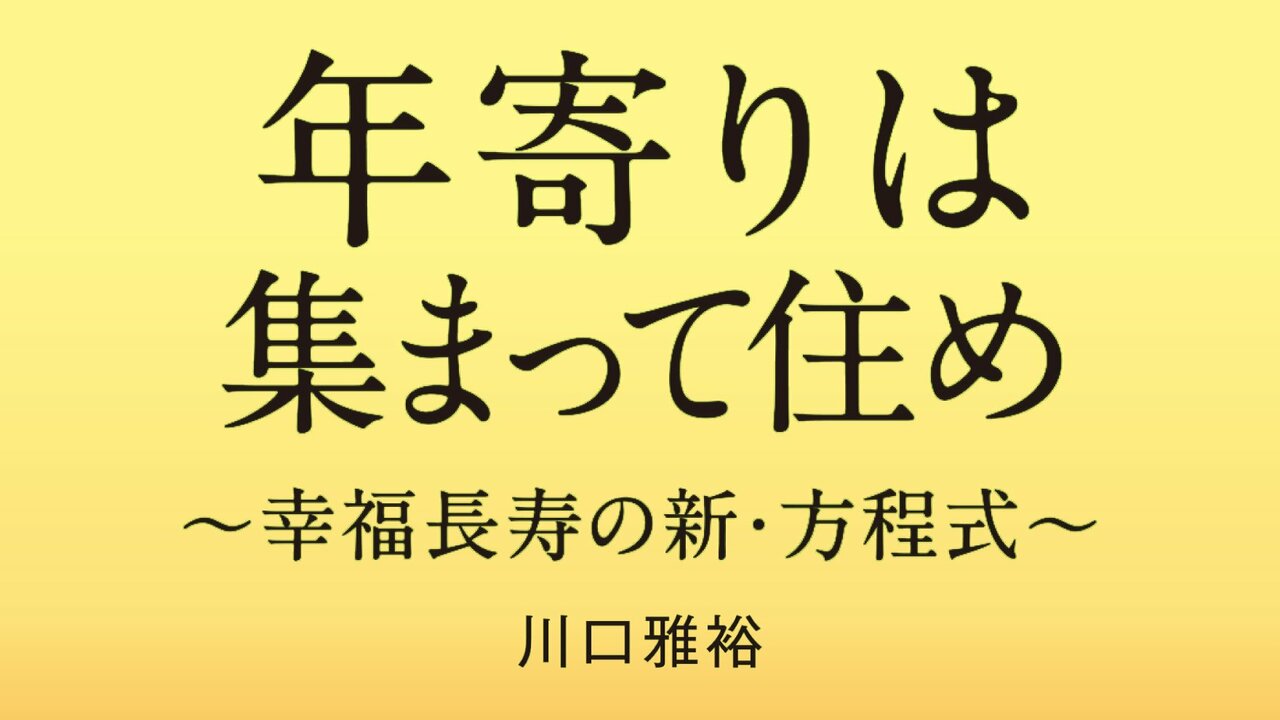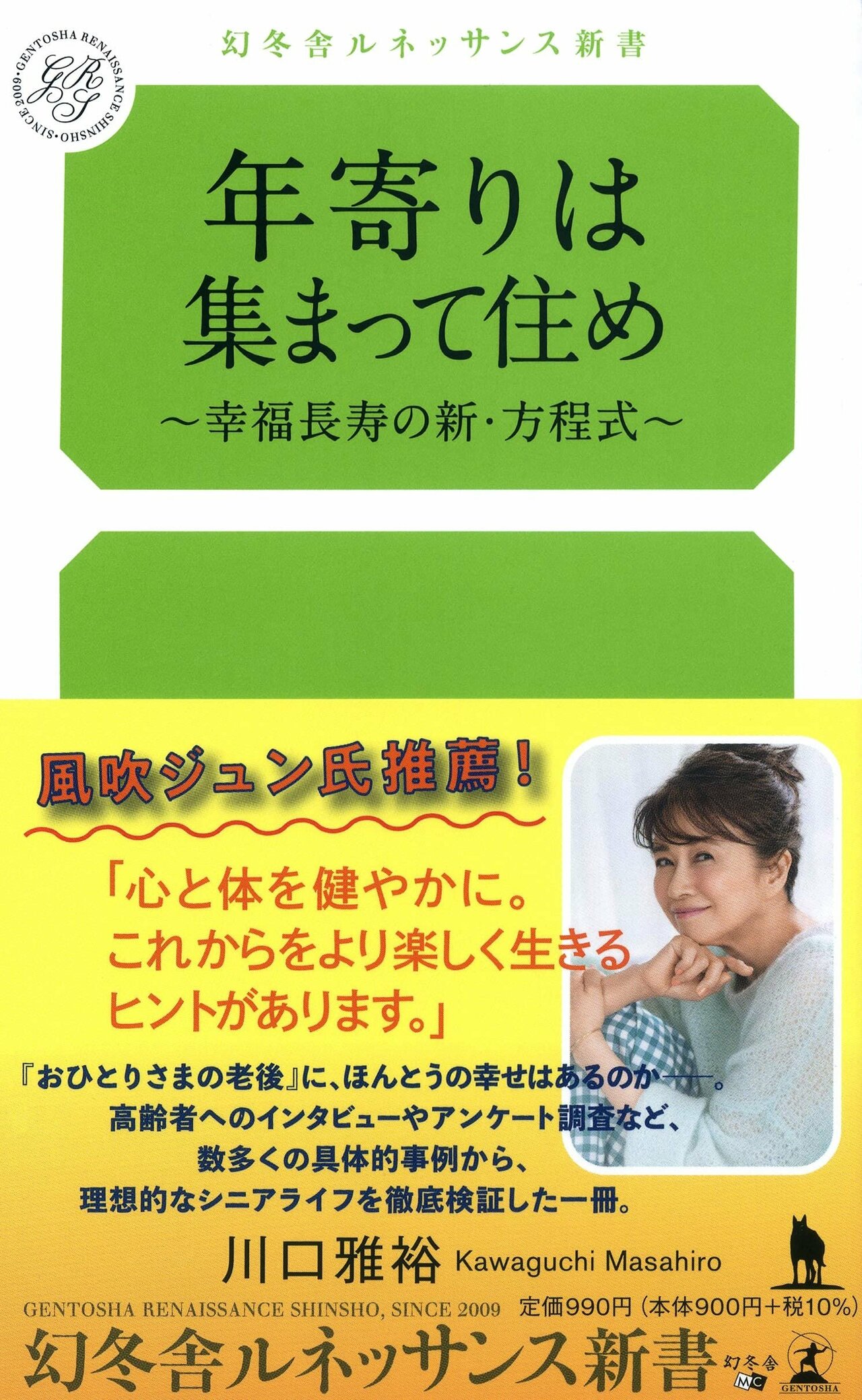鬱陶しい「ムラ共同体」を出た人たち
私の母は今年八一歳になります。二〇代前半に結婚し、祖母を一人残して田舎から神戸に出てきました。一九六〇年代のことです。私は中学生の頃、夏休みになると必ず祖母の家(母親の実家)へ行き三週間くらいは祖母と二人で暮らしていました。到着すると必ず近所のお年寄りたちがやってきて「〇〇さんの孫か。大きくなったなあ」と声をかけてきます。
夕方には、また別の人が野菜やちょっとした料理を持ってやってくる。酒と肴を抱えて、ずかずかと家に上がってくる爺さんもいました。
朝起きると、近くに住んでいた親戚のオジサンが既に顔を赤くして居間でビールを飲んでいて、「お前もそろそろ飲んだらどうや」と勧められて閉口したものです。思い出してみれば、そこでの会話は、「あそこの家の〇〇ちゃんが、〇〇大学に入った」とか「あそこに来た嫁は挨拶もせんし、果樹狩りの手伝いにも来ない」といった噂話がとても多くありました。
その話の内容を詳しくは理解できませんでしたが、狭い世間の中で一人一人の動向が筒抜けになっていて、それを皆があれこれと“評価”していることくらいは分かりました。
調味料の貸し借りは当たり前。風呂がない家の人に、「沸いたよ」と声をかけてお風呂を勧める。(そのまま上がり込んで酒を飲んでいる人もいました)。雨が降ったら、近所の留守宅に行って、洗濯物を入れておいてあげる。葬式は年寄りが仕切って地域全体で行い、全員参加。
挙げていけばきりがありませんが、相互理解と助け合いがある一方で、それがしがらみや軋轢を生み、プライバシーがなく、監視や評価の目にもさらされる。そこには今では想像できないような、濃厚なムラ社会、強いストレスを含んだ共同体、誰も逆らうことができない「世間」という存在がありました。
「世間さまに顔向けができないようなことはしない」というのは、程度の差はあれ日本人に組み込まれた行動規範です。
皆が、世間体を気にしながら生きている。自分の意思や基準ではなく、また、時には法やルールにも増して、「皆がどうしているか」「これまでどうしてきたか」「皆が違和感を持たないようにするためには」と考え、瞬時に様々な忖度を巡らして自らの言動を選択します。世間こそが正義。世間が許せばよくて、世間が許さなければアウト。
世間というものの存在を感じさせる言葉も、「出る杭は打たれる」「身内」「ウチでは/ソトでは」「空気を読む」「村八分」「外人」などたくさんあります。私の母を含めた今の高齢世代は、このような“濃厚な世間”が存在していたムラから都会へ大量に出てきた世代です。
就職や結婚は確かにきっかけではあったけれども、むしろ、そんなムラ共同体の息苦しさ、不自由さから逃れたかったのではないでしょうか。その世代は「都会への憧れ」と言ったのかもしれませんが、本音は「ムラからの脱出欲求」ではなかったかと思います。