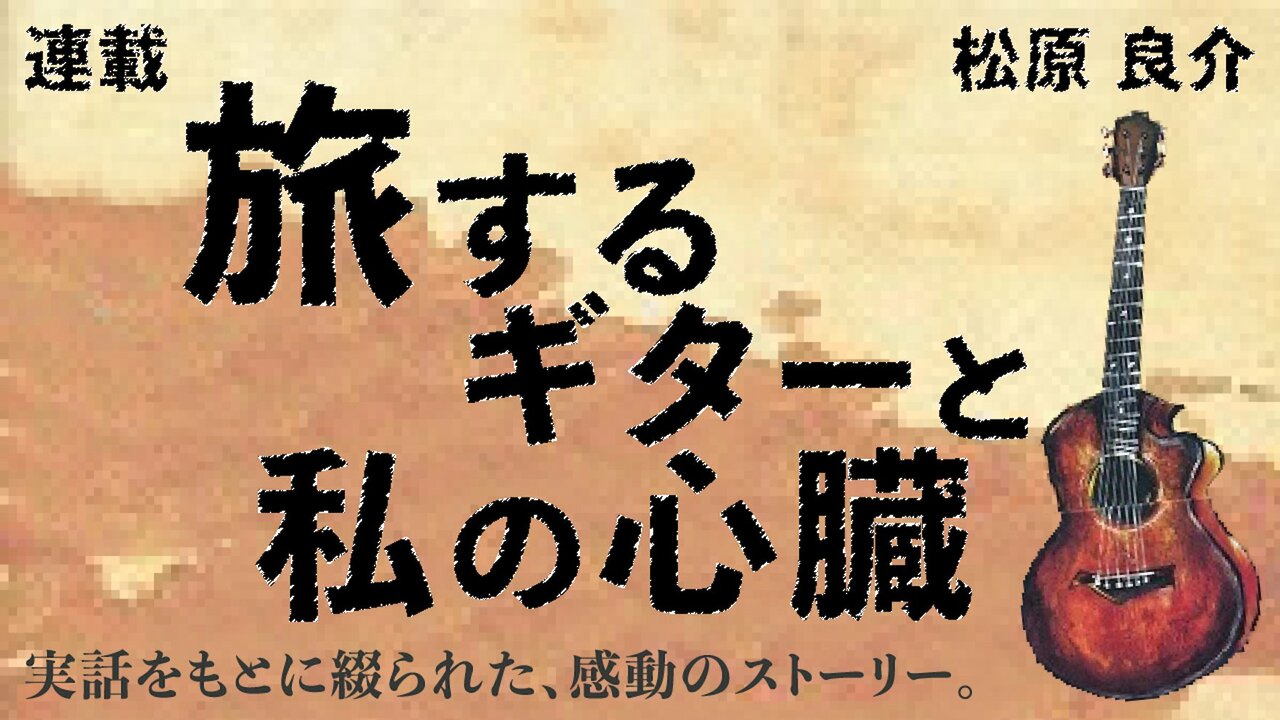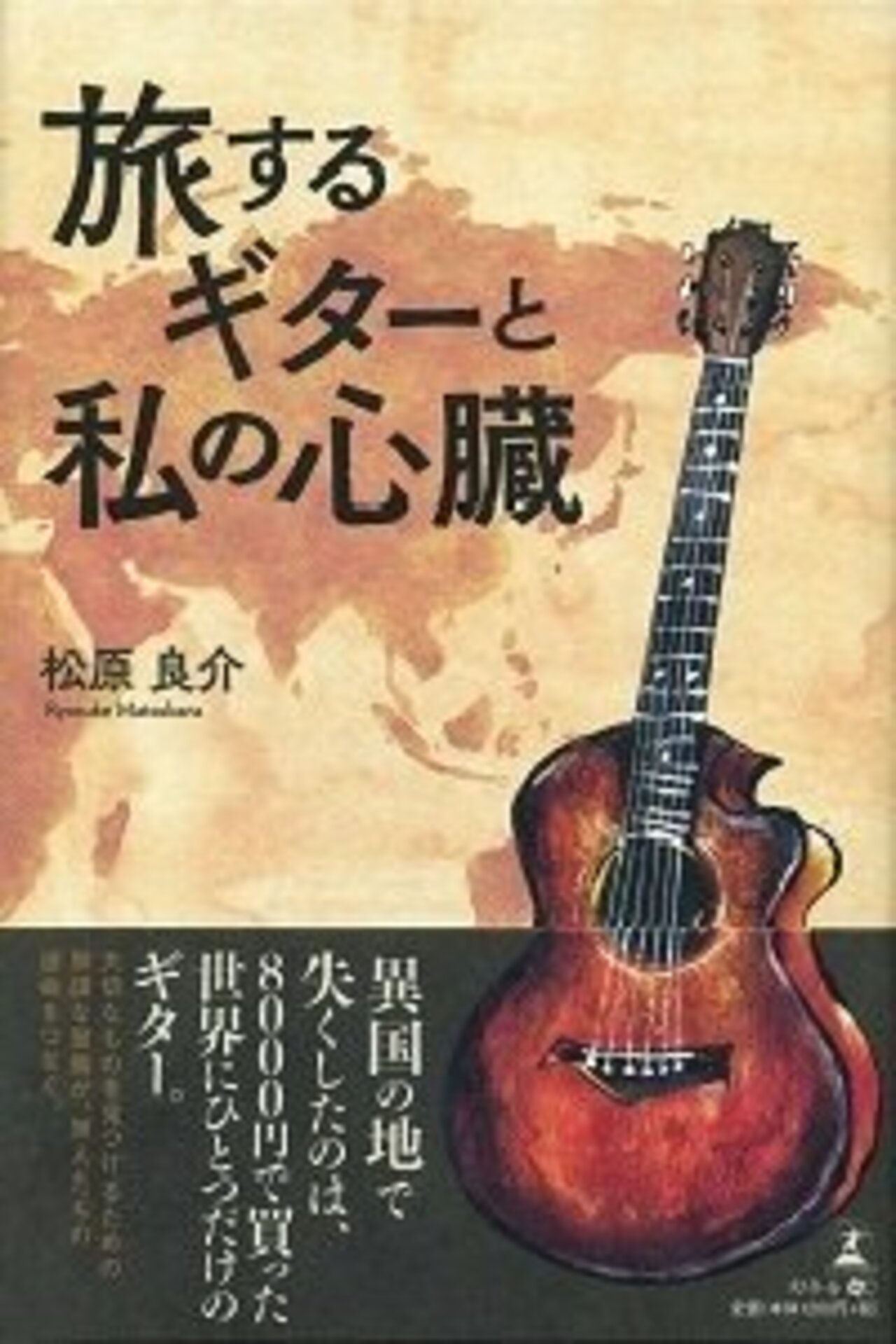〈宇山祐介の事情〉 ホットコーヒー
2012年4月。東京都内の音楽教室。
「宇山先生、ありがとうございました」
私(宇山祐介)の生徒である高橋このみの母親が、教室のドアの取っ手に手をかけながら小さく会釈をした。
このみの母は私と同じくらいの年齢で、上品だが気取った様子もなく、はきはきと話す感じのいい人だった。本当はこのみにピアノを習わせたかったようだったが、9歳になる娘は体験入学のときに手にしたいくつかの楽器のなかからギターを選択した。
このみは私がこの教室で最初に担当した生徒だった。小さな身体を覆い隠してしまいそうな大きさのアコースティックギターを今では器用に弾きこなす。
私が「はい、お疲れさまでした」と、二人を目で追いながら見送ると、いったんドアの向こうに消えたこのみが照れくさそうに戻ってきて、もう一度手を振った。その光景は疲れた私の身体を癒すのに十分な効果があった。私は口元を緩ませたまま、このみに向かって小さく手を振り返した。
〝カチャッ〟という音を立ててドアが閉まると、外界と遮断され、防音対策が施された室内に静けさがやってくる。部屋が静寂に満たされたことに満足すると、私は教室の後ろにある窓に向かって手を伸ばした。少し建付けの悪い窓を開けると、駅前の賑わいとともに、向かいにあるドーナツ屋から甘い香りが飛び込んでくる。
私は誰もいない室内を確認するように、ぐるりと見渡しながら背伸びをすると、口から絞り出したようなうめき声を出した。そして乾燥した冷たい空気が室内に充満したのを感じながら、ため息を一つついた。私は最後の生徒を送り出した後のこの時間が好きだった
教室の後片付けを始めると急に「トントン」と、外からドアを叩く音が聞こえた。室内を探るようにゆっくりとドアが開くと、金髪の頭をひょっこり出しながら、生徒の吉野大樹が現れた。
「先生! お疲れさまです!」
吉野は私と目を合わせると屈託ない笑顔で挨拶をしてみせた。
に挨拶を返してから、ドアの横にかけてある予定表に目をやったが、今日の予定に彼の名前は書かれていなかった。
「あれ、吉野君? 今日このあとレッスンだったっけ?」
「いや、違うんですよ。少し用事があって寄っただけなんです。先生、今ちょっとだけいいですか?」
吉野は金髪の頭をポリポリと指先で掻きながら言った。
「ああ、ちょうどレッスンが終わったところだから大丈夫だよ。どうぞ」
「失礼します」
吉野は部屋に入ると丁寧にドアを閉めた。
「先生、今月の29日の夜って空いていますか? 日曜日なんですけど」
こちらの機嫌を窺うように吉野は尋ねた。
「日曜日? えーっと、日曜日か。日曜日何かあるの?」
「実は、渋谷でライブやるんですけど……観に来てくれませんか?」
吉野はまるで告白する女の子のように、もじもじしながら答えた。
「渋谷のライブハウスなんですけど、ぜひ先生に観に来てほしいんです。20時くらいから出る予定なんですけど厳しいですか?」
「おお、ライブか。20時? ちょっと待ってね」
ここしばらく私は仕事終わりに予定が入っていたことなどなかったが、なんとなく見栄を張って一応カレンダーを確認するふりをした。
「うん、大丈夫。行くよ、仕事も18時には終わるし。何ていうライブハウス?」
私はカレンダーの日曜日を人差し指でトントンっと叩きながら言った。
「ホントですか⁉」
彼はカバンから慌ててチケットを取り出してみせると、2枚のチケットを差し出した。私が代金を払おうとすると、いらないと無邪気に笑ってそれを拒んだ。
それから彼は初めて組んだ自分のバンドのことを話し始めた。最近正式にドラムが決まったことや、今作っているオリジナル曲のことなどを嬉しそうに話す吉野を見ながら、かつて自分にも同じ時代があったことを懐かしく思った。
しばらく話し込んでいると、思い出したように吉野が時計に目をやった。
「あ、こんな時間だ。すみません、俺、これからスタジオで練習あるんで、これで失礼します」
吉野はそう言って忙しくカバンに残りのチケットをしまいこむと部屋を後にした。
扉が閉まると室内には再び静寂が訪れる。
手元に残ったチケットを眺めながら、私は妙な胸の高鳴りを感じて口元を緩めた。
友人の野崎哲也がこの音楽教室を立ち上げたのは、私がこの生徒からライブに招待される3ヵ月前のことだった。
哲也とは中学校からの付き合いで、大学は違ったが上京してからも一緒に過ごすことが多かった。就職してからはお互いしばらく会わない期間があったが、彼が私をギター講師としてスカウトしに来たことをきっかけに再会した。彼の真面目な人柄は相変わらずで、経営する親切指導がウリの音楽教室も評判が良かった。
哲也は昔からの音楽仲間や知り合いのミュージシャンにかたっぱしから声をかけ、彼らの空いているスケジュールを利用して非常勤講師として教室に招いた。
そしてなるべくコストを抑えることで、誰でも気軽に入会できる料金設定を実現させていた。ホームページや音楽教室の入口に“家族割”とか“60歳以上半額”とか、まるでどこかのスマホの割引プランみたいなうたい文句が並んだときは、スタッフ一同“センスがない”、と苦笑したものだった。
ところがふたを開けてみたところ、主婦や仕事を引退した年配者をターゲットとしたこのプランが功を奏して、予想よりも多くの入会希望者を獲得する結果となった。私たち講師陣は、哲也の世の中の流れをつかむ目の鋭さに驚き、いつしか一目置くようになっていた。
音楽教室で私は主にギターを教えていたが、忙しくなるとピアノの授業を引き受けることもあった。9歳からやっていたギターは、一応それなりに自信があったが、趣味の延長で独学しただけのピアノは、いつも教えながら不安と申しわけない気持ちでいっぱいになった。
一応、哲也も各講師の能力を理解したうえで生徒を割り振っていたので、私の担当する生徒は子どもや年配者しかいなかったのだが、当初は慣れない仕事を押し付けられたような気がして、その日になると気が乗らない顔になっていたのが自覚できた。
私が哲也から音楽教室の話を聞いたのは、2012年の年明けすぐのタイミングだった。
あまりリスクをかけない人生を送ってきた哲也が、急に音楽教室を始めることにも驚いたが、自分を講師として招きたいと言ってきたときは冗談かと思った。ただ、当時の私は勤めていた広告代理店の社長が夜逃げをしたせいで、事実上無職になっていたということもあって、その話はまるではかったようなタイミングに思えた。
とはいえ、やったこともない講師というものに対してすぐには気が乗らず、
「講師が足りないって、そもそも何で俺なんだよ」
と最初は呆れたように言い放ってみせていた。
「祐介、どうせ暇なんだろ? 少しでいいからさ、な? 講師が足りなくて困ってんだよ、手伝ってくれないか?」
結局、哲也の勢いに負け、私はとりあえず1ヵ月だけ引き受けることにした。仕事を探しながら片手間でやろうと、軽い気持ちで引き受けた臨時講師のはずだったが、実際にやってみると、その仕事は甘いものではなかった。