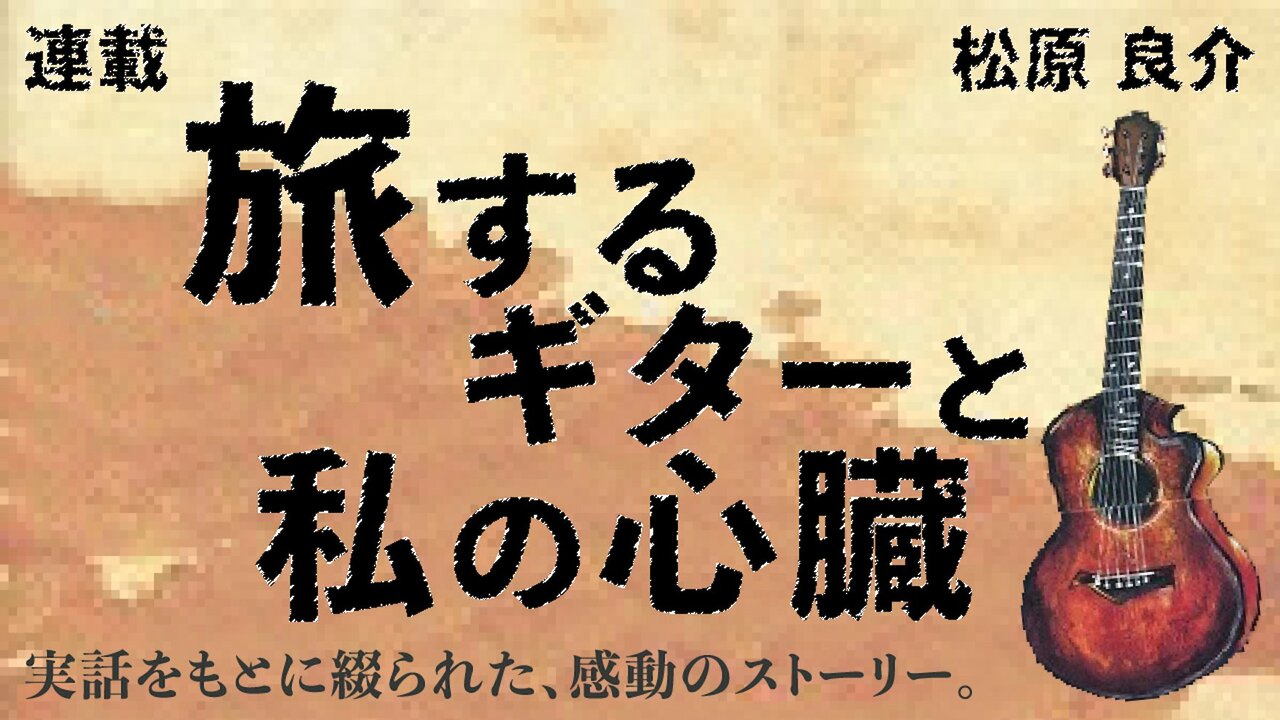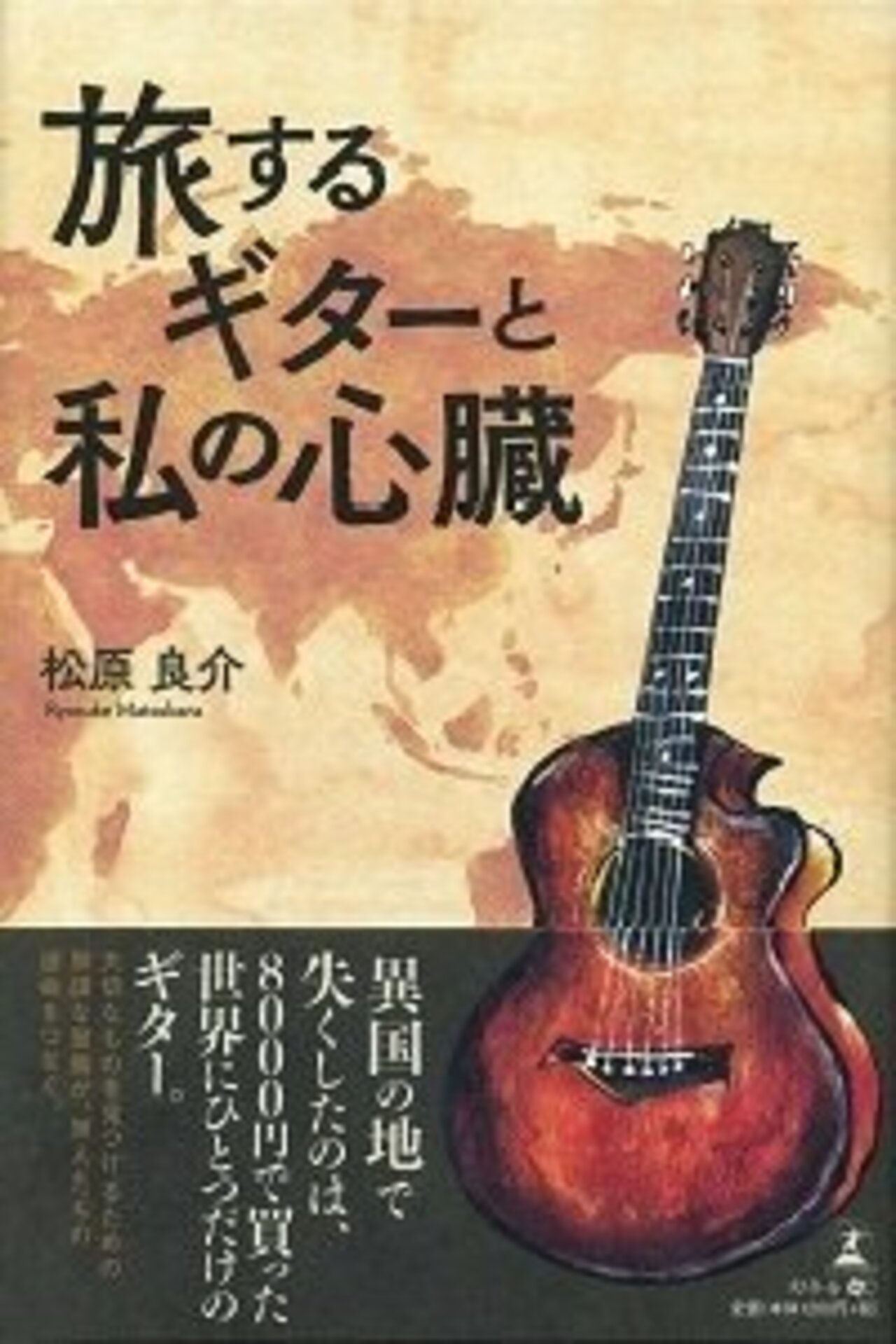10代~60代の生徒たちを相手に1コマ1時間のレッスンをこなすのは、事前の準備を含む綿密なスケジューリング能力が求められる重労働だったのである。私は哲也やほかの講師たちの授業の進め方を見ながら参考にしたが、やることなすこと初めてだったので、結局すべてが手探りで進めることとなった。レッスンが終わったら、すぐさま机に向かい、生徒たちのレベルに合わせて譜面を作ったり、課題曲を探したりした。
講師の1日はあまりにも短く感じられた。
効率的なやり方を模索しているうちに、哲也と約束していた1ヵ月はあっという間に過ぎたが、その頃になると私の気持ちに少しずつ変化が現れていた。
何年も離れていた楽器に再び触る懐かしさと、音楽を教えるという新鮮な気持ちは、いつしか私のモチベーションに変わり、気がつけば次のレッスンを待ち遠しく思うようになっていた。そうして生徒たちが成長する姿を追いかけているうちに、過去の契約を気にする余裕などなくなっていたのである。
ある日、いつものように駅前の広場を通ったときのことだった。
暗くなった広場の中央にギターを弾きながら歌う青年の姿があった。街灯がスポットライトのように彼を照らしていた。寒いなか手袋もせずにギターを弾く彼の指を見て、私は思い出したように自分の手に白い息をかけた。
彼の透きとおるような高い声が胸のなかにスッと入り込んできた。
歌う青年の様子を気にしながら、少し歩くと音楽教室の生徒・緒形重治がいた。教室で最年長の生徒である緒形は、青年の歌う姿を優しく見つめていた。私は緒形のそばにゆっくり歩み寄り、声をかけた。
「緒形さん、どうも」
「ああ、先生。こんな時間までお疲れさまです」
緒形はトレードマークのフェルト帽に手をやりながら私に会釈をすると、再び視線を広場で歌う青年に向けた。その姿を見ながら、私は緒形と出会ったときのことを思い出していた。
音楽教室ができてすぐの頃、茶色いフェルト帽をかぶった緒形がピアノを習うためにやって来たのは印象的な出来事だった。
その還暦を過ぎた男性は、楽器に触ったことすらないようだったが、妻の誕生日である4月18日までに『ハッピーバースデー』をピアノで弾けるようになりたいと話していた。さらに詳しい事情を伺うと、妻にプレゼントを渡したいと考えたが、欲しいものを聞いても、36年連れ添った妻は〝今さら何もいらない〟、と困った顔をするだけだったという。
困った緒形は、たまたま駅前にできたこの教室の前を通ったとき、娘が妻の誕生日になると自宅にあるピアノで『ハッピーバースデー』を弾いていたことを思い出したという。
そんなことを思い出しながら、私は緒形と広場で歌う青年を眺めていた。
互いの白い息がゆっくりと顔の周りを漂って消えた。音楽教室での緒形は、自分の半分ほどの年齢の私に対して、いつも敬意を払って話してくれた。その姿を見るたびに、自分も歳をとったらこうありたいと感じていた。すらりと背筋の伸びた様子や口調、そして見事なほどにセピア色のコートを着こなす姿。トレードマークの帽子の下には整えられた白髪がしまい込まれ、皺の多い瞼に隠れる奥まった瞳からは、まだ子どものような好奇心が感じられた。還暦を過ぎた者が出す独特の若々しさがあるものだと、緒形を見て私は思った。
いつの間にか時計の針は9時を指していた。駅前の弁当屋がシャッターを降ろす準備を始めるのが見えた。
「先生、音楽とは不思議なものですね」
緒形が唐突に言った。
「不思議?」
思わず私はオウムのように言葉をそのまま返した。
「ええ、不思議です」緒形は少し笑って見せると、ゆっくりと話し出した。
「先生、なぜ彼はこんな寒空の下でお客さんもいないのに、ああして歌っているんだと思います?」
緒形の質問に私は言葉を詰まらせてしまい、青年のほうに目を向けながら考え込んでしまった。気まずくなった空気を感じた緒形は、
「私はすぐそこのマンションに住んでいましてね。毎日ここを通っていたんです」
そう言うと緒形は駅の向こうに見える高層マンションを指さした。
このあたりは高級マンションが多いことで知られている。とっさに私は、緒形の質問の真意を探ることも忘れて、彼の住むマンションの価格を予想していた。
「実は先週、そこで歌っている青年と話をしましてね。聞くと彼は、ほぼ毎日ここで歌っているそうです。お客さんもいないのに」
緒形は私のほうを向きながら、なぞかけを楽しむ子どものように微笑んだ。
「え? 緒形さん、彼に話しかけたんですか?」
「ええ、おかしいでしょう?」
そう言って緒形は思い出したように笑った。
「でもね、そこなんですよ、不思議なのは」
緒形は口から白い息を漏らしながらゆっくり話し始めた。
「私は今まで何度もこの広場を通っていたんですが、彼がそこでギターを弾いていたことに全然気がつかなかったんです。彼に気がついたのは……いえ、彼のギターが聞こえるようになったのは、つい最近なんです」
そう言って緒形はゆっくりとこっちを向いた。
「先生からピアノを教えてもらうようになってからなんです」
私は目の前の還暦を過ぎた生徒が、音楽を学ぶことで世のなかの見え方が変わったことを知った。後から思い出してみると、講師として誇らしい出来事に遭遇したようにも感じるが、そのときは突然すぎて頭が真っ白になっただけであった。
道端で歌を聞きながら私と緒形が話し込んでいると、観客二人の視線を感じた青年は笑顔を作り、歌いながら器用に小さくこちらに向かって会釈をした。それに応えるように緒形は、スッと右手を上げた。
「自分はどちらかというと、ああいった若者を苦手にしていたんですが……それがどうしたことか、温かいコーヒーをわざわざ彼に差し入れしてまで、彼と話がしたいと思うようになったんです」
緒形はポケットから手を出してコーヒーを2つ持つ仕草をしながら言った。
「寒空の下で彼と音楽について話すなんて、以前の私なら想像すらできないことでした。そして何度か話すうちに彼は、私とコーヒーを飲みながら話ができたことが、ここで歌っている大きな意味だと言ってくれたんです」
緒形は皺の多い顔をくしゃくしゃにして笑みを作ると、
「ね? 不思議でしょう?」
と一言付け加えるように言った。
帰りの電車を待ちながら、私はさっきの出来事を思い出していた。
フェルト帽が似合う年老いた男性も、広場でギターを弾いていた吉野大樹もおそらくこの小さな奇跡を知らないでいるだろう。
世界で私だけが知る贅沢な奇跡だ。
まるで接点がないであろう二人が寒空の下でコーヒーをすすりながら話す姿を思い浮かべながら、私は思わず口元を緩めた。