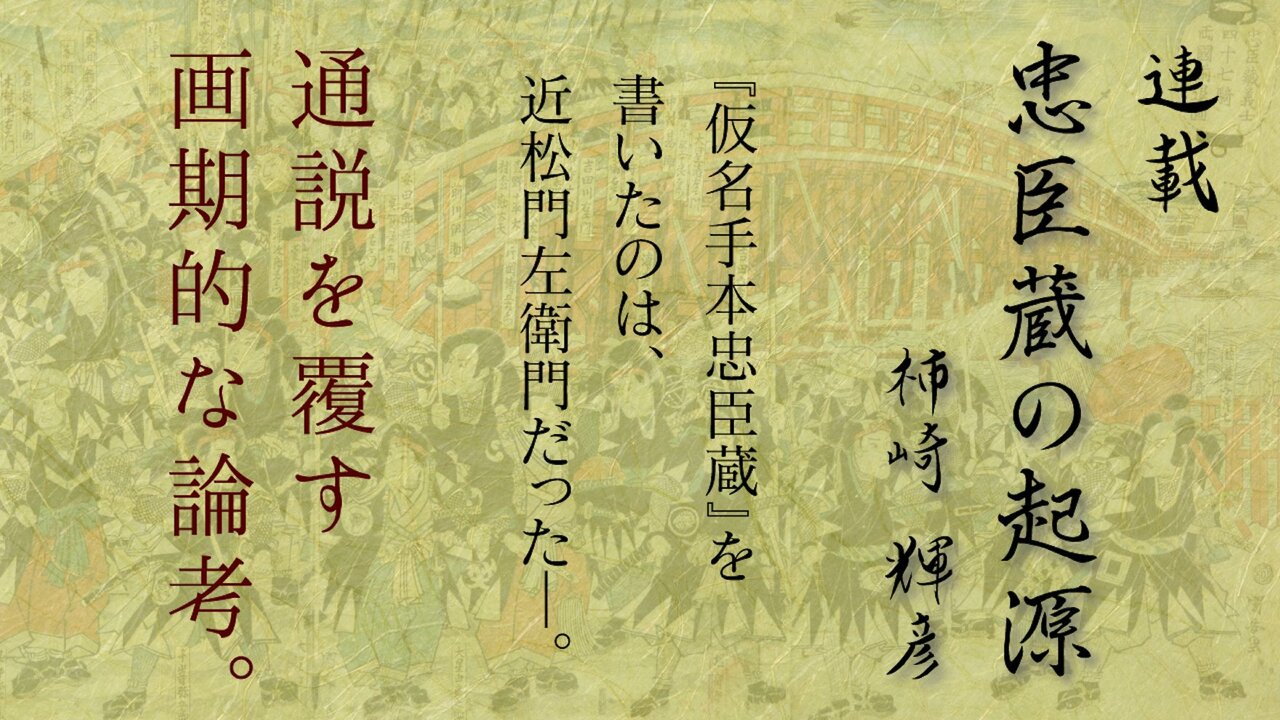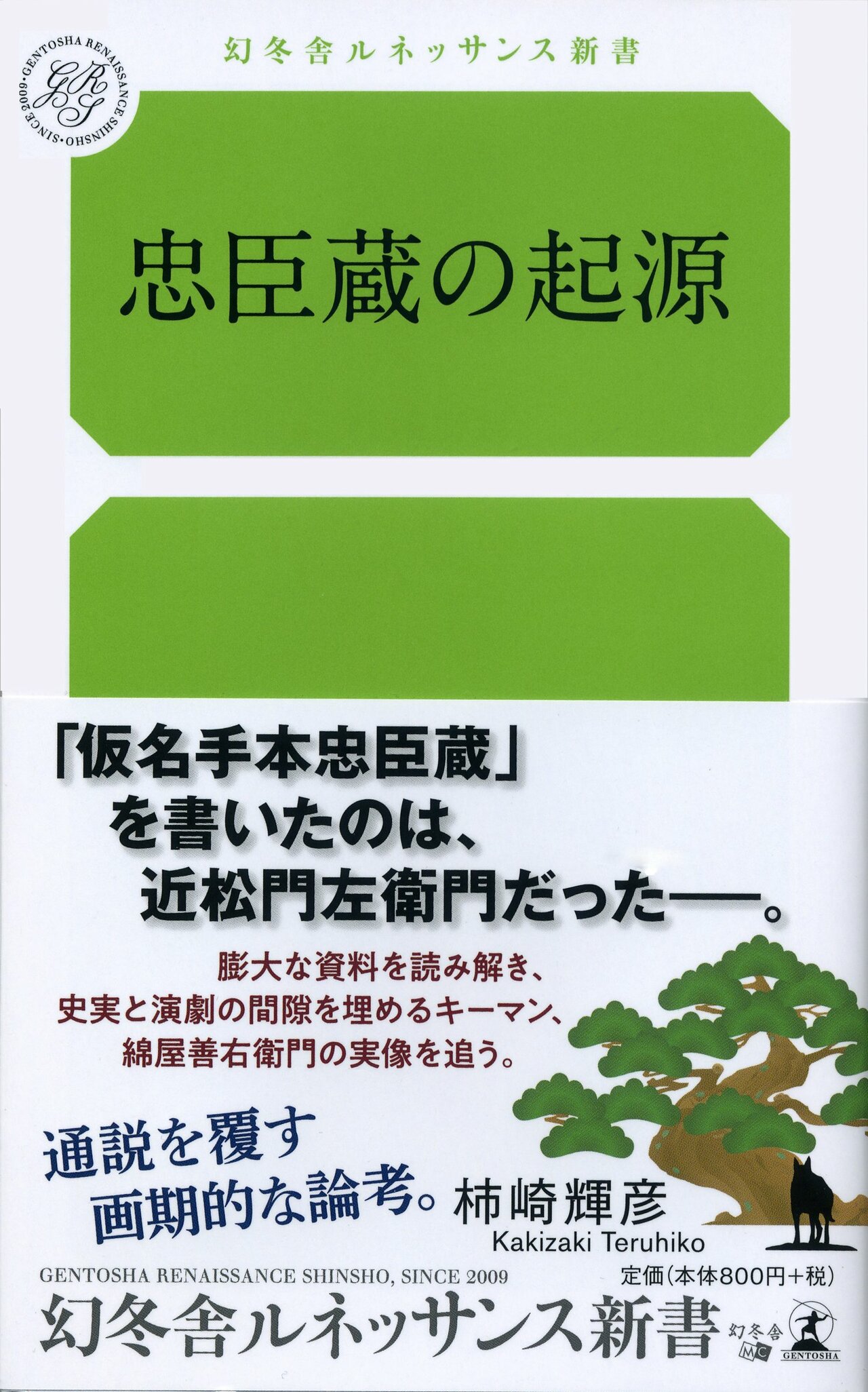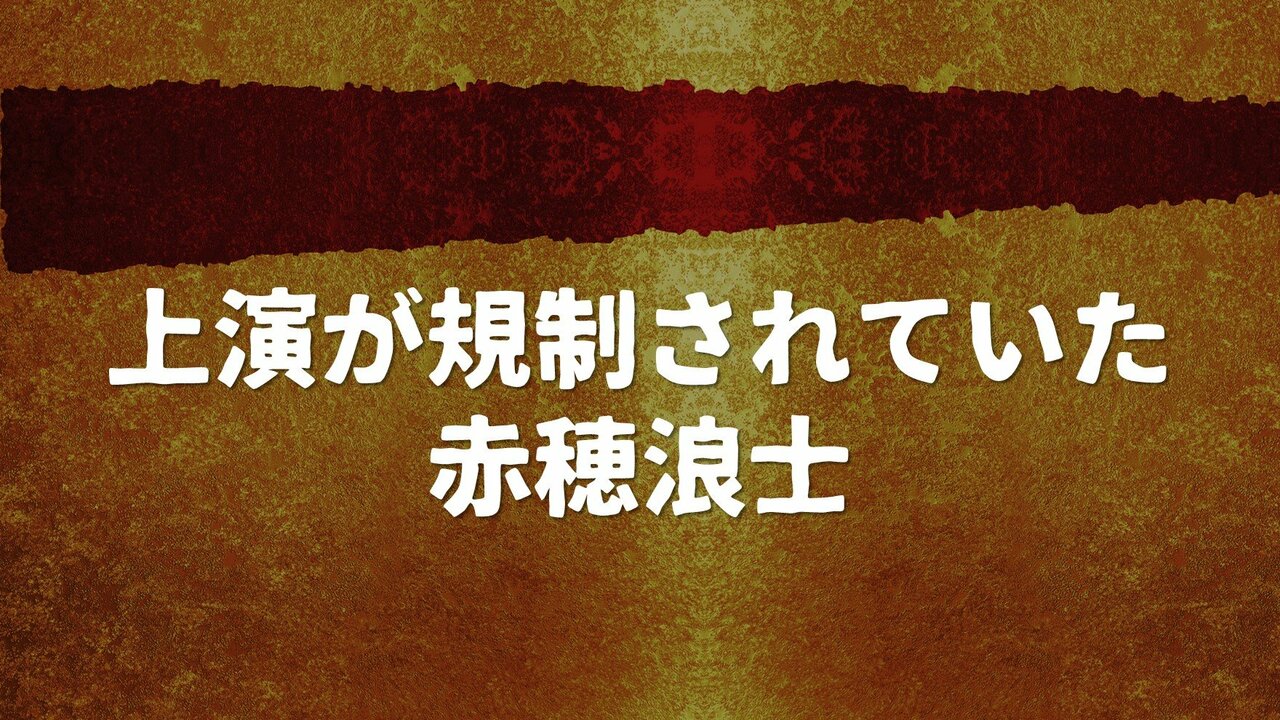第二章 忠臣蔵とは何か
事件の伝承
元禄赤穂事件を最も早く取り入れたのが、討入りから二ヶ月後の二月十六日に江戸中村座で上演された『曙曽我夜討』とされている。赤穂浪士切腹から僅か十二日後のことであったが、公儀により三日で中止させられている。この芝居の中に仇討ちを模した見せ場があったようであるが、それが赤穂浪士を意図していたものであったかについては不明で、観客側が事件との因果関係をどれ程認識していたかは最早確認することが出来ない。
『曙曽我夜討』上演の事実は、江戸の俳諧師宝井其角と京都在住の浄瑠璃作者近松門左衛門との書簡のなかに見える。ところが、『曙曽我夜討』について触れた史料が他に見当たらないことや歌舞伎浄瑠璃研究家の裕田善雄などが、書簡の文面そのものに矛盾を指摘していることから書簡そのものを偽書とする考えが支配的である。
一方で、歌舞伎研究家の渡辺保は著書『忠臣蔵 もう一つの歴史感覚』で、書簡にある文面に矛盾はないとの見解を示し、この書簡を偽書とは断定できないとしている。赤穂市発行の『忠臣蔵』第二巻では、別の見解が紹介されているが、これ以上は本題の趣旨から逸れるのでここまでに留めておくが、書簡がもしも真書であったとするならば江戸中村座での『曙曽我夜討』の上演中止からは、少なくとも公儀の検閲に対しては、宝井並びに近松双方共に敏感であった様子が窺える。
その後も、元禄赤穂事件を取り入れた芝居が上演されてはいたが、やはり公儀の検閲を気にしてか事件の描写を極端に強調することはなく、逆に興行側はお咎めを想定して、いくつもの理論武装を用意していたはずである。そのため、どれもが小粒な作品となる傾向にあったことは否めない。
しかも、興行側が敢えて公儀に挑発的な行為に及ぶ必然性も見当たらない。そんな中で、最大のインパクトをもって登場したのが『仮名手本忠臣蔵』である。
江戸時代は公儀が絶対的権力を握っていた時代である。とくに元禄期においては人より家畜のほうが優先される『生類憐れみの令』が施行され、強い締め付けのもと、公儀により切腹の刑に処せられた赤穂浪士らを巷で積極的に語られることはなく、事件の詳細や真相については、それ程流布されることはなかったが、それを補って余りあるほどに『仮名手本忠臣蔵』の完成度は高く、芝居の内容そのものが恰も事実であるかのように伝承され、元禄赤穂事件を伝えるものとしては、いみじくも『仮名手本忠臣蔵』がその役割を独占し、この歪な状態を維持したまま広く人口に膾炙していくことになる。
事件についての本格的な調査研究が始まるのは明治時代に入ってからのことである。契機となったのが明治維新である。
明治政府が樹立された直後の明治元年(一八六八)十一月五日、明治天皇が京都から東京に行幸される際に、高輪泉岳寺の赤穂浪士墓域に勅使を遣わされ、大石内蔵助の墓前において浪士らを弔い義士として賞賛するとの勅宣と共に金幣を賜られた。これにより四十七士は切腹から百六十五年の月日を経て晴れて市民権を得ることになる。
今日では、十二月十四日の討入りの日に因んで、赤穂浪士の遺徳を偲び彼らの霊を弔う祭りが日本全国の赤穂浪士所縁の地で開催されている。なかでも、人出の多いことで知られるのが、忠臣蔵の故郷播州赤穂の義士祭で市をあげての行事となっている。
赤穂浪士に関連する祭事としては、おそらく最も古くから存在する祭りであると考えられるが、それでも第一回目は赤穂浪士切腹から二百年後の明治三十六年(一九〇三)のことである。また、東京高輪泉岳寺で開催される赤穂義士祭も有名であるが、この赤穂義士祭が始まったのは終戦後の昭和二十五年(一九五〇)のことである。今日では、恒例となっている義士祭ではあるが、何れも思いのほか歴史は浅いことがわかる。