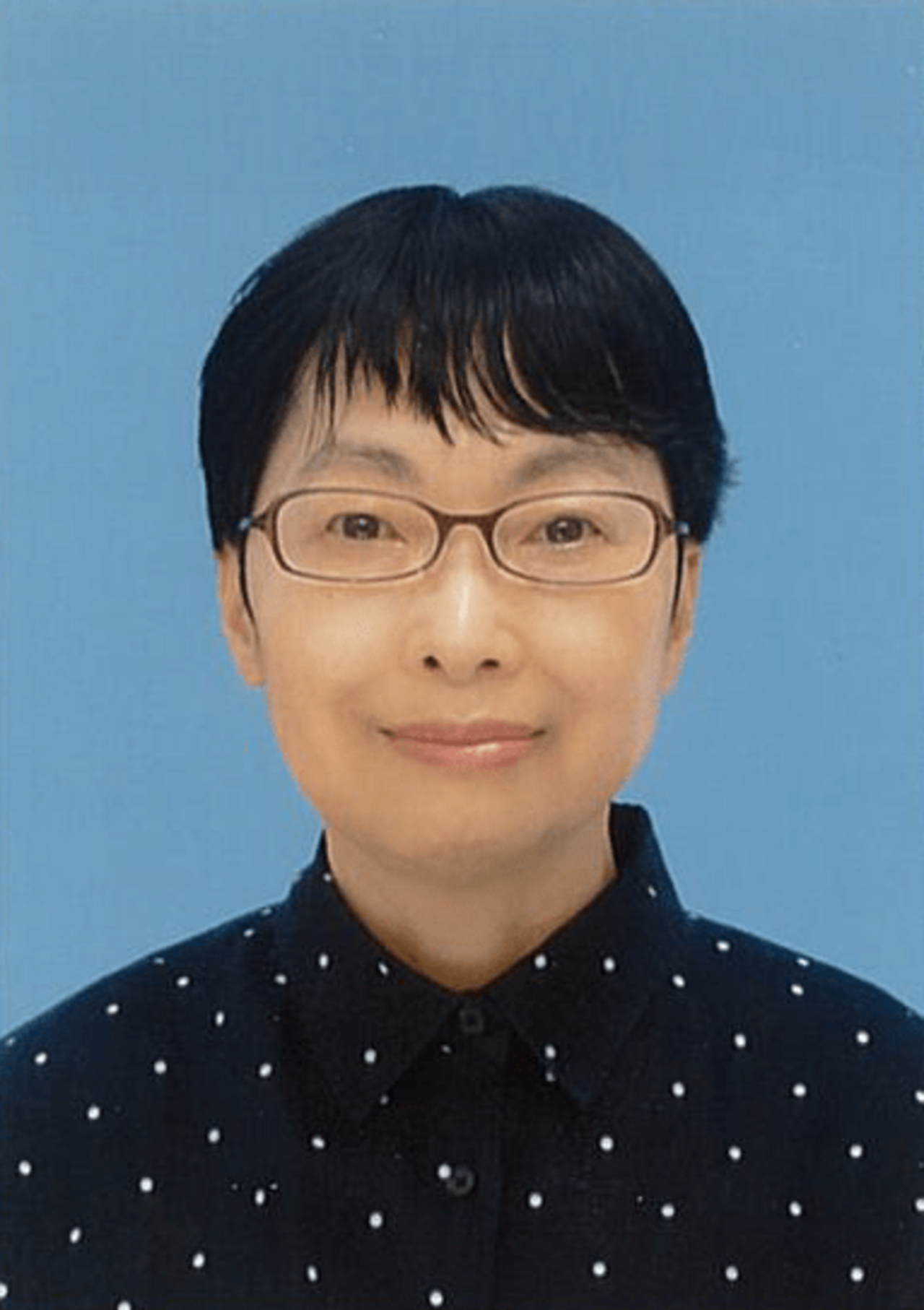三月になり、及川は大学を卒業して、四月から、新社会人として、大手町の会社で勤務するようになっていた。弓子は大学の四年生になっていた。
弓子は、子どもの時から読書が好きで、いつも、よく本を読んでいた。色々なジャンルの本を読むけれど、特に小説が好きだった。それで大学は文学部の国文科を選んで入学していた。将来は、本に関係する職業に就きたいと考えていた。それで、就職活動は、出版社を中心に行っていた。
八月になって、弓子は、飯田橋にある出版社に就職が決まった。それで弓子と及川は、また大学の近くにあるイタリアンレストランで、就職祝いの食事会をすることにした。弓子は、子どもの時からの夢が叶って、幸せな気分になっていた。及川も、とても喜んで、二人で、安心して笑顔になっていた。
三月になって弓子が大学を卒業すると、弓子と及川は、恋人として付き合うようになっていた。二人の交際は、とても順調だった。弓子は出版社での仕事にも、やりがいを感じていて、仕事もプライベートも充実していて、気分はバラ色だった。
弓子が二十六歳になった年に、及川に会社から辞令が下った。それは、ニューヨークへ転勤という内容だった。
及川は、弓子にプロポーズして、一緒にニューヨークへついてきて欲しいと言った。弓子は、及川のことが好きだったけれど、出版社を辞めなければならないことに、ためらいを感じた。二週間悩んで、結局プロポーズは、断ってしまった。
そして時は流れ、弓子は三十八歳になっていた。この頃は、弓子は、出版社で出版企画部長として働くようになっていた。弓子は、及川と別れてからは、恋人を作るようなこともなく、仕事に専念して、部下からも慕われる存在となっていた。
そんなある日、弓子は、仕事の打ち合わせの帰りで、大手町の地下街を歩いていた。
「川上さん?」
弓子は後ろで、自分の名前を呼ぶ声を聞いて、振り返った。なんと、そこには及川が立っていた。
「ああ、やっぱり弓子だ」
弓子は突然の及川の出現に驚いた。
「日本に五年前に帰ってきたんだ」
二人は、しばらく地下街の通路で立ち話をして、それから、東京駅にある、イタリアンレストランで夕食をとることにした。久々の偶然の再会に、二人は、お互いに懐しいものを感じていた。及川の左手の薬指には、指輪が光っていた。
「弓子に振られちゃって、意気消沈しちゃったよ」
及川は、そう言うと、ワインを一口飲んだ。
「でも、日本に帰ってきて、人の紹介で知り合って、結婚したんだ。今、二歳の娘がいるよ」
「そうなんだ。よかった。おめでとう。及川さんが幸せに暮らしていることを知って、私もうれしい」
「弓子は、結婚は?」
「していない。仕事一筋」
「そうなんだ。よっぽど出版社の仕事が好きなんだね」
二人は、そんな話をしながら、別れ際に、メールアドレスの交換をした。二人とも、メールアドレスは、学生時代とは異なった、新しいものを使っていた。
その頃、弓子は、勤務先の出版社から、徒歩十分ほどのところにある、賃貸マンションの一室に暮らしていた。ダイニングキッチンとリビングが一緒になった部屋の他に、寝室のある、築五年のマンションだ。
弓子は、その夜、及川のことを考えていた。及川は、一八〇センチの身長がさらに高くなったように感じるほど、光り輝いていた。仕事も順調で、結婚もして、二歳の娘もいて、きっと人生幸せいっぱいで暮らしているんだろうなと思った。
そして、自分が及川のプロポーズを断ってしまったことを、少し後悔した。
それで、自分は、自分の仕事に誇りを持っていて、仕事と結婚したのだと、思うことにした。
その晩は、弓子は、ぐっすり眠った。