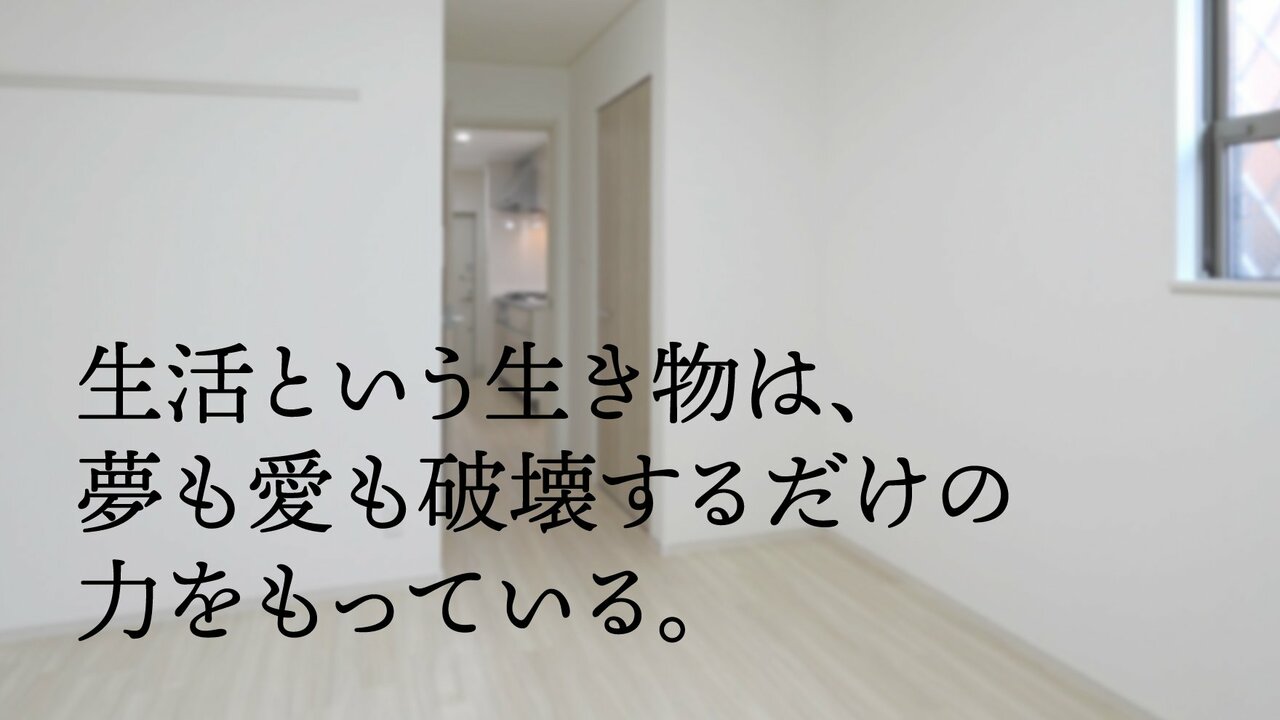再会の扉
そして年が明け、一月と二月と三月は飛ぶように過ぎ、世は新しい年度を迎える四月になった。新入生の初々しい姿が、眩しくて微笑ましい季節である。
私の中でも、新しい命がすくすくと育っていた。さらに二カ月が過ぎ、新年度気分も落ち着いた頃、私はわが子を迎えるために病院のベッドでその時を待っていた。
園井にはこのことを話していない。彼から思いがけない言葉を聞いたのは去年の夏。付き合い始めて一年が過ぎた頃だった。新しく福岡の会社に中途採用が決まった彼は、私に一緒に来てほしいと言った。そして結婚してほしいのだと。
「今すぐっていう意味じゃないんだ。未代がうんって言ってくれたら、俺、二人で住める部屋探して待ってる。未代の準備ができるまで、先に行って待ってるからさ。……慌てなくていいんだ」
転勤の話は驚いたし、プロポーズはもっと驚いた。自分がまさかこんなに早く結婚について考えるとは思ってもいなかった。しかも相手が園井佑人となれば、二度と来ないレベルの話である。イケメンで性格も優しく、控えめで気配りもできる。仕事もできる。何より年下の至らない私を大切に扱ってくれる。
ただ私の立場は重い。普通の家庭でどこかに勤めているのなら、何のためらいもなくその場ではいと答えた。私も彼が大好きだったからだ。
私は未熟で頼りないけれど、立場上は喫茶店のオーナーであり、自宅の家主でもある。
父の残してくれた財産を守りながら、少しずつ融資の残高を減らしている身だ。彼と結婚して福岡で暮らすということは、この財産を処分すれば借入金は清算できるが、その結果帰るところがなくなるという意味でもある。
彼の夢にはついていけなかったが、自分の判断は正しかったと思っている。遠距離恋愛で結論を先送りにすることもできただろう。仮に結婚したとしても、一流でない私立大学中退で無資格の女が、見ず知らずの土地でいい条件の就職などできるわけがない。かといって四十を過ぎてもパートの連続では、家計が楽にならない。優秀な園井が高給取りになって、専業主婦でいられる可能性はゼロではないが、初めからそれをあてにするのは甘すぎるというものだ。
つまり愛しているだけでは、彼を助けることができない。生活という生き物は、その環境次第で夢も愛も破壊するだけの力をもっている。臆病な私は立ちすくんでしまい、目の前から延びていた道を先に進めなかった。文字通り全てを捨てて彼の元に飛び込むなんて、その時の私には考えられなかったのだ。