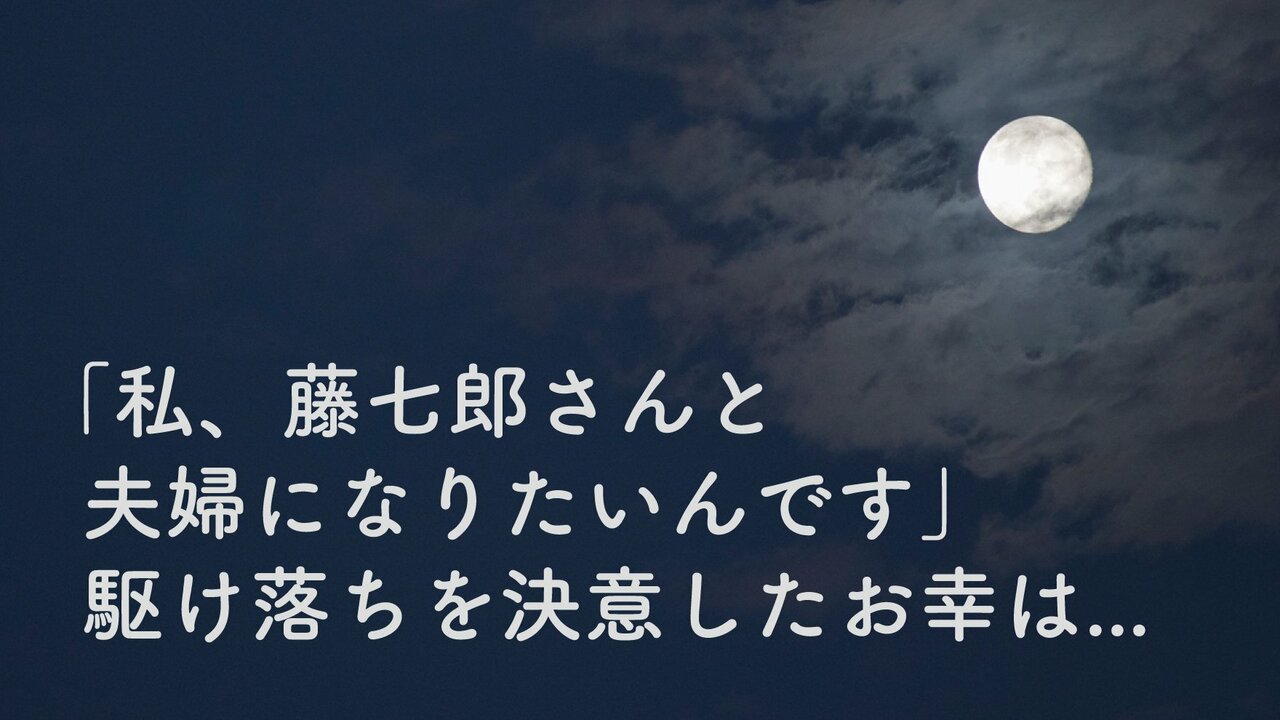さすがに心配になった二人はお菊に様子を見に行かせた。
「お幸ちゃん」
「――お菊さん」
「どうしちまったんだい。すっかり――やつれちまって。目も腫れているじゃあないか。お夕飯、できているよ。少しでもいいから食べておくれ」
「……そんな気分じゃありません」
「……お幸ちゃん……」
お幸はすっかり気落ちして、いつもは赤みがさしている頬も、心なしか青白くなっている。
生きる気力さえ失われているようにも感じた。
藤七郎が来てから生き生きとしていたお幸の面影がすっかり失われてしまっている。
お菊は与七も藤七郎を可愛がっていたのを知っていたから、どうしてお幸と藤七郎の仲を反対するのだろうかと不思議だった。
「お幸ちゃんは藤七郎ちゃんのことを好いているんだね」
「……はい。でも、おじいさまとおばあさまが許してくれなくて」
「……そうだったのかい」
お菊はそれを聞いて話しながら泣き崩れるお幸を抱き締めた。