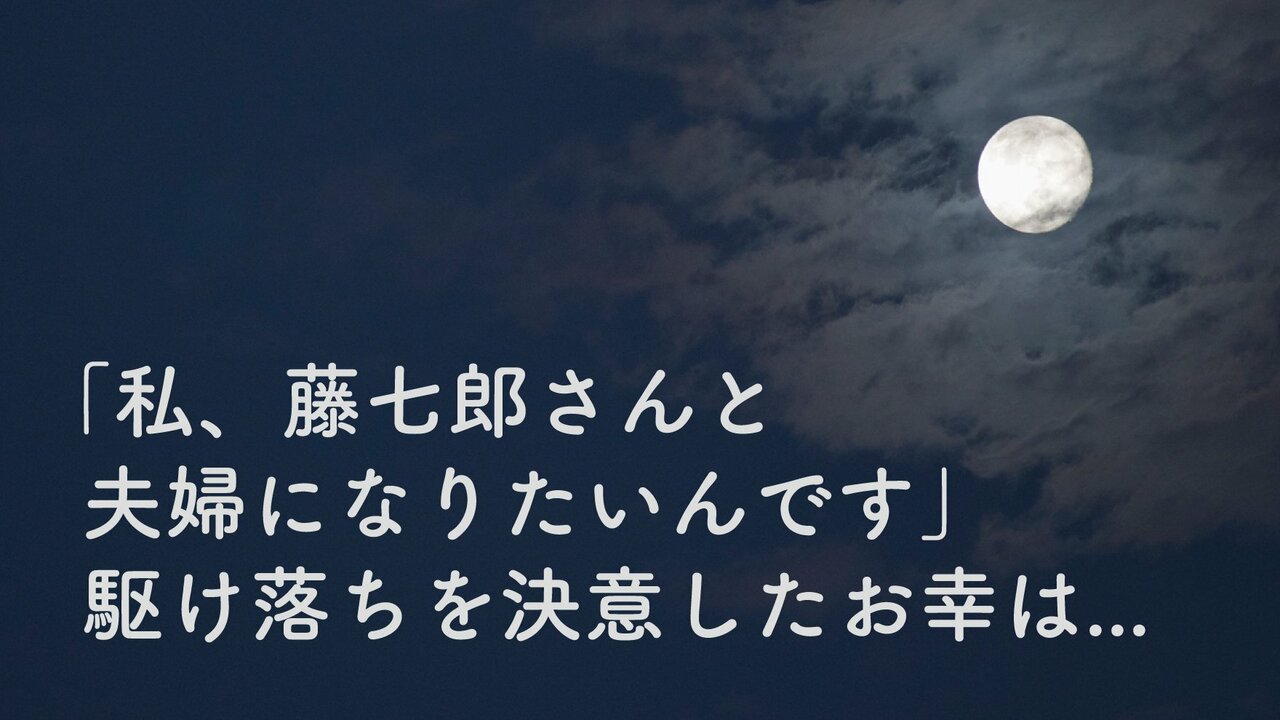来客
「おじいさま、おばあさま」
「なんだい、お幸」
「……縁談のことなんですが」
藤七郎が藤吉ではないかと疑いを持つようになってから数日経ったある日のこと。
お幸は二人に話があると言って三人で話す場を設けた。
内容は縁談のこと。
もしや、と与七とお吉は目を見合わせた。
「縁談がどうしたんだい」
あくまでも落ち着き、素知らぬふりをしてお幸へと問い掛ける。
お幸は目を伏せたまま、話し出した。
「――私、藤七郎さんと夫婦になりたいんです」
「……」
「……お幸」
内容は悪い予感があたったものだった。
与七は目を閉じ、考え込む素振りを見せつつも内心穏やかではなかった。
お幸は顔を上げるとその様子を見つめ、口を開いた。
「認めてくれませんか? 私と藤七郎さんのことを」
「……。お幸、よく聞きなさい」
「……おじいさま」
「藤七郎はだめだ。出自のよくわからん男をこの由緒ある近江屋の跡取りとして認めるわけにはいかない」
「そんな……」
「お幸、……わかっておくれ」
「……おばあさま」
目に涙をたくさん溜めたお幸を見て、与七もお吉も心が痛んだ。
二人ともお幸に告げたことが本心だったからだ。
藤七郎はよく働いてくれるし、下男たちからの評判も良い。客からも愛想がよくて丁寧だと人気がある。下働きの藤七郎を指名する常連客もいるくらいだ。
もし、藤吉でなければ喜んで跡取りに迎えただろう。
その心配が拭えないままでは、二人の仲を許可するわけにはいかなかった。
大きな目に涙を溜め、ぽろぽろとこぼしながら二人の顔を交互に見つめたお幸は、そのまま何も言わずに部屋を出て行ってしまった。その後すぐに自室へとこもったらしく、その日は一歩も出てこなかった。