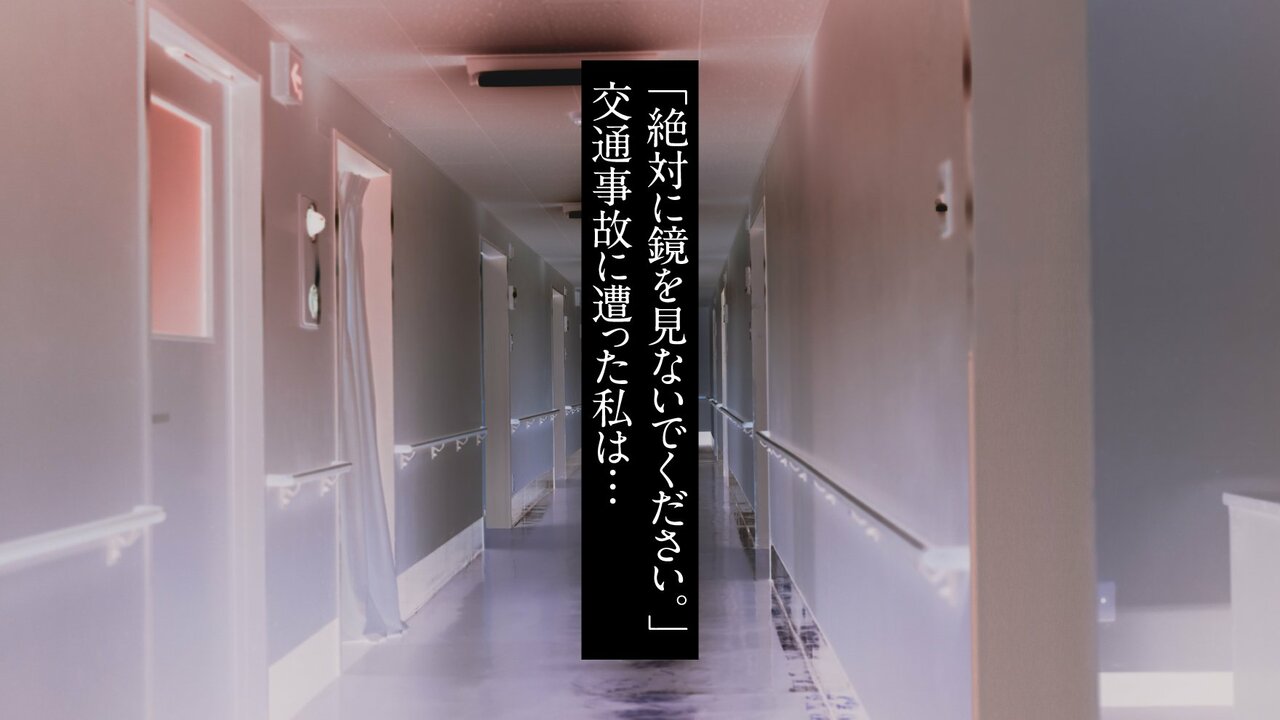【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
音楽が終わったら
私は弟を置き去りにして、家を出た。
住む場所もなく、仕事も金も無かったが、怖いものも無かった。高校は卒業するという約束だった。だが、実家を出る以上自分の稼ぎで生活をするのは当然のことのように思っていたので、働く必要があった。しかしそう簡単に仕事もアパートも見つかるはずはない。
最初は友達の家をほっつき回り、二十四時間営業のファミレスへ行き、銭湯へ行き、夜中にこっそり実家のマンションに忍び込み親の財布から金を盗んだりしていた。殆ど学校へは行かなかった。好きだった倫理の授業にしか顔を出さず、行事は一切参加しなかった。
学校へ行っても図書室に籠ってばかりだった。
私には友達があまりいなかった。
それは中学生の頃からだ。転校生だったということもあって、札幌には馴染めなかったのだ。ましてや、私は笑うことを知らない暗い女の子だった。放課後は本を持って喫茶店へ行き、CD屋へ行き、本屋で立ち読みをし、終電まで街をぶらついた。
街では不良グループがたむろしていたが、私はそういったグループに入ることすらできなかった。聞こえはいいが、一匹狼だった。学校にも馴染めず、住む場所もなく、帰る場所もない。私の居場所はどこにもなかった。
そんな中、街でスカウトされた人に働く場所を紹介され、経営者に事情を説明して寮に入れてもらった。そこからが、私の一人暮らしの始まりだ。
ススキノの外れにある小さな部屋。その部屋は四階にあり、目の前にはセブンイレブンがあり、一〇メートルも行けば三十六号線だった。あんなに憎かった家を出て来たにもかかわらず、初めての一人暮らしというものの寂しさは想像以上に苛酷だった。呼べばすぐに来てくれる友達などいなかった私は、アパートに一人でいるのが寂しすぎて、昼も夜もその経営者の元で働いた。お陰で経済的に困ることはなかった。
アパートが見つかってから、高校を卒業することと、ピアノを続けることと、今後一切親を頼らないということを条件に、ピアノを搬送してもらった。
「音楽大学へは行けないが、ピアノで生活できるように頑張る」と、私は嘘でもそう言った。
その時母親からもらった手紙にはこう書いてあった。
「ピアノを送ります。今後一切、私達の邪魔をしないでください」
家を出たにもかかわらずピアノを続けようと思っていたのは、どこかで母親を信じていたからだろう。いつか私を受け入れてくれるのではないかということを。自分の中のけじめとして、ピアノはライセンスの資格だけを取得して辞めた。自由を手に入れた私は、自力で生きて行くことに必死だった。ピアノなんて、もうどうでも良くなってしまっていた。
弟はプロのサッカー選手にはなれなかったが、一流の私立大学に合格した。