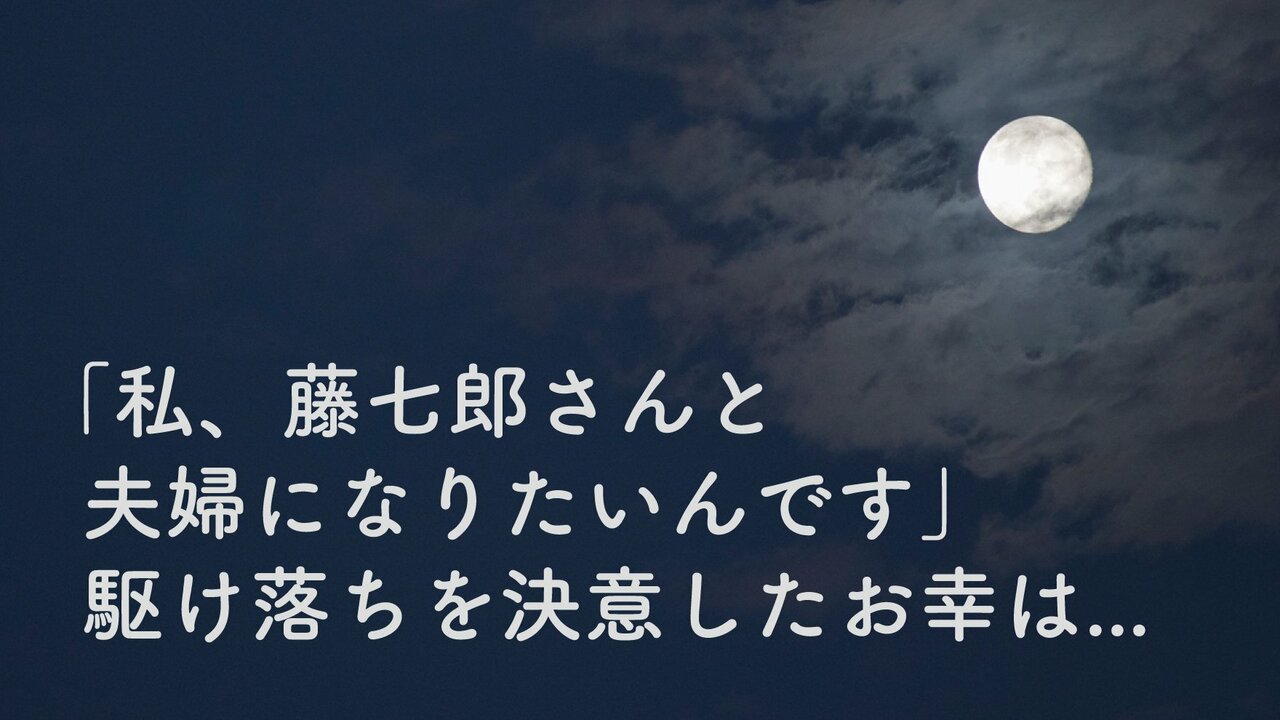「締め切りには間に合いそうか?」
「私が働いているところはね、締め切りはあってないようなものだ。気長に待ってくれと、まなみくんには頼んでいるんだ」
「暢気なものだな」
「廃れた作家の扱いなんてこんなものだよ」
「ふうん」
私が自嘲気味に溢した言葉に御巫は適当な相槌を打つと、「僕は君の話は嫌いじゃあないがね、読み辛いが」と世辞なのか何なのか分からないフォローをしてくれた。
「褒めるならもっと心を込めてくれよ」なんて態とらしく皮肉めいて言ってみれば、「ふん」と紫煙を吐き出しながらそっぽを向く。――しかし私が此処に来てから三十分程経つが、ゆうに五本は吸っているが大丈夫だろうか。
「そんなことより君。大体の構想は練れた、と先程言っていたが、どんな風に書く予定なんだい?」
くすくすと笑う私が面白くなかったのだろう、御巫はそれから逃れるかのように話題転換をしてきた。
「ああ。君に借りた本をオマージュ作品にしようかと思ってね。タイトルはそのまま引用させてもらうことになったよ」
「それは編集部の意向か?」
「勿論」
先日、御巫宅で水蜜桃を頂戴してから、これは是非使いたいと考えていた。これを書いた作者は不明な様だし、マイナーな部類に入る物らしい。この作品を世間に広めるにはいい機会だと私は思った。
「ちょうど今年で私もデビューしてから二十年が経つからね。この本の売れ行きが良ければドラマ化を考えていると言われたんだ」
「中々大がかりじゃないか」
「まあな」
編集長の森(もり)さんは私のやる気を引き出すために言ったのかもしれない。だが出版社を贔屓にしてくれているテレビ局のディレクターがその時同席していてこの話に乗ったのだ。
出来上がった小説を読んで、気に入ったら脚本を書く気でいると聞いた。
これはもう気合が入らないわけがない。
学生時代からの友人で今も交流が続いている友人に俳優業を営む者がいる。そいつに話をしたら絶対演じたいと言ってくれた。
どうなるかは分からないが、私も是非彼に演じて欲しい登場人物がいたから、彼のディレクターが気に入るような作品を書き上げねばならない使命感もあった。