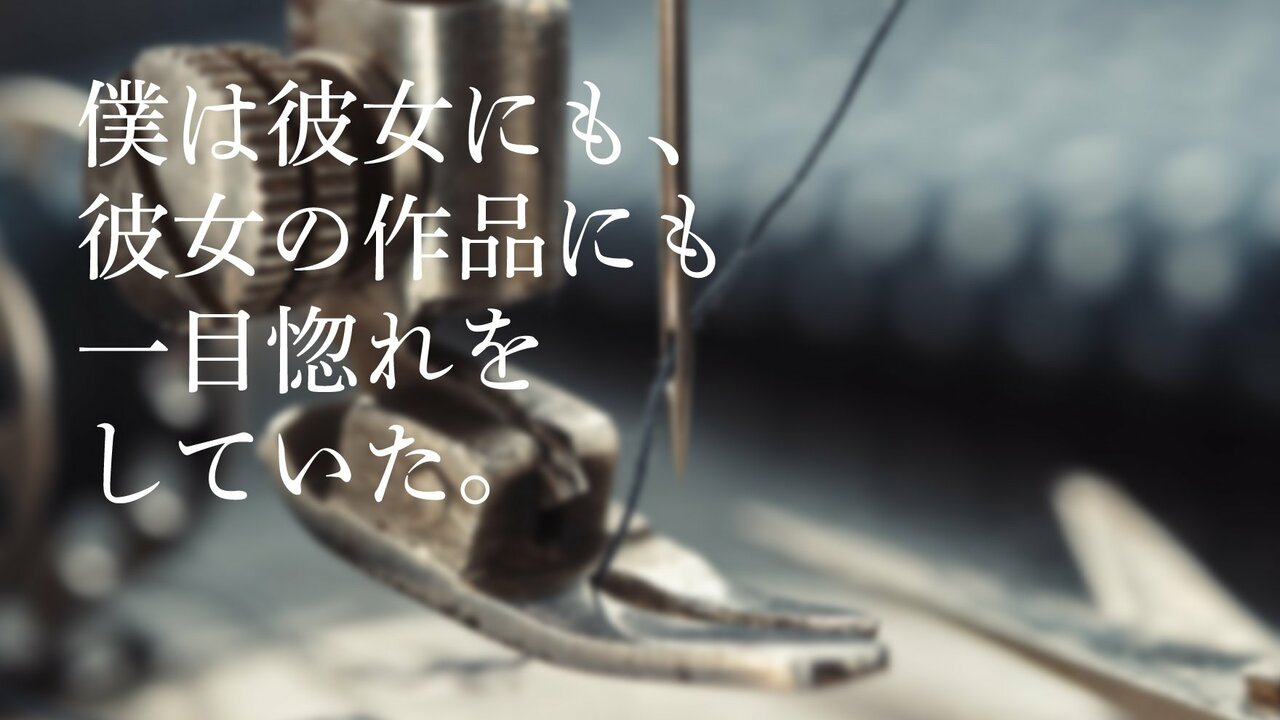ずっと聞きたかった声が後ろからして、ドキドキしながらゆっくり振り返ると、肩にフリルの付いた水色のひざ丈ワンピースに、白いヒールを履いた女性が立っていた。久々過ぎて顔を見るのが恥ずかしくて目をそらしてしまった。
頼まれていたブローチの進捗を訊かれて、まだデザイン画しか描けてないことを言ったら彼女は怒るだろうか。今度は別のドキドキが体中に脈打つ。
「こんにちは」
僕は丁寧にお辞儀をした。
彼女はフフっと品よく笑い声をたて、自分の作品を手に取り僕に差し出してきた。
「触ってみて」
「あ、いや、でも、触っちゃいけないって書いてあったし……」
「でも触ってほしいの」
彼女の作品に自然と手を伸ばしていた。落とさないように両手で包み込むように受け取り、生まれたての小鳥でも温めるように優しく包み込んだ。
冷たくて気持ちいい。海そのものだと思った。
「綺麗だね。作るの大変だったでしょ?」
恥ずかしくて顔が見られない。
「もちろん簡単じゃないけど、作っていてとても楽しかったから私は満足してるんだ」
「ごめんね。あの、えっと、まだブローチ完成してないんだ。色々迷っちゃって」
「迷う?」
「うん。デザイン画は描き終わっているんだけど、どのくらいの深さや薄さで、君のために、どんな表現が出来るか、一度悩みだしたら手が動かなくて」
彼女はまた少し笑い、僕の手の下に両手を添えた。僕は自然と両手を開き隙間から彼女の手へとガラスの海を落とした。
「私のために上村君の感性を抑え込む必要なんてないよ。私もこの展示会が終わったらこの作品をハンドメイドサイトで売るつもりなの。初めて値段をつけることを意識して作った作品だから、自分の思うままに作った作品をそのまま気に入ってくれる人がいたらラッキーくらいに思ってるの。だから上村君もそんなに気負わずに作ってみて」
「い、いくらで売るの!」
僕らしくない取り乱し方だった。それに質問も不躾すぎる。でも、自分の心の奥には嫉妬心に似た執着心みたいなものが渦巻いていた。彼女の初めて値段のつく作品だと思ったらなんだか焦ってしまった。心が急いでいる。
「えっと、一万円ぐらい?」
「僕が買うよ!」
「え?」
彼女の声には僕の焦りが伝わり切ってなかったようで、不思議な間があった。
「城間さんが楽しく作っていた時間を買いたい」
「そんな、え、本気? 私がブローチにお金を出したからって気を使ってるの?」
「そういうのじゃないよ。でも、初めて売れたものって君のクリエイターとしての第一歩で、これから作る作品の基盤になっていくでしょ? 僕もそうなんだ。お金に換える作品、城間さんから頼まれたブローチが初めてなんだ。だから、自分でも納得のいく作品にしたくて、その……待たせちゃって悪いけど、僕もこの展示会が終わるの待つから、この作品は売却済みってことにしてくれないかな?」
どうか、受け入れてもらえないだろうか。体をヒリヒリさせながら緊張していた。だって、僕の記憶は消えることがない。大抵の嫌な記憶なら乗り越えてこられたけれど、ここで断られたら、絶望する。永遠に記憶に残って、どうでもいい時に勝手に蘇って、何度も悲しみと戦うことになって、精神が削り取られる。またストレスで眠れなくなる。