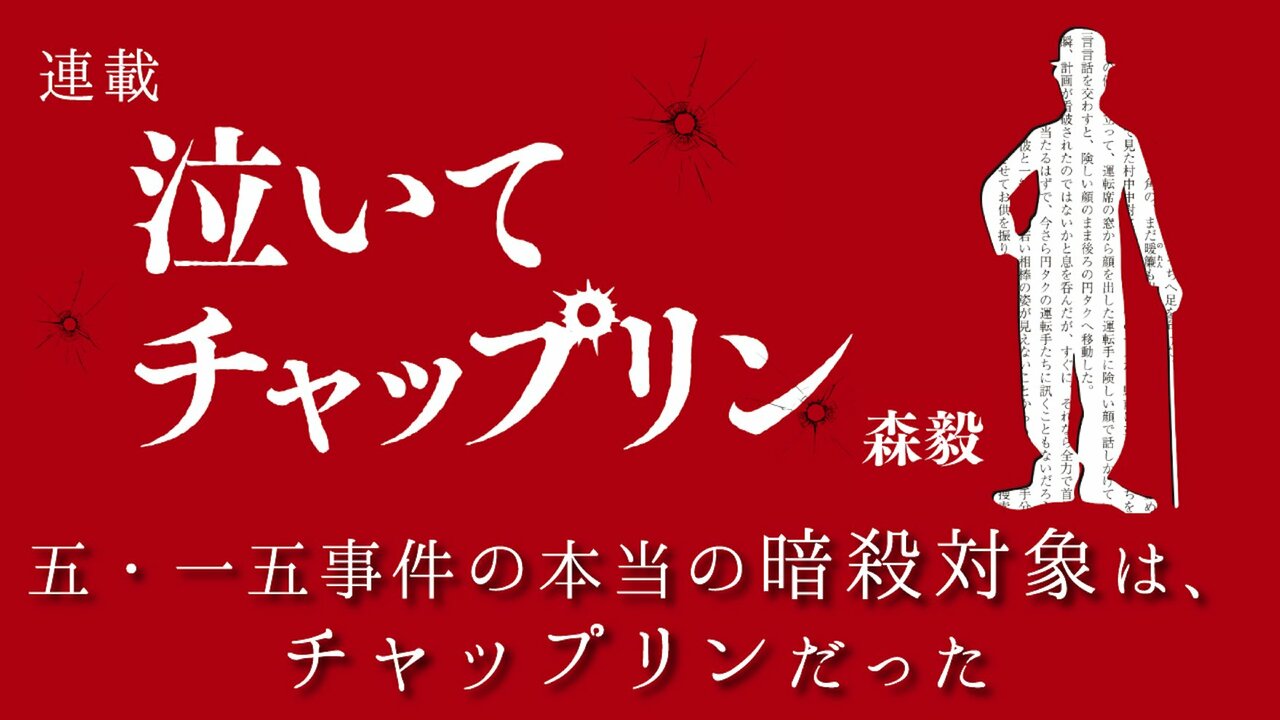「いや……『窮猿(きゅうえん)林に奔(はし)る、豈(あに)、木を択(えら)ぶに暇(いとま)あらんや』といったところだが、たしかに、これから計画を練り直しているヒマはないし、そういうことであれば、当初のきみらの計画通り、やはり十五日に決行することも已むをえないだろうな」
「むん。『二兎追う者は』というからな……きみらもそれでいいかな?」
と、三上は左右の二人を見比べた。が、田島はその言葉じりに被せるようにつづけた。
「いや、関東軍の石原参謀も、『対支外交即ち対米外交なり』といっているように、日米外交と満州の経営、それと国家改造は、いわば三位一体で、その一つが欠けても、かの新渡戸稲造博士も警鐘をならしている、『日本の空を覆っている不吉な予兆』が晴れるとはいえないからな。
チャップリンの件は、私がいいだしたことでもあるし、それは私に任せてくれないか。たしかに古賀くんのいう通り、まだ日本に来ていない彼の日程を探りだすのは至難のことだろう。しかし、それはコソコソ探りだそうと思うからであって、それならそれで、いっそこちらから神戸港までお出迎えにあがって、陰ながらピッタリお供させてもらうというのはどうかな。
それなら、仮にも相手は日本政府の公式招待客だ。いうなれば、お祭りの山車(だし)に従(つ)いてゆくようなものだと思うが……それで、決行のその日、その時刻には、こちらは何処でどうしているかは分からないが、きみらが立てた以前の計画通り、一七三〇時に決行するというのであれば、私もその時刻に合わせて決行するということでどうだろう?
あるいは、こちらの情況によっては時刻が多少前後するかもしれないが、それはさしたる問題ではないだろう。何か問題が生じた場合に備えて、当日に私の方からかならず電話するということでどうかな?もちろん、誰に、何時、何所へ電話をすればいいのかは、その前に、きみらの誰かに電話して確認するが」
と、田島は三人を均等に見比べた。すかさず、三上がピシャリと膝を叩いていった。
「むん! いわれてみればなんでもないが、そいつは妙案だ。窮猿林に奔るといいながら、ちゃんと木を択(えら)んでるじゃないか。まさに窮(きゅう)すれば通ずだな」
「ということは、チャップリンは田島さん一人でやるということですか?」
と中村は、さらに身をのりだした。
「ああ、そういうことであれば、むしろ一人のほうが目立たないし、私に張り付いているお供も、煙(けむ)に撒かなければならないからな。そのためにも、やはり、一人で身軽に動けたほうが何かと都合がいいからね」と、田島は自分自身にも言い聞かせているようにいった。
「その案には私も賛成です。しかし 三上さんがいわれたように、海には時化ということもありますし、もしチャップリンの到着が日延べになった場合はどうしますか?
その時は、私たちだけで先行しても構いませんか……直前になって中止して、また変更というのでは、私等将校はいいとしても、自由に外出できない士候等のことも考えてやらなければなりませんし、そこに齟齬(そご)が生じ足並みが乱れると、それが《桜会》の失敗の原因の一つであったように、その二の舞にならないともかぎりませんので」
と、古賀はあくまで冷静だった。同じように、田島も穏やかに答えた。
「きみのいうことも尤もだが、それでは、政府の公式招待客であるチャップリンも早々に帰国してしまうかもしれないし、その時は、それもまた天の配剤と考え、延期も已むをえないのではないかな。
政治家や財閥は何時でもやれるが、チャップリンが来日するなどということは、何度もいうように、文字通り千載一遇の天与のチャンスだからね。同時に決行することで、起爆剤としての威力も倍増することは間違いないし、『天与取らざれば反りてその咎を受く』ともいうからね」
「たしかに、アメリカは黙ってないでしょうからね」
と、横から中村が相槌を打った。
「それに、政党政治の打倒が焦眉の急であることはいうまでもないが、浜口首相や井上蔵相、それに三井の団琢磨(だんたくま)の狙撃事件でも分かるように、そんな『血盟団』の二番煎じのようなことをやっただけでは、何の効果もないことはすでに証明されていると思うが、いや、徒(いたずら)に新聞紙上を賑わせ、『国家改造』イコール、ロシアの『共産革命』というような印象を国民に与えたという点では、彼等の壮挙(そうきょ)も的外れだったというか、残念ながら、むしろ逆効果だったといってもいいのではないかな。ちょっと辛辣ないい方をすれば、彼等は自分で自分の首を絞めたようなものだと思うが、違うかな?」
と田島は、また三人に、順次目をやった。
それら一連の狙撃事件は、『一人一殺』を標榜している民間の秘密結社、いわゆる『血盟団』のメンバーによるもので、実行犯もすでに警察に検挙されていたが、その血盟団と、古賀中尉ら海軍の青年将校が大川周明の主催する「行地社(こうちしゃ)」を通じて接触していることは、田島もある程度は知っていた。
また、その血盟団の盟主の井上日召(にっしょう)こと井上昭(あきら)は、四十代半ばまで仏門に身をおいていたといわれ、それなりの教養も備えた人物で、「善を為すも名に近づく勿れ」という荘子の訓えに則り、「目的を達成するためには必ずしも目標人物を殺さなくてもよく、目的を達すると達しないとにかかわらず潔く腹を切ろうなどと、外見を飾るような真似はするな」と、若いメンバーらを厳しく戒めていたということも仄聞(そくぶん)していた。
古賀は、それを認めるように小さく頷いた。
「むん! それで結論はでたようだな。いやいや、古賀くんからの一報で、吾輩もびっくりして飛んできたんだが、『案ずるより産むが易し』とはこのことだな。
しかし、今朝神戸から帰ったばかりのきみが、すぐにまた神戸にとんぼ返りすると知ったら、憲兵さんも、まるっきりチャップリンを知らないわけじゃないからな。
いくらお祭りの山車に従いていくようなものだとはいっても、その山車が、いきなり、『トロイの木馬』に早変わりしないともかぎらないからな。まずは、その連中の目を欺く策を考えないとな……何か妙案はあるかな?」
と三上は、また少々はしゃいでいるような、愉しげな声で訊いた。
「べつに妙案というほどではないが、山登りにでも行ってみようかと思う……これもいま思いついたことだが、北アルプスへでもね」
「北アルプス?」
と三上は、はじめて耳にする海外の国名を聞いたような顔をした。田島は笑顔で頷いた。
「ああ、上高地から穂高、槍ヶ岳と縦走して中房温泉に下って、その足で神戸に向かうことにしようかと思う。いや、それで万事解決というわけにはいかないだろうが、北アルプスは、まだこの時期、猛吹雪に見舞われることもめずらしくないから、いかに闘志溢るる憲兵さんといえども、普段着で登れるような山ではないからね……一人で最後の山を存分に楽しんでくるよ」
「なるほど。そいつはさしずめ『山越えの計』とでもいうべき妙案だな。しかし、吾輩は山にはまったくの素人だが、この大事を前に危険なことはないのか?さっきもいったように、海では時化で漁船が転覆したとか、海水浴で子供が溺れたという話はめずらしくないが、最近は、山の遭難というのも時々新聞で目にするからなあ」
と、三上は真顔に返って訊いた。
「ええ。たしかにそうですね。今年の正月早々にも関西の有名な登山家が、その北アルプスで遭難して、雪山を幾日も彷徨(さまよ)っていたと新聞でも報じられていましたが、いかに憲兵を欺くためとはいえ、日本の将来を左右するこの大事を前にあえて危険を冒さなくとも、何かほかにも方法があるかと思いますが?」
と、中村も口を挟んだ。