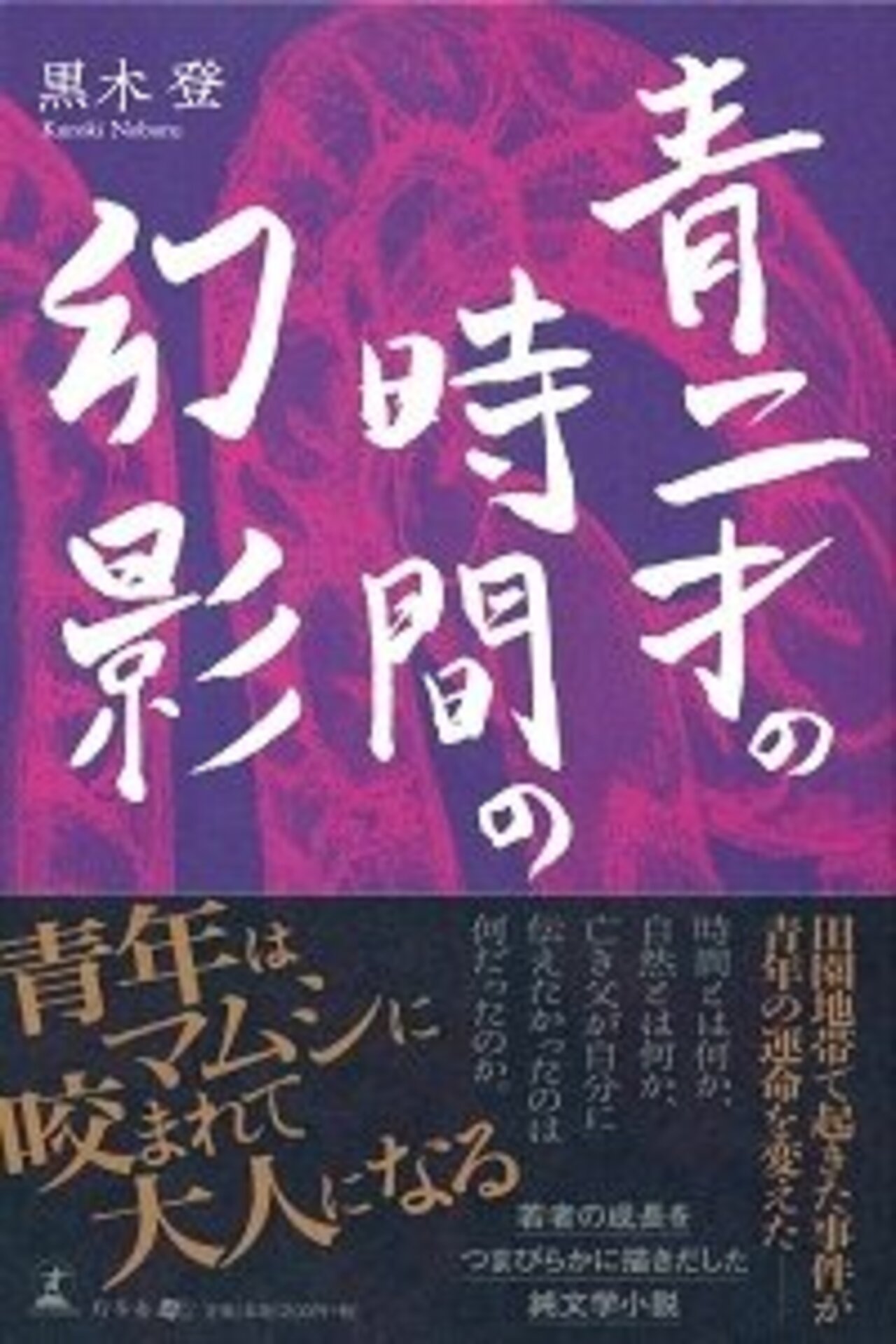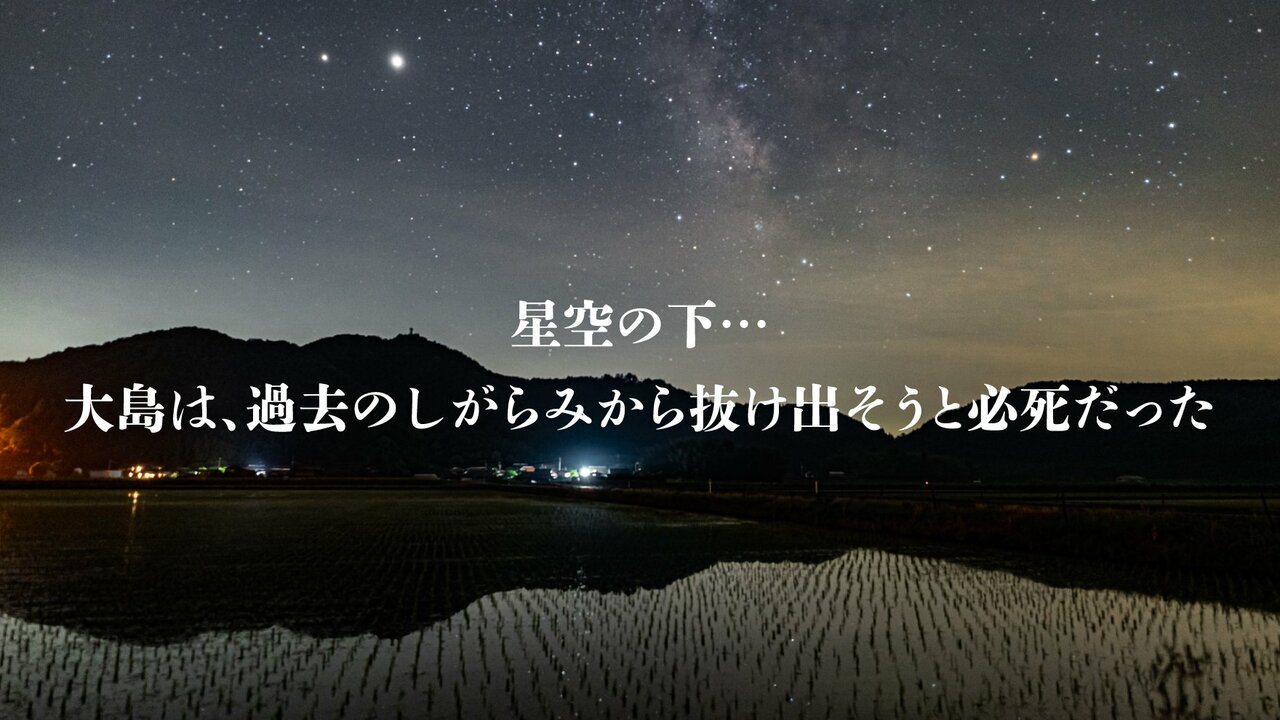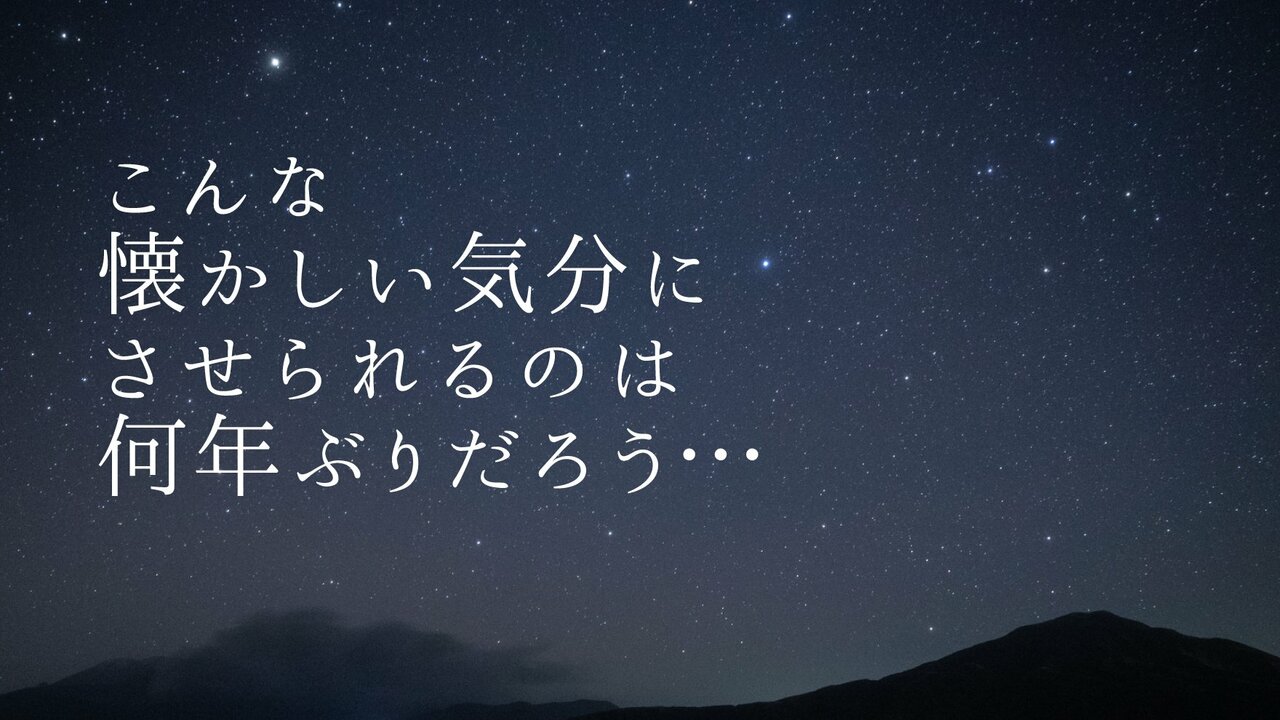それから一年も経たないうちに父は癌で亡くなったが、大島が生あるものの儚さみたいなものを感じ取ったのは、ずっと後になってからである。星空を見上げていると、子供の頃の懐かしい思い出がつい最近のように思い出されてきて、目頭が熱くなった。大島は、少し感傷的な気分になりかけていた。
父さん……。
心の中で、そっと呟いた。幸せとは何だろう?まんざら見込みがないようでもなく、星の一つがキラッと輝いたようにも見えた。
その頃の大島は、印刷会社に勤め、何不自由もない生活を送っていたが、ただ精神的に満たされない日々が続いていたのは、性格的なものが色濃く滲み出ていたからだろうか。
例えば、一つのことに夢中になってしまうと、その殻からなかなか抜け出せない性分は何も大島に限ったことではなかったが、神経質で優柔不断、しかも不器用ともなれば少々趣が異なってきたのである。
その夜、アパートを飛び出したのも、日常的な他愛もない出来事によるものだったが、大島にとってはどれも看過できない切実な問題を孕んでいたのだった。仕事のこと、社会のこと、人生のこと……。
時間という突拍子もない魔物に翻弄されていたことも、大島を混乱させた大きな理由と言えば、そう言えただろうか。この時間というのは、今は亡き父によって触発されたものだった。
父は癌を患っていたが、亡くなる直前まで時間とは無縁の、死を恐れぬ、まるで仏のような慈愛に満ちた表情さえ漂わせていたのだった。むろん、それは多情多感な子供心に映った突拍子もない感覚だったとはいえ、大島が父の人間としての側面に妙な感情を抱いたのは、そのときが初めてだった。
以来、大島はこの時間という謎めいた問題に悩まされることになる。
もっとも、その時間という問題は、子供の能力では解明できるような問題でもなかったので、長い間、心の中で燻ぶり続けたあと、満を持して浮上してきたのである。