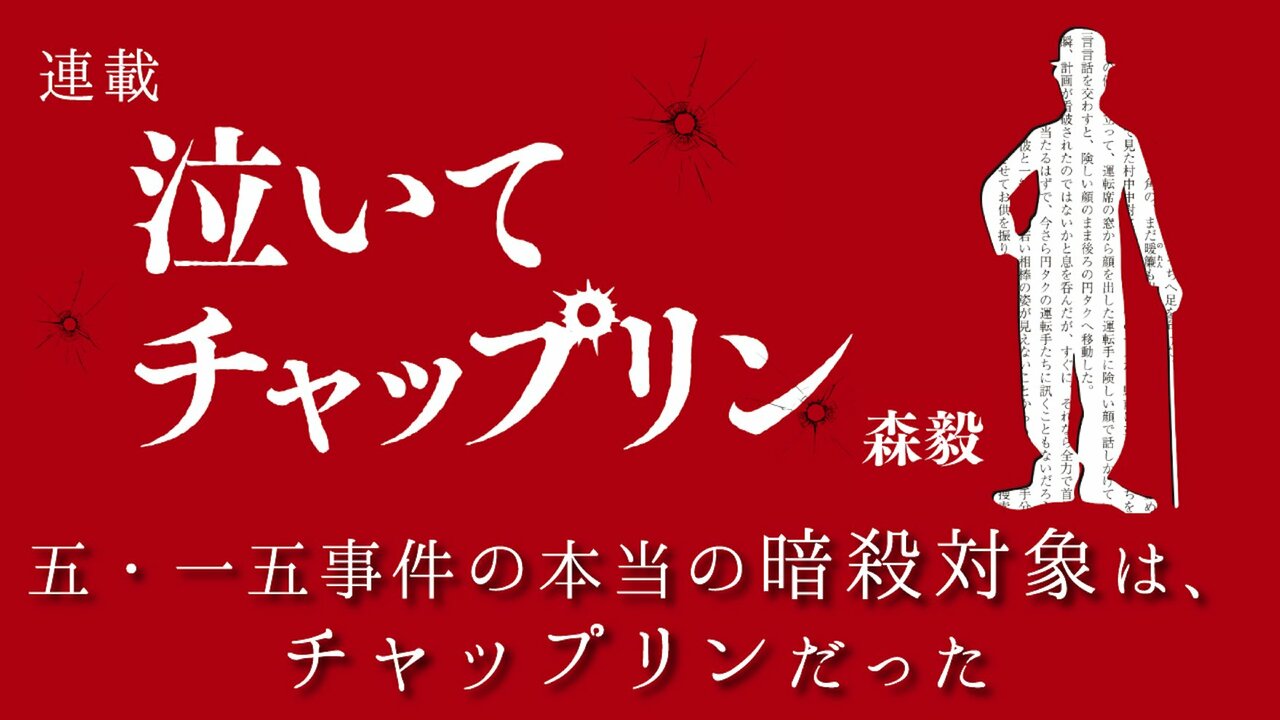田島も、コーヒーカップを机にもどして顔を上げた。
「はあ……それは、つまり、いえ、いま申しましたように、大尉殿にお目にかかるのも今宵が最後かと思いますので、非礼を顧みず申しますが、突然、今お話ししたような次第になってしまい、良子(よしこ)さんにも、ご挨拶もせずにお暇(いとま)しなければならなくなってしまいましたので、大尉殿から宜しくお伝えいただければと……。
それと、これは、以前ご一緒にテニスをしたときに、良子さんに拝借したハンカチですが、大尉殿からお返ししていただければと思いまして……」
田島は上衣の胸のボタンをはずし、襦袢(じゅばん)の胸ポケットから取り出した淡い水色のハンカチを大尉の前に、そっと滑らすように差し出した。
それは一年ほど前、山内大尉に、「大正ロマン」とともに花開いたといってもいいテニスに誘われ、生まれて初めて興じて大汗をかいたとき、大笑いしながら相手をしてくれた良子が貸してくれたものだったが、そのとき交わした眼差しによって、一瞬にして何かが弾け、互いの魂が一つに溶け合い、身も心も宇宙の彼方に拡散してゆくような陶酔感に打たれ、以来、それを返す機会のないまま、何時も肌身につけていたものだった。
山内大尉は、一瞬張り詰めた気持ちが、一気に緩んだように相好をくずした。
「そうか、それでさっきは、赤の他人と思って容赦してくれなどと、妙な言い方をしたんだな。
しかし早いもので、私も世帯をもって実家を出てから、もう二年になるが、妹の顔を見たのは去年の夏に、これも三人で、《穂高(ほたか)》へ行ったときを除けば盆と正月ぐらいのものでね……そういえば、そのとき《奥穂(おくほ)》だったか、《北穂(きたほ)》だったかの山頂で、来年は《槍(やり)》から、いま評判の《喜作(きさく)新道》を経て、《中房(なかぶさ)温泉》に下って、のんびりと温泉につかっていこうと約束したことを憶えているかな?」
「ええ、もちろん憶えております」
「だったら、その約束が果たせなくなったことぐらいは、きみの口から、それに、このハンカチも、きみが直接返したほうがいいのじゃないかな……まあ、この際だから、私も、回りくどい気遣いや、他人行儀は抜きにしてはっきりいうが、良子は、きみと一緒になれることを露ほども疑っていないようだし、きみも、そのつもりじゃなかったのかな?」
と、大尉は笑い、からかうような調子でいった。
「は、そのつもりでおりました……四十四期生が無事卒業したら、連隊長殿にお願いして、すぐにでも話をすすめたいと考えておりました」
「そうか、それできみは女々しいとか未熟な俗物などと思っていたというわけかな? だがきみは、その思いにけじめをつけぬまま決行するつもりかな? それでは、いま話した項羽も、『騅逝かざれば如何んすべき、虞(ぐ)や虞や汝を如何せんと』と、虞美人草の花の名にもなった寵愛(ちょうあい)する虞美人との別れを悲歌慷(ひかこうがい)慨しているように、きみもきっと後悔すると思うがな。
大義に殉ずる青年将校としては、為すべきことを為して思い残すことはないかもしれないが、田島邦明という一人の生身(なまみ)の人間としては、死んでも死にきれないのじゃないかと思うのだが……また良子にしても、やはり同じ思いを抱いてその後の人生を送らなければならないだろう。いやその前に、ひょっとすると世を儚(はかな)んで、語るも涙ということになるやもしれないぞ。
近頃は、若い男女の心中や自殺が、『近松』の心中物の近代版であるかのように持て囃(はや)されて、新聞でも美談のように書き立てているご時世だからね……とまあ、それは冗談だが、顔も見せずに、風のように去っていってしまうというのはどうかな?」
と、山内大尉は目で笑った。
「はあ、ですがお会いすれば、後日、やはり良子さんにもご迷惑が及ぶかもしれませんし。それに良子さんは、子供の頃から津田梅子(つだうめこ)女史に師事され、後(のち)にアメリカにも留学された方ですし。また、『親は刃をにぎらせて人を殺せと教えしや』と詠んだ、与謝野晶子(よさのあきこ)を愛読されている進歩的な方ですから、お会いしても、いったい何をどう話せば……」
「なあに、晶子女史がそうした進歩的な詩歌を詠んだり、津田梅子女史が男勝りの活躍ができる世になったのは、福沢諭吉や大隈重信侯のお陰ばかりではなく、名もない大勢の若者が近代化のため、吾身を顧みず戦場に赴き、散っていったお陰であることも忘れてはならないし、それに私たちも、人を殺したくて軍人になったわけじゃないといいたいところだ。
だがまあ、戦地へいったことのない者には、言葉を尽くせば尽くすほど、言い逃れの弁解としか聞こえないだろうから、それは言わぬが花、『秘すれば花』で 何もバカ正直に話すことはないのだし、嘘も方便という、それもまた仏の道、すなわち人の道ではないのかな。
それに、『梓弓(あずさゆみ)引きて許さずあらませば かかる恋には逢わざらましを』という万葉の昔から、進歩的な近代婦人の旗頭といってもいい晶子女史も、『柔肌の熱き血潮に触れも見で さびしからずや道を説くきみ』と詠んでいるように、男女の仲は、近松の心中物ではないが、理性や道理では如何ともし難い宿命的なもので、そこに古典的も進歩的も、またロマン主義もないと思うが、まあ、それはさておき、一度会って話をすれば、また別の道が開けることも無きにしも非ずだと思うがね」
「は、それは、私の決意が変わるかもしれないということでしょうか?」
と、田島の表情は、一瞬、真剣みを帯びた。
「いや。でも、もしそれできみの決意が変わるのであれば、それもまた一つの天命といえるが、今もいったように他人行儀は抜きで、ちょっとぶっちゃけた話をするが、笑い話だと思って聞いてくれ。私の親父が、乃木将軍麾下(きか)の第三軍の増援部隊の中隊長として、《二〇三高地》の最後の総攻撃に加わり、脇腹に敵の機関銃の弾丸(タマ)を喰らったことが自慢のタネで、その古傷にものをいわせて、その時は陸士を出たばかりの新任少尉で、後備旅団の旅団長の副官として出征した荒木閣下を、後方でウロチョロしていたやつに何が分かるかなどと、閣下が陸相になった今でも、事あるごとに批判していることはきみも知ってるね。
帝国陸軍も、今はそんなタマの下を潜ったこともないような連中ばかりになってしまったから、満州事変などという向こう見ずな戦をはじめるし 怪しげな口実で独断専行をした関東軍や、戦(イクサ)のイの字も知らない若い連中のご機嫌取りをしているような荒木が、あろうことか、陸相になってふんぞり返っているようじゃ、この先またどんなバカなことをしでかすか分かったもんじゃないともね。
まあ半分は、今や飛ぶ鳥落とす勢いの、荒木閣下に対するやっかみかもしれないが、実のところは、その古傷はほんのかすり傷程度のもので、親父が負った本当の傷は、その日たった一日の戦闘で、部下の三分の一の兵を戦死させてしまったという心の傷なんだ。
むかし、私が十二、三の頃だったが、親父が、大きな声ではいえないが、乃木将軍は、明治大帝に殉じて軍神に祀り上げられたけど、本当は《二〇三高地》で戦死した将兵に殉じたのだといってたよ。
その胸の内は、《二〇三高地》を『爾霊山』と命名されて詠まれた漢詩に見る通りだが、なかには、無謀な総攻撃を繰り返して、幾千万の将兵を戦死させた無能な将軍とか、また、『一将功成りて万骨枯る』などと、一面識どころか、後ろ姿も拝んだことがない物書きが、いっぱしの軍事評論家か、司馬遷(しばせん)気取りの大歴史家にでもなったつもりで知ったふうな小賢しい批判をしたり、日和見主義の政治家や学者の浅はかな批判を、今では考えられないことだが、新聞も堂々と掲載している有様だったといって憤慨してたな。
だが、当時はイギリスやアメリカでさえ、『白熊』と恐れていた世界一の陸軍の大帝国ロシアと戦争すること自体、無謀は百も承知の戦で、若い頃から将軍と面識のあった森鷗外(もりおうがい)も、『長身巨頭沈黙厳格の人なり』と評しているように、それは己(おのれ)にも厳格な乃木将軍だからこそ為しえたことであり、日本が今日あるのは、東郷元帥の日本海海戦の功績もさることながら、その歴史的な大勝利も、ロシア艦隊の拠点の、旅順港を見下ろす鉄壁の要塞、《二〇三高地》を陥お落とすことができたからであって、乃木将軍が、今なお、小さな子供たちにも慕われ敬われているのは、みんなそのことを知っているからだとね。
また、その森鷗外の、乃木将軍の殉死を悼んで書かれた『興津彌五右衛門の遺書』は、『某(それがし)年来桑門(そうもん)同様の渡世致居候へ共、根性(こんじょう)は元の武士なれば』という、将軍の想いを代弁したと思える殉死をテーマにした史伝小説で、しかもそれを、葬儀のわずか一カ月後に『中央公論』に発表したということが、乃木将軍に対する鷗外の並々ならぬ敬愛の念と、浅はかな批判に対する反駁(はんばく)だったことを如実(にょじつ)に物語っているともね……そのとき親父は、大勢の部下を戦死させた自分自身に言い聞かせていただけかもしれないが。
とまあ、そんなことはさておき、話は飛ぶが、以前に一度、私には腹違いの弟がいることを話したと思うが、憶えているかな?」