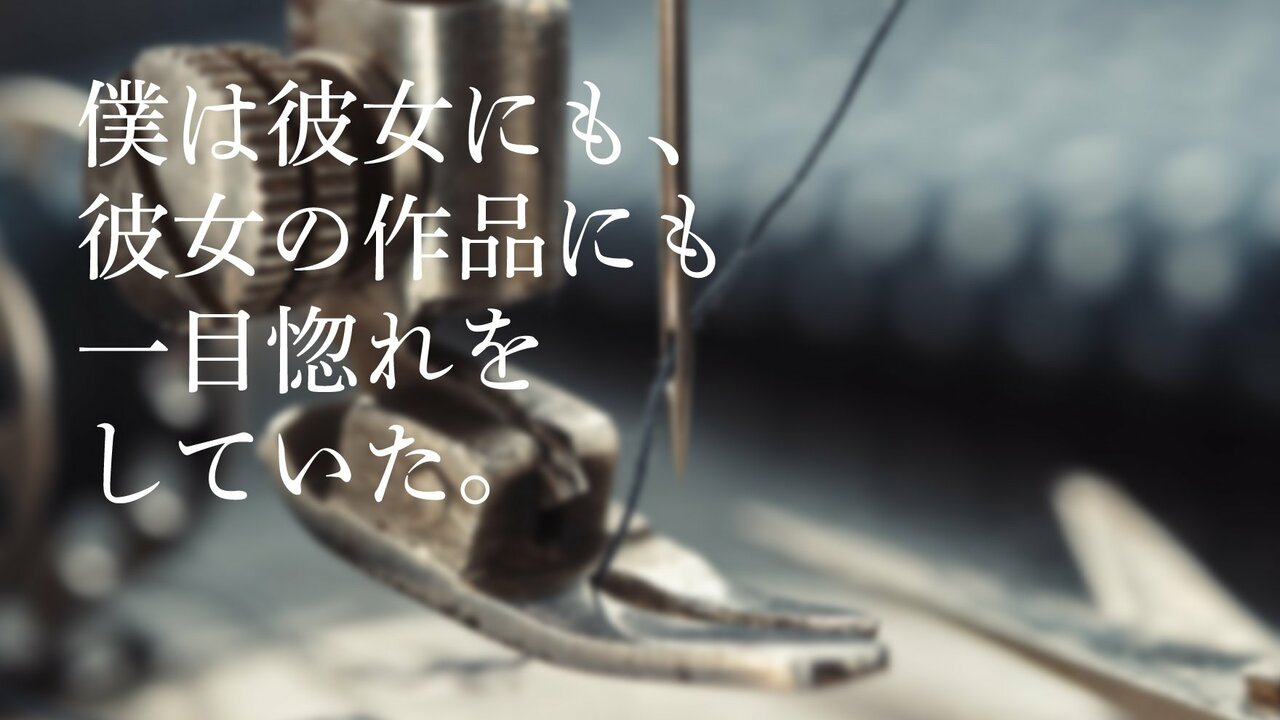バカとハサミは使いよう
「ど、どんなデザインがいいとかある?」
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
声を出すのも必死にならなきゃいけなかった。目の前の彼女を見ていると、苦しいのに目をそらせない。疑った感情は恋だったけど、これが恋だっていうなら冗談じゃない。世界観が変わるどころの騒ぎじゃない。
いつか恋をしても気が付かないかもしれないと思っていたけど、気がついても認めたくないなんて、僕は随分強情な奴だったんだと今知った。
「デザインは上村君の考えたものがいいんだけど、ブローチでお願いしても大丈夫ですか? あと、出来たら、本当に出来たらでいいんだけど、二つで一つみたいな感じで作れますか?」
「よくある二つをくっつけると、ハートになるやつみたいなの?」
「うん。そんな感じ。でも、とにかくただこの二つが合わさると更に綺麗だなって思えるようなものが欲しくて。ダメかな?」
今まで思うがまま作ったものを交換してきたけど、これはお金をもらう仕事で、尚且つ、初めてのオーダーメイドだ。上手くいくか自分でも自信がなくなっていた。
「少し時間がかかるかもしれないけどいいかな?」
「うん!」
嬉しそうな彼女の表情に僕は見とれていた。かわいい。
「あの、二つでお値段どれくらいになるかな?」
またモニュモニョと手を絡め合わせ、僕から目をそらし続ける彼女に健ちゃんがサラッと「一万五千円」と言い放った。何もそんなに高値じゃなくてもいいだろうと思った。
僕がそんなに高くなくていいと言う前に、健ちゃんは僕を睨んだ。
「自分の価値を知れ」
「僕が決めることでしょ」
「そうだけど、お前の場合は違う。お前は自分の作品の価値を自分で把握できてなかったから高値で転売なんかされていたんだ。彼女の要望に全力で応える気があるなら自分をもう安売りするな」
気さくで独りぼっちが嫌いな健ちゃんが、僕に突きつけた言葉は、僕にとって衝撃的で攻撃的で、彼女にまで釘を刺しているみたいな物言いだった。
「私、一万五千円払います。今は現金を持ち合わせてないので、明日でも大丈夫ですか?」
僕は何か健ちゃんに言い返すべきだったのかもしれない。城間さんにそんなに貰えないよと言いたかったような気もした。だけど思考は別のところにあった。僕は他人からの評価なんて気にもしたことがなかった。もちろん自分の価値についても。