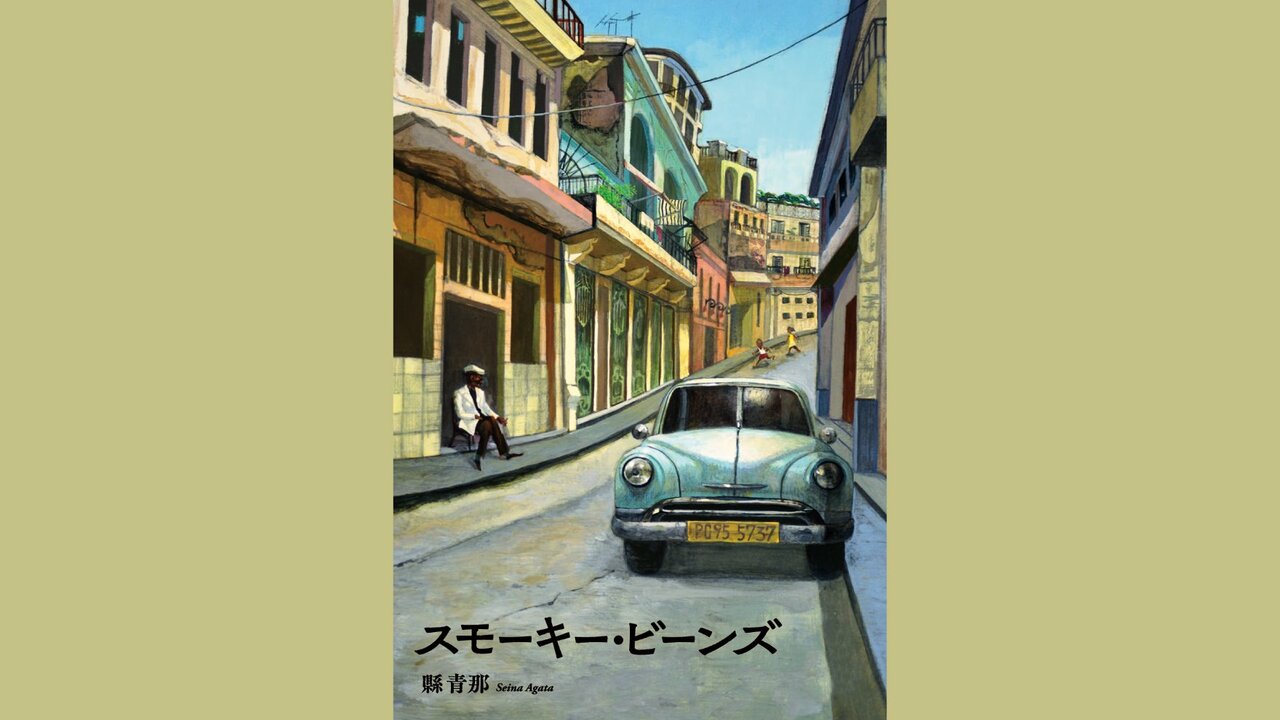再会
彼はすべての食材を丹念に味わいながら食べるようになった。このソテーには何々のスパイスが使われている、とか、この料理の隠し味は擦りおろしたタマネギに違いない、とか、その味と風味への探求は段々と熱を増し、三十代を終えるころには、彼はどんな手の込んだ煮込み料理においてさえも、その具材も味つけも、完璧に言い当てられるほどになっていた。
「そのときの感覚が昂じてね……」
手製のスープを出しながらドン・ロドリゲスの亭主、ミゲルは言った。先だってのオレンジジュースの女性とオンボロ車の男性の話は、彼が聞かせてくれたものだ。カウンターの向こうでは、恰幅のいい彼を縦にも横にも更にひと周り大きくしたような体格の妻が忙しく立ち働いている。長く伸ばした黒い縮れ髪を後ろで束ね、ややぶっきらぼうだが情のある目つきをした、色の白い豊満な肉体の持ち主で名はミルナといった。
そのカウンターから二メートルと離れていない、小さなテーブル席の私と亭主に向かって振り向きざま彼女はこう言った。
「まったく、いまじゃあたしの手料理なんか見向きもしないんだから」