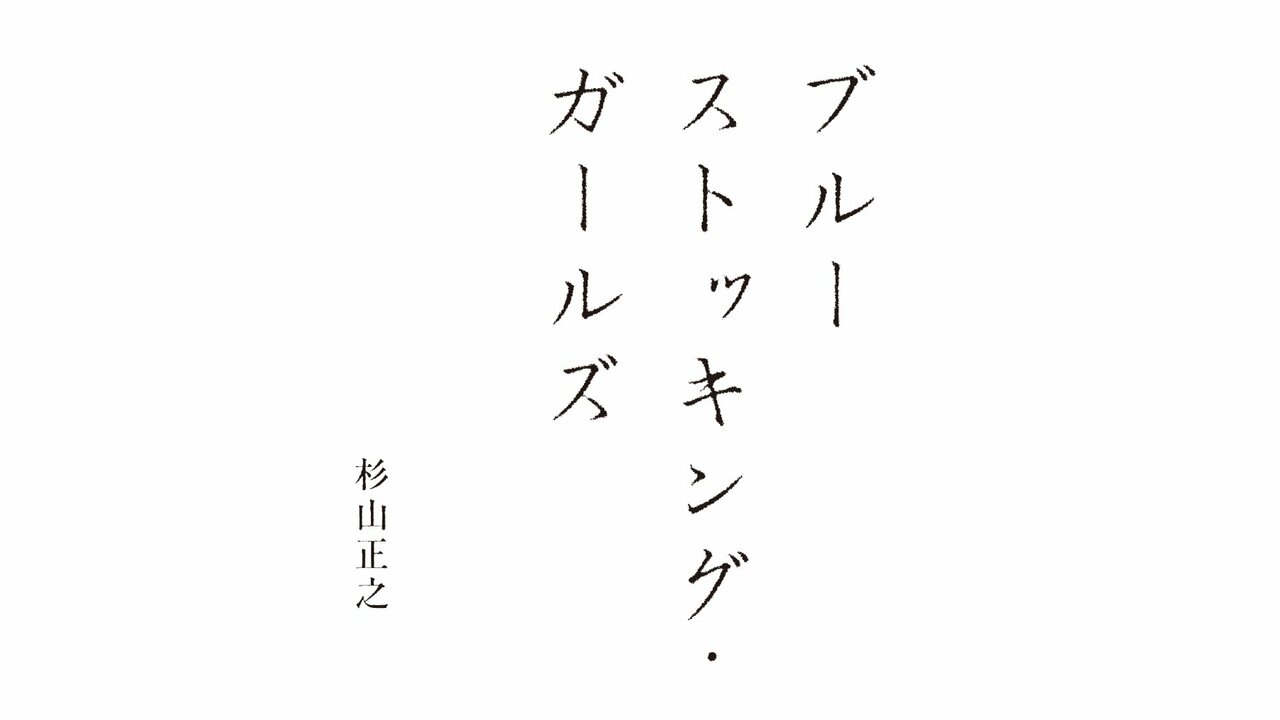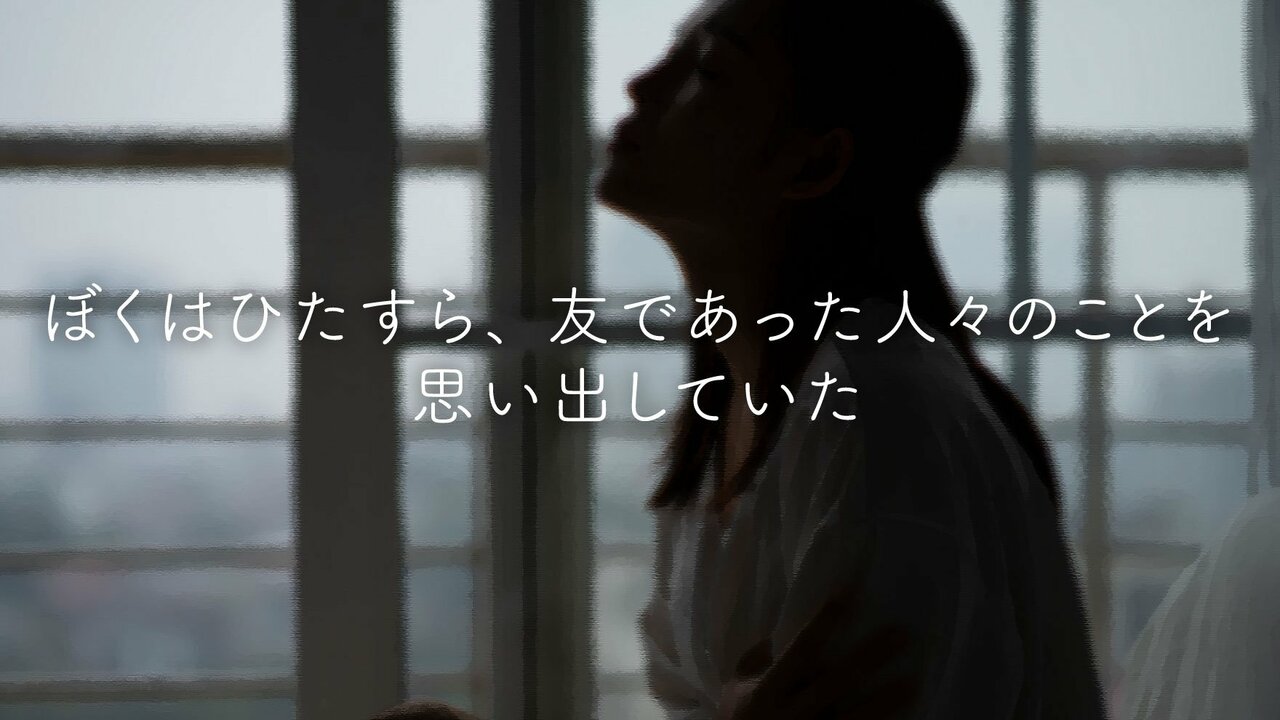第2作『人形』
英二はぼくの襟を掴み上げて立たせると、もう一度ぼくを殴った。
ぼくは学校の横の水なし川の底を歩いていた。雷鳴が近く、辺りは夕方のように薄暗くなっていた。なぜ川底などを歩きたくなったのか。それは雷鳴のせいだったのか。追われているかのように、自転車を乗り捨てて川底に降り立っていた。
何かが欲しかった。それは突然の欲求だった。それが何なのか、ぼくには理解することができなかった。ただぼくは自分の体を痛めつけたかった。できれば雷に撃たれたいとも思った。
驟雨が山を下って、大粒の雨が頰を打った。英二に殴られたところに沁みた。たちまちぼくはずぶ濡れになっていた。ぼくはごしごしと雨で顔を洗った。仰向いて口を大きく開けて、雨を飲んだ。雨はすぐに咽頭まで流れ込み、むせてしまった。叩きつける雨粒はワイシャツの上からも痛い。
「ククククク」
サムが笑う。ぼくも笑い返す。
上流からじりじりと川の流れが近づいてくる。ゆっくりゆっくりと、川は這ってくる。川の流れがぼくの足を浸した。すぐにスニーカーの隙間から水が浸み込んだ。
この川は、ひとたび強い雨が降ると濁流が起こる。それをぼくは期待していたのかも知れない。水嵩はどんどん増してくる。それに抗うかのように、ぼくは流れを遡って駆け出した。自分が狂気じみていると思った。
川の流れが膝まで来たとき、身動きがとれなくなった。強い流れはぼくをどんと押し、突き倒した。そのまま引きずられるように流された。このまま流されたいと思った次の瞬間、自分の命が危ないことに気付いた。すぐ傍にある川岸に泳ぎ着こうとしたが、体の自由がきかなかった。汚れた水をたくさん飲んだ。このまま流れていくのだろうか。水膨れて腐乱し、岸辺に打ち上げられている自分の姿が頭をよぎった。
ぼくはもがいた。もがけばもがくほど、体は回転し、泥水をかぶり、たくさん汚れた水を飲んだ。流れてくる流木は、ぼくの体や頭を打った。その激痛に耐えながら一層もがいた。川が蛇行していた。そこでぼくは奇跡的に岸に打ち寄せられた。助かったと思った。
ぼくは四つん這いになり、泥だらけで土手の上に上った。息は激しく、心臓の音がありありと聞こえた。助かった! 助かった! 雨の中で、熱い涙が流れていることが分かった。
ずぶ濡れで傷だらけのぼくを見て母は驚き、すぐに風呂に入れた。そこまでは覚えている。次の朝、ぼくは高熱に浮かされている自分に気付いた。夏場の寝床は、じめじめと蒸していた。体をどう動かしても、不快感が満ち、体の節々が痛んだ。体がほてり、指や腕を掴むと、浮腫んでいるように太く感じた。暑さに耐えかねて扇風機を回すが、弱にしても身が縮み、叩き付けられるような悪寒に襲われた。
その間にも、ぼくは何度も空虚な白い夢を見た。ぼくはその空間を漂っていた。
そして目が覚めると、部屋の天井があり、机の上にサムがいた。何度も麻酔にかけられたように、眠りに落ちては夢を見る。そんな時間が永遠に続くような気がした。