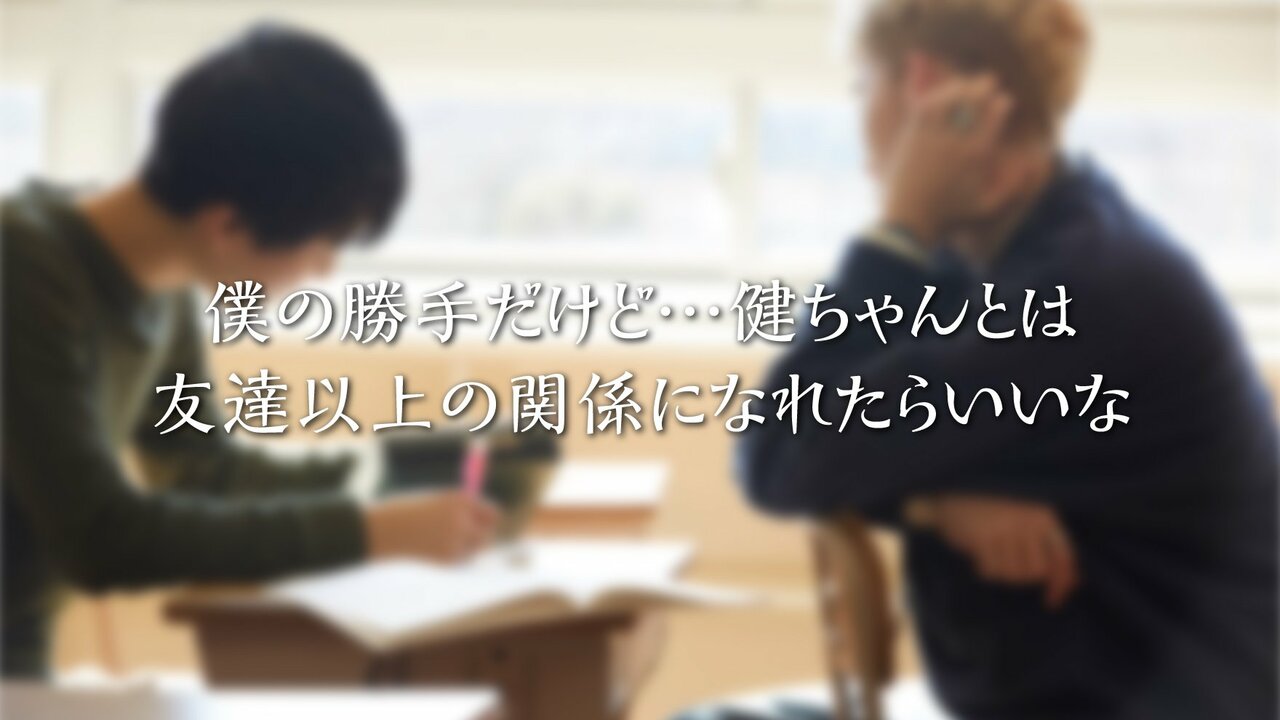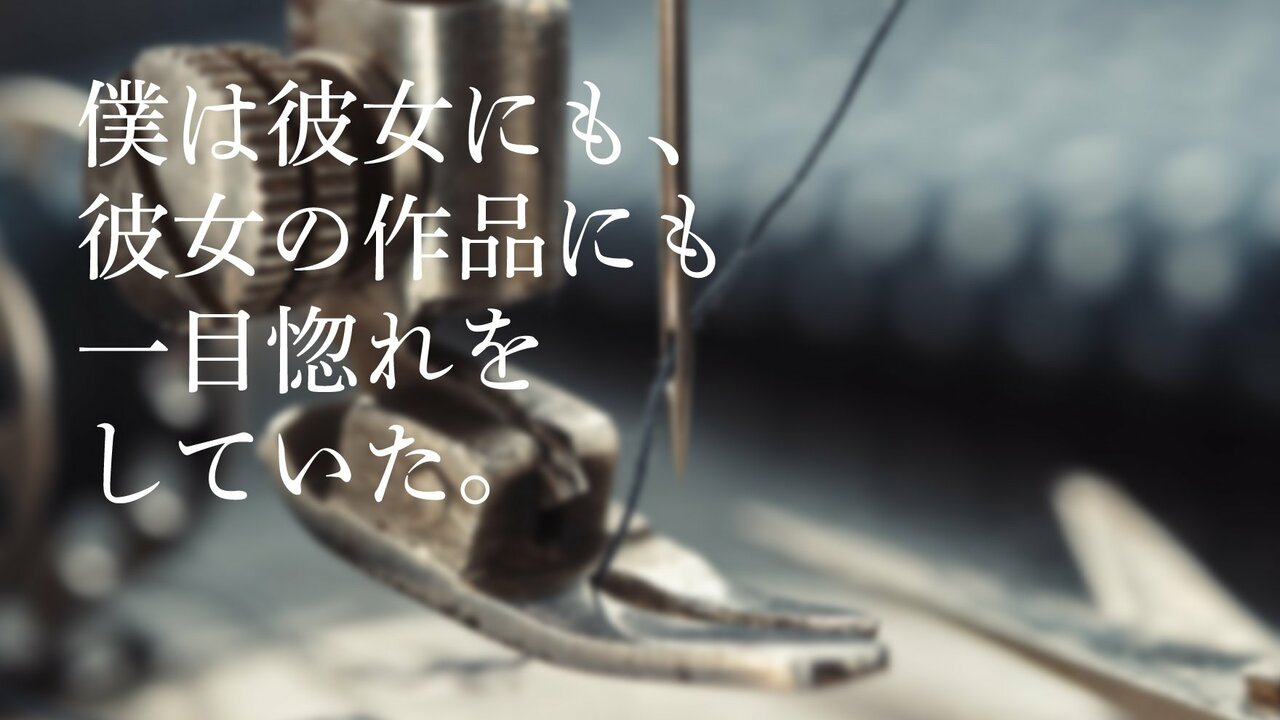僕は普通じゃないけれど
あぁこれが友達か。僕はなんだか嬉しくなってニヤニヤしてしまった。
「おいおい。笑うところじゃねぇだろ。もっと怒れよ」
「そうだね。でも僕の作品にコンビニのサンドウィッチ以上の価値がついていたって知れてうれしいよ。ありがとう心配してくれて」
「当たり前だろ。友達がこんなことされて黙ってられるかよ」
健ちゃんは寂しがり屋だ。一人が耐えられないタイプだ。僕は今までそういう人がグループから仲間外れにされたとき、最後の手段みたいに依存された経験を何回か持っている。
でも一週間もしないうちにそういう人はグループの仲間に戻っていって、また別の人が仲間外れにされると、今度はその人が僕に依存してきた。まるで僕はレンタル友達のようだった。
健ちゃんはきっと、固定の友達が欲しかったんだと思う。それが僕なんて嬉しい。でも少し不安だった。
「ねぇ健ちゃん」
「どうした?」
「いつまで友達でいてくれる?」
「は?」
僕は仲間外れにされた可哀想な人たちの避難所みたいな存在で、友達として定着してくれた人は誰もいなかった。だからこそ知りたかった。彼はいつまで傍に居てくれるんだろう。
「別に期限なんてねぇだろ。卒業しても就職しても友達は友達だろ」
「そっか」
「ほら、早く行くぞ」
健ちゃんはいいやつだし、女子にモテる。そのうち恋人も出来るだろう。それでも友情は一生ものなのだろうか。今まで友達がいなかったからわからない。
交換してすでにもらっちゃったサンドウィッチなんかは食べちゃったけど、新しく買い直して一人一人もらったものを間違いなく返そう。売られてしまったものは戻ってこないけど、誰にどんなサンドウィッチやおにぎりをもらったか全て記憶されている。断りに行くのが面倒だけど、仕方がない。