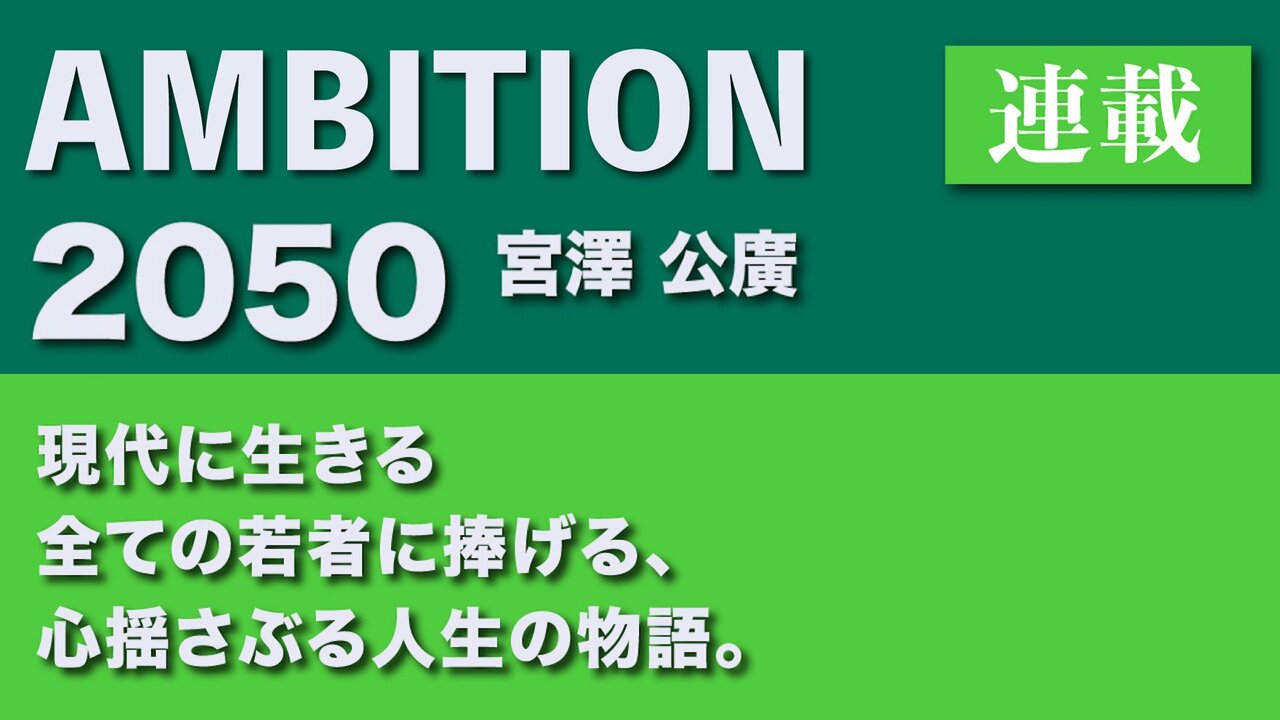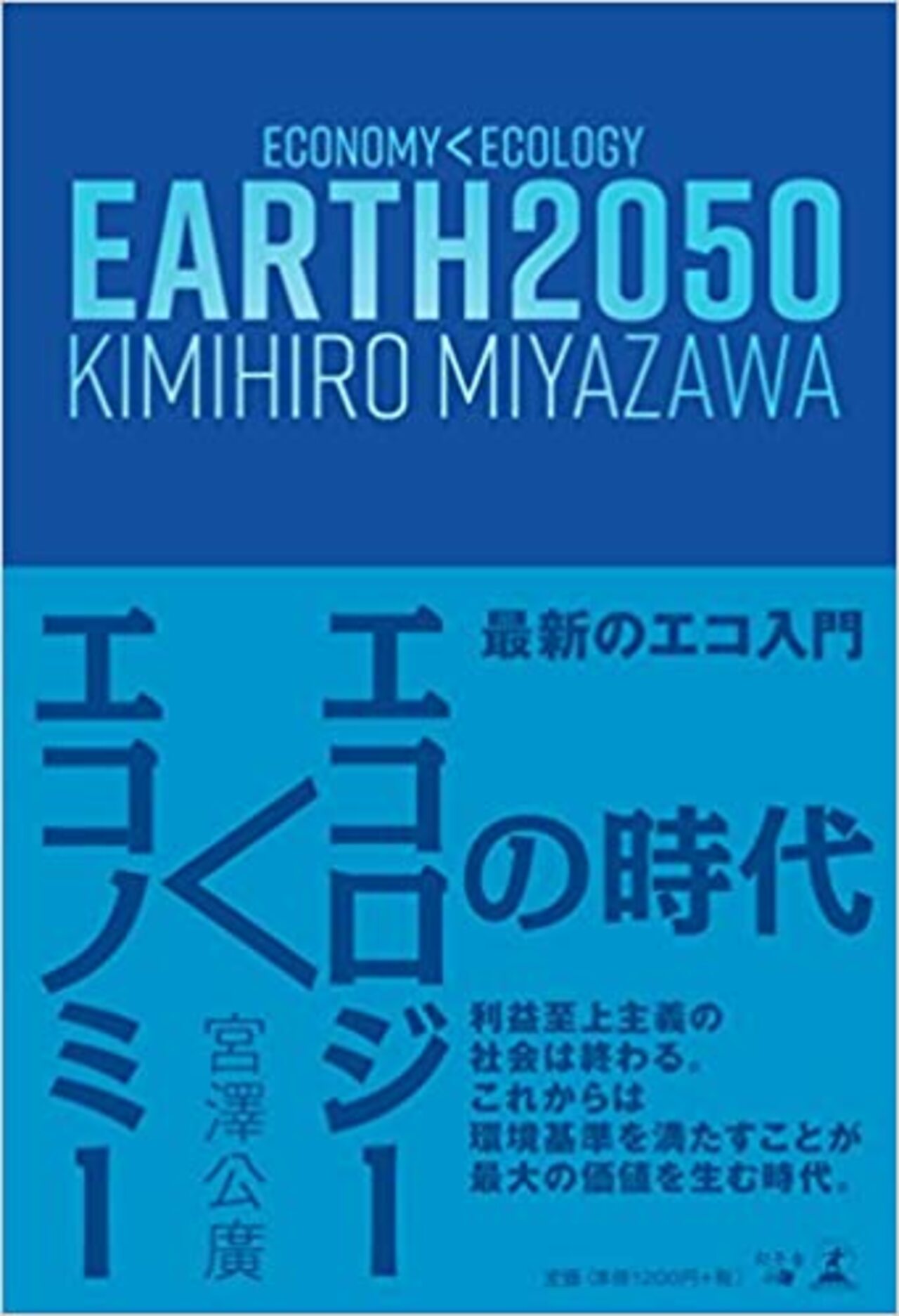第一章 道 程
【7】
昼食には名物の生素麵をたらふく食べ、東回りに島を一周してドライブを楽しみ、島西部の弁天島へ向かった。何でも、潮の満ち引きによって現れる砂の道があるそうで、干潮の前後二時間ほどは歩くこともできるという。この時期の干潮時刻は夕方五時頃なので、四時に到着すれば余裕をもって歩けるだろう。
ドライブ中の会話でいくぶん緊張もほどけた頃、現地に到着した。なるほど砂洲によって南の余島へと続く道ができている。周囲がカップルだらけなので少し意識してしまうが、美穂はまったく意に介さず、「ようけ観光客がおる」と感嘆の声を漏らしている。時折讃岐弁の混じるところに形容しがたい魅力を感じる。
片側が切り立った崖になっている弁天島の展望台に上ると、遠くには島が見えた。美穂によると、どうやら高松の屋島らしい。宮神は小豆島の自然美にすっかり心を奪われていた。
「本当に美しい島だね。もっと長く滞在していたいな」
「ありがとう。そういってもらえるのはうれしいよ」
「今は東京でひとり暮らしだから、こういう場所に来ると心が洗われるようだよ」
「そう」
そっけない返事が気になって美穂を見ると、どこか複雑な表情をしている。まただ。分教場のときもこんな顔をしていた。美穂はやや深刻な表情で、「もうひとつ、見せたいところがあるんだけど」と切り出してきた。宮神は断る理由もなく、首を縦に振った。
車で十分ほど走ると、島の西端にあるビーチに到着した。時刻は夕方の五時を回り、気温が少しずつ下がりはじめている。
車を降りた美穂は砂浜に立ち、黒髪を潮風にたなびかせながら、何やら敵を睨むような目つきで西に浮かぶ島を見つめている。
「小さな島の向こうに、もうひとつ大きな島が見えるでしょう。豊島っていう小さな島なんだけど、あの島にも『二十四の瞳』みたいに子どもが通う学校もあって、当たり前に人々が生活しているの」
「あの島も観光客が多いの?」
「そうね。豊かな島って書くくらいだから、自然の恩恵が感じられるいいところよ。だけど、あの島は不法投棄が問題になっていて、住民たちは環境汚染に苦しめられている。住民は反対しているけど、自治体は見てみぬふり。そんな状態が十年以上続いているの」
「……全然知らなかった」
「都会の人はこういうことを知らないよね」
美穂はそう言ってハッとしたような表情を見せた。
「きつく聞こえたらゴメン。別にね、宮神くんを責めているわけじゃないんだ。故郷の小豆島を美しいって褒めてもらえるのはうれしいよ。けど、美しい自然と隣り合わせで公害も問題になっている現実があるけん。そこまで含めて知ってもらえたらいいかなって」
宮神は愕然とした。無知な自分に対して嫌悪感がこみ上げてきた。美穂の痛切な願いに、胸が押しつぶされそうだった。
自然豊かな離島に幻想を抱き、観光客として都合良く消費し、その実態を知ろうとする努力を怠っていた。たとえるなら、多くの人がリゾート地としての沖縄に抱いている幻想から、米軍基地問題がすっぽり抜け落ちているのと似たような構造かもしれない。
そして宮神は、美しい小豆島と端麗な容姿の美穂を重ね、彼女の内面には島育ちならではの純粋さや無垢さがあるだろうという妄念を、心中で押しつけていたことにも気づいた。美穂がただただ無条件によそ者の自分を受け入れてくれるはずだと夢想していたのだ。
思えば、宮神自身は大いなる自然に生かされて今日に至っている。故郷では山が遊び場で、草花の生命力を身近に感じて育ってきた。高校時代に優秀賞を受賞した課題研究も、ハイマツとホシガラスをテーマにしたものだった。登山という趣味があったからこそ、甲斐駒ヶ岳で清川との邂逅を果たせた。
自然こそが自分を成長させてくれたのだから、環境問題全般に対する関心をもっと強く持つべきだった。チェルノブイリ原発の事故が起こったときには心を痛め、国内の原発立地で暮らす人々に思いを馳せ、ジャーナリストの著作を読み漁った。その危険性について頭に叩き込んだと思っていたはずなのに、喉元を過ぎれば熱さを忘れ、いつの間にか原発のことはあまり考えなくなっていた。
原発事故だけでなく、普段から環境問題へのアンテナを張り巡らせていれば、たとえば豊島の問題について知見を得ていた可能性だってある。小豆島に来てただただ浮かれていた自分が恥ずかしく思える。
「無知の知」を自覚することは賢明とも言えるが、無知を自覚した後には知を追求する努力が必要だ。いくら知らないことを知っていると自らを誇ったところで、謙虚さがなければただの傲慢に陥ってしまう。
名状しがたい縁を感じる大自然を、五十億人もの人々の営みの土台となる地球環境を、後世に手渡したい。そのために、さまざまな環境問題に興味を抱き、美穂のように傷ついている人をフォローできる人間でありたい。だが、現実の自分は理想とはかけ離れている。そのことが宮神を急激に落ち込ませた。
いたたまれなくなった帰り道、宮神は美穂と一言も言葉を交わせなかった。宿に着くと上杉から「どうだった?」と首尾を尋ねられたが、じっくりと話す気力もなく、食事もとらずに布団に倒れ込んだ。