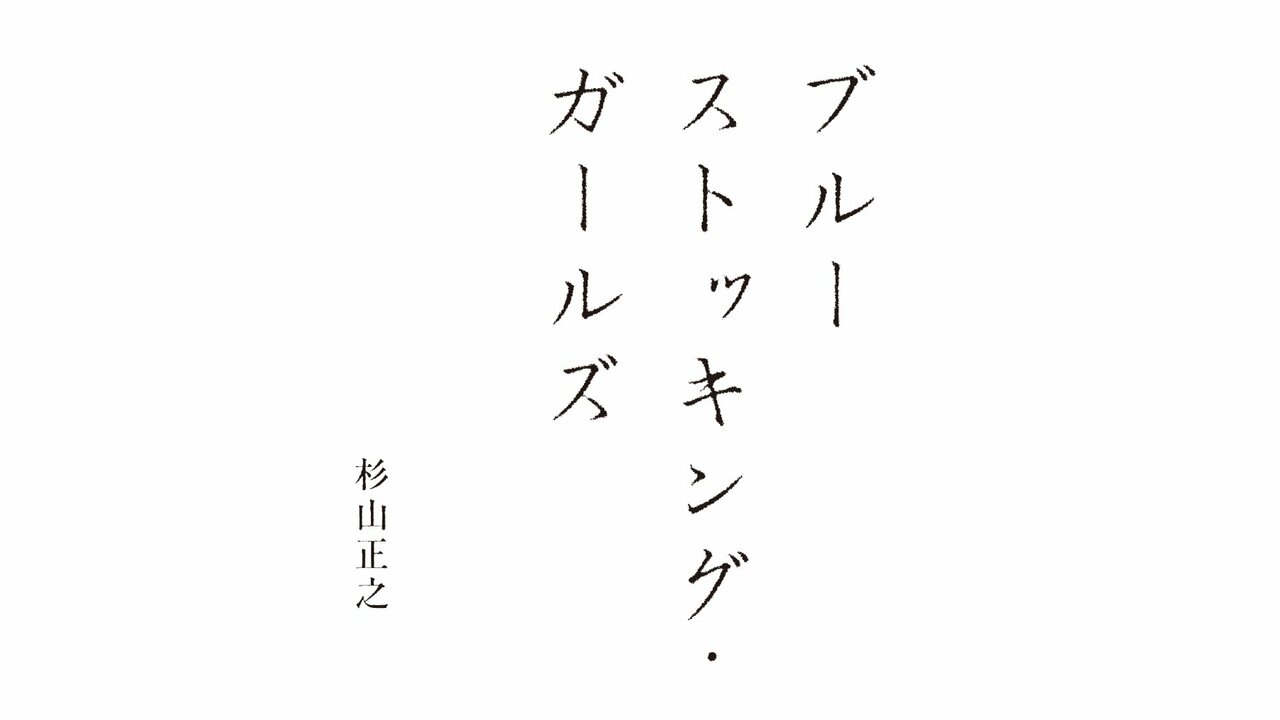第2作『人形』
家に帰ると、自分の部屋の襖をしっかりと閉め、「彼」を机の上に置いた。
身体を真っ直ぐに伸ばすと五十センチぐらいだろうか。棚の上にいたときよりも、意外と大きい。彼の顔は白い陶器だった。眼はガラス玉で、瞳は碧く、虹彩の筋さえもくっきりと見える。しかし口元には悲しそうな笑みを浮かべている。これは棚の上で見たときの印象と違っていた。
髪の毛は金色でさらりと七三に分けている。着ている服はウール素材の、毛羽だった茶色のジャケットだった。映画などで見る、外国のおしゃれな紳士が着ていそうなものだ。靴も革靴で、きちんとした職人が作ったような細かな模様が打たれていた。手足は木製だった。細部まで本当の肌を思わせるような質感で、ふくよかで柔らかそうだった。関節は動くように細工され、積み重ねた本の上に腰掛けさせることができた。ぼくは彼を飽かずに見つめた。そして彼を所有することができた喜びに、微かに震えた。
何となく、彼がぼくを見つめ返しているのを感じた。棚の上からのあの漠とした感覚ではなく、射すくめられているのがありありと分かった。ぼくはしばらくの間、金縛りのように身動きが取れなかった。先ほどまで彼を所有した喜びに満足していたのに、今は何かとんでもないところに彼によって導かれてしまった気がした。もう後へは戻れないところへ一歩足を踏み入れてしまったことを自覚した。それは後悔ではなく、適切な表現ではないが、厳粛な感覚とでも言えた。ぼくは大きく息を吸った。
彼はぼくを見つめている。そして語りかける。しかしそれは言葉ではない。ぼくの心の奥をくすぐっているのだ。それは鬱屈した世界から解放された快感だった。
母が階段下から夕食ができたと伝えた。その声でぼくは彼から解放された。
ぼくは押入れの簞笥の上に彼を座らせて隠した。