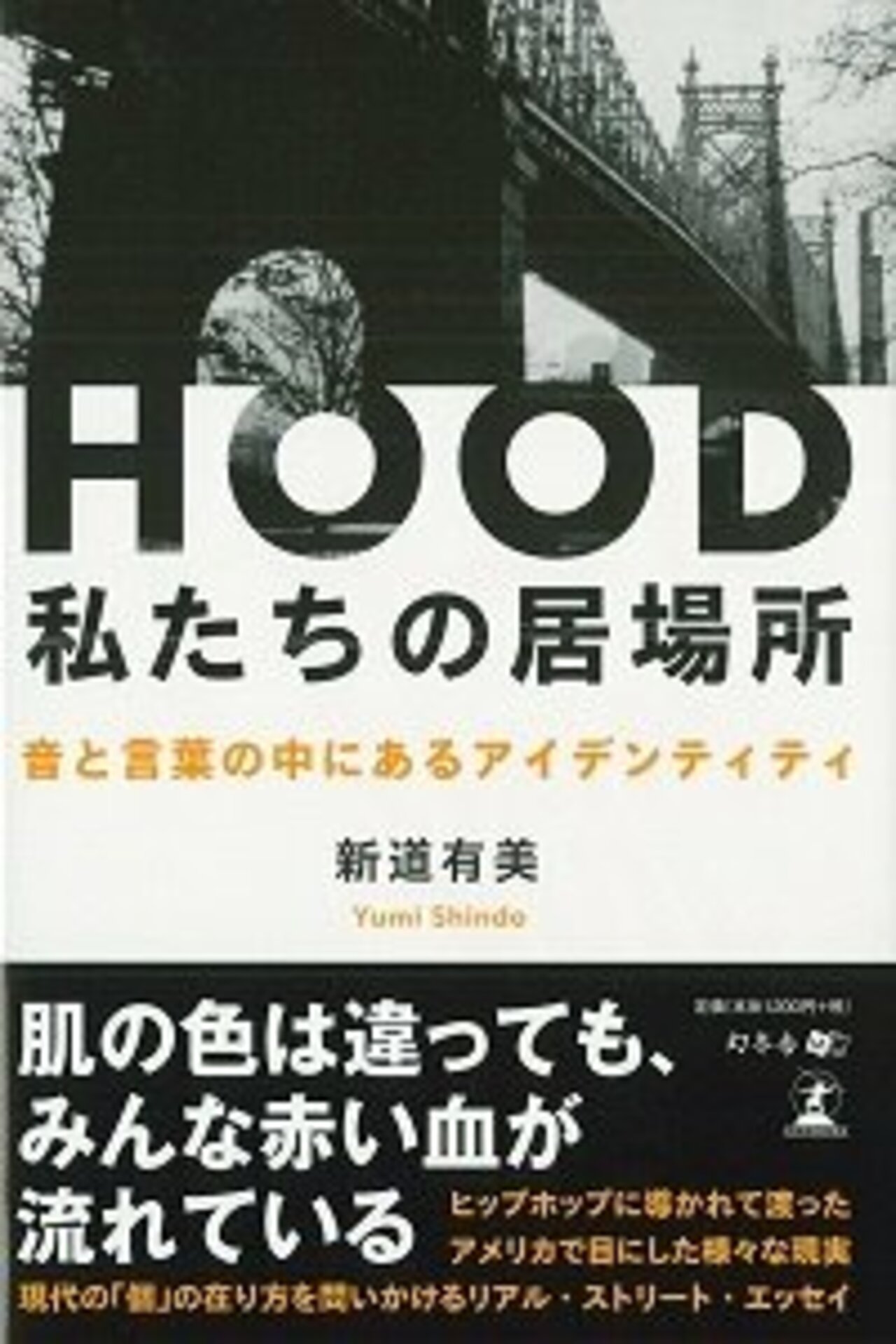だが、この球場だけはナイターの明かりとQ.B.の光に明るく照らし出されている。10代くらいと思われる少年少女たちがソフトボールをしている。一人ベンチに座っていた少年が右手の拳でグローブの平を叩きながら、こちらに向かって来た。
「名前は? このプロジェクトに住んでんの?」
大きな目にクルンとカールしたまつ毛が印象的だ。
「Yumiよ。ううん。ここには住んでない。キミの目ってキュートだね。キミはプエルトリカン?」
「プエルトリカンとドミニカンのミックスだよ。みんな俺の目がいいって言うんだぜ。キミはどこ出身?」
「私は日本人」
「へぇー。ねぇ、彼氏はいるの?」
「いないよ。キミは彼女いるの?」
「うーん。いると言えばいるのかな」
「キミっていくつ?」
「俺、16歳。キミは?」
「……」
ここでは日本ほど、女性の年齢を気には留めない。それでも素直に自分の年齢を言えなくなってきた。とりあえず、「キミよりずっと年上だよ」とだけ伝えた。
「でも、俺のママよりはずっと若いだろ?」
「えっ? キミのママは何歳?」
「32歳だよ」
「……」
まさかとは思ったが、私の予想は的中した。私は彼の母親とほぼ同じ年齢だった。
「キミは22歳とか、23歳ぐらい? オレ、そのくらいなら全然気にしないよ。でも、キミのBodyはまだ10代だよ」
16歳の少年のお世辞とも言えるこの気の利いた言葉に、私は少し気を良くしていた。