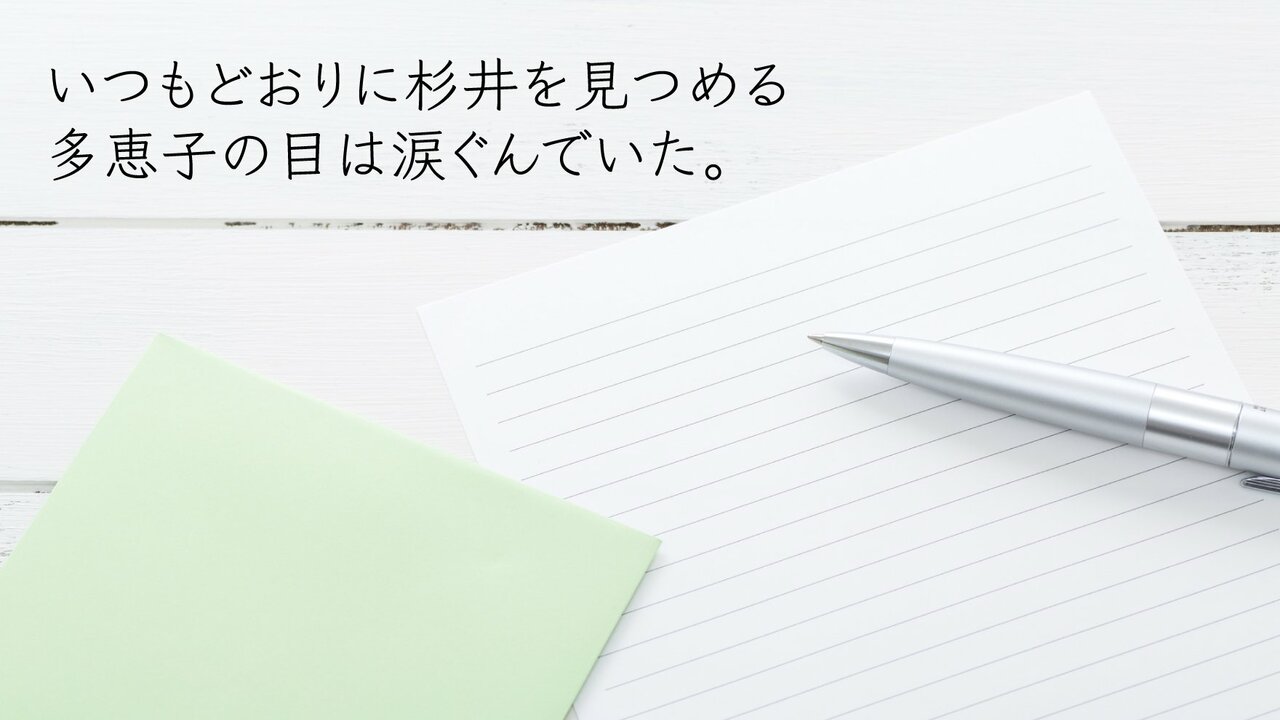「これをいただいたら、上等兵殿が困るのではないですか」
「俺は立場上この種のものはどうにでもなる。午後にでも被服庫に行って員数はつけてくる」
大宮はそう言って、また寝床に横になった。翌々日の月曜日の夕方、杉井が部屋に戻ってくると、寝台の上に新聞紙に包んだ小さな包みが置いてある。中には小さな錠前が五個入っていた。誰が何のために置いていったのだろうと、杉井が不思議そうにながめていると、脇を通りかかった大宮が言った。
「昨日城外の員数屋で買ってきた豆錠だ。これからは洗濯物を干したところには錠をかけておけ」
「ありがとうございます。代金の方は」
「そんなもの、いらんよ」
そう答えて、涼しい顔で部屋を出ていく大宮の後ろ姿を見ながら、杉井は本当に頭が下がる思いだった。同時に、もしかしたら自分を当番に推挙してくれたのも大宮かも知れないと杉井は思った。いずれにしても、辛いことだらけの初年兵生活において、大宮の存在はまさに地獄に仏だった。