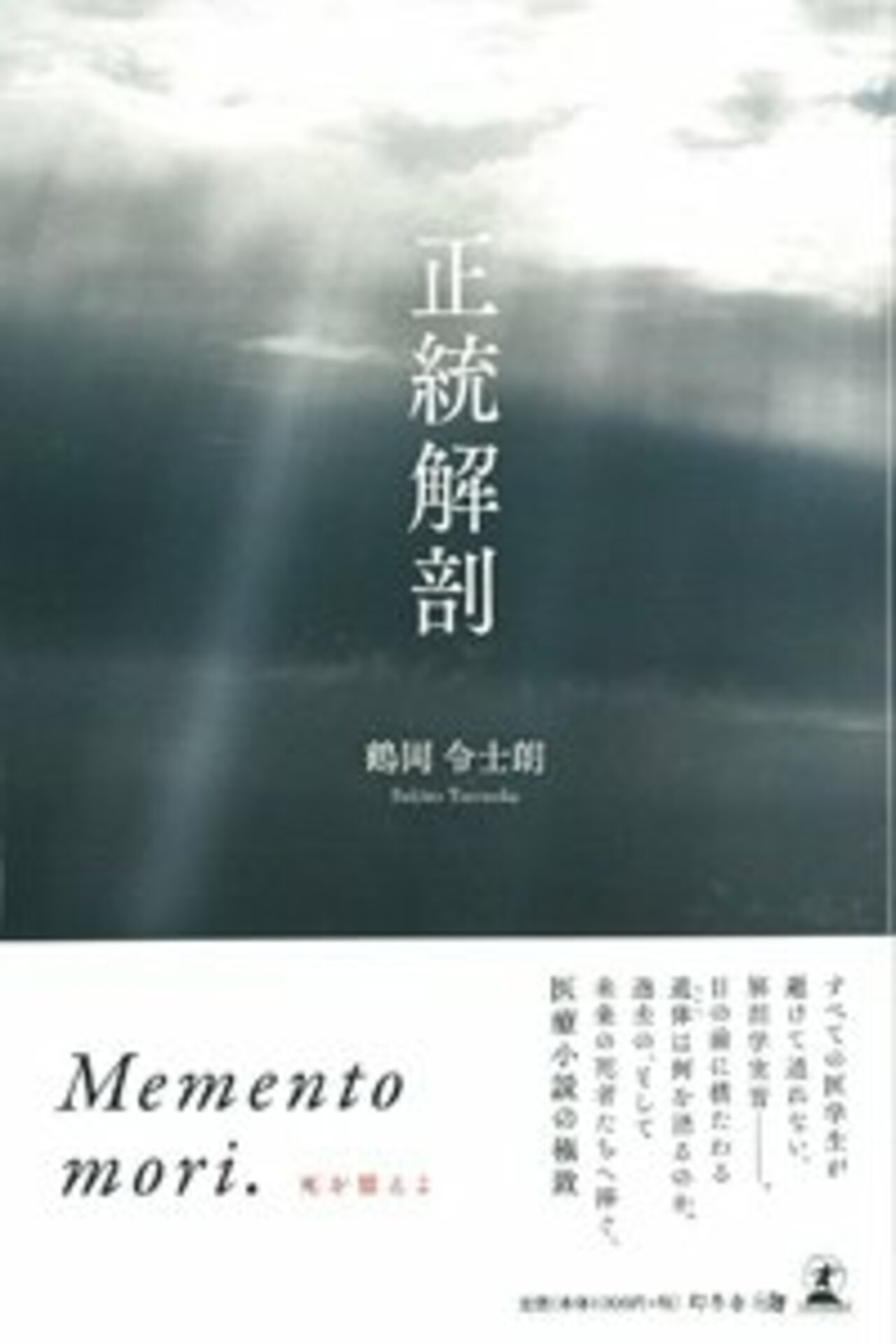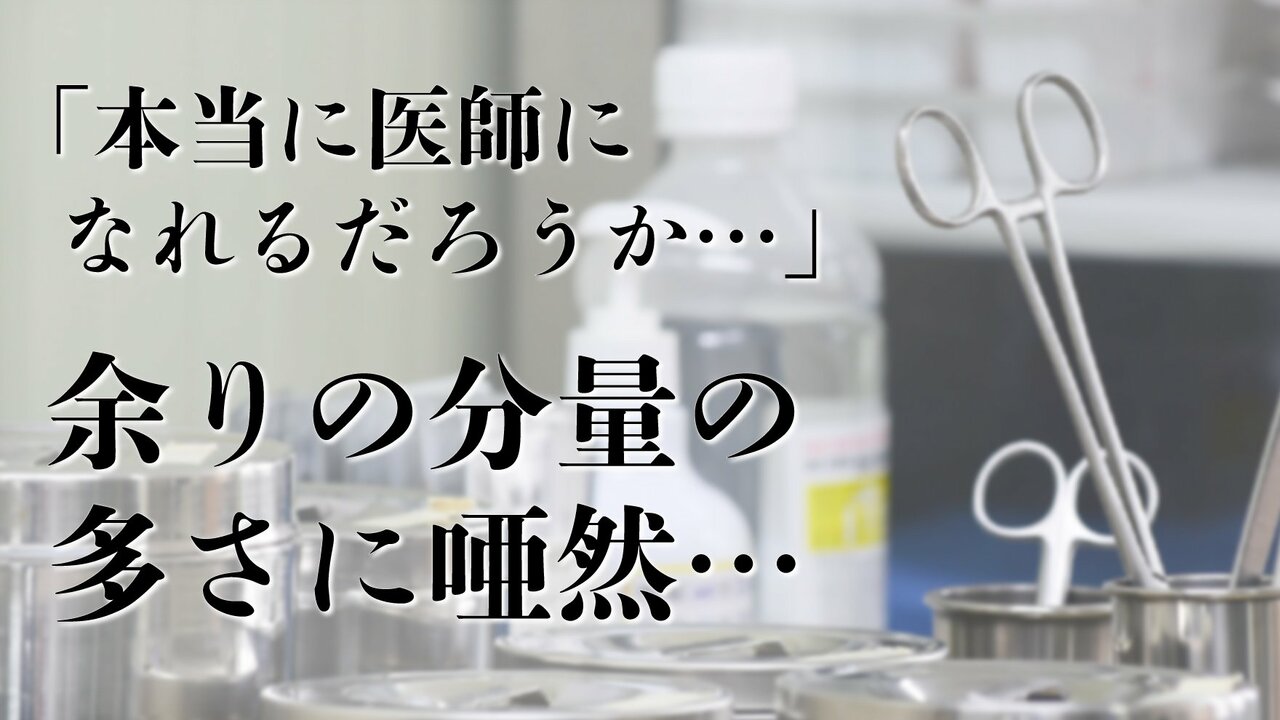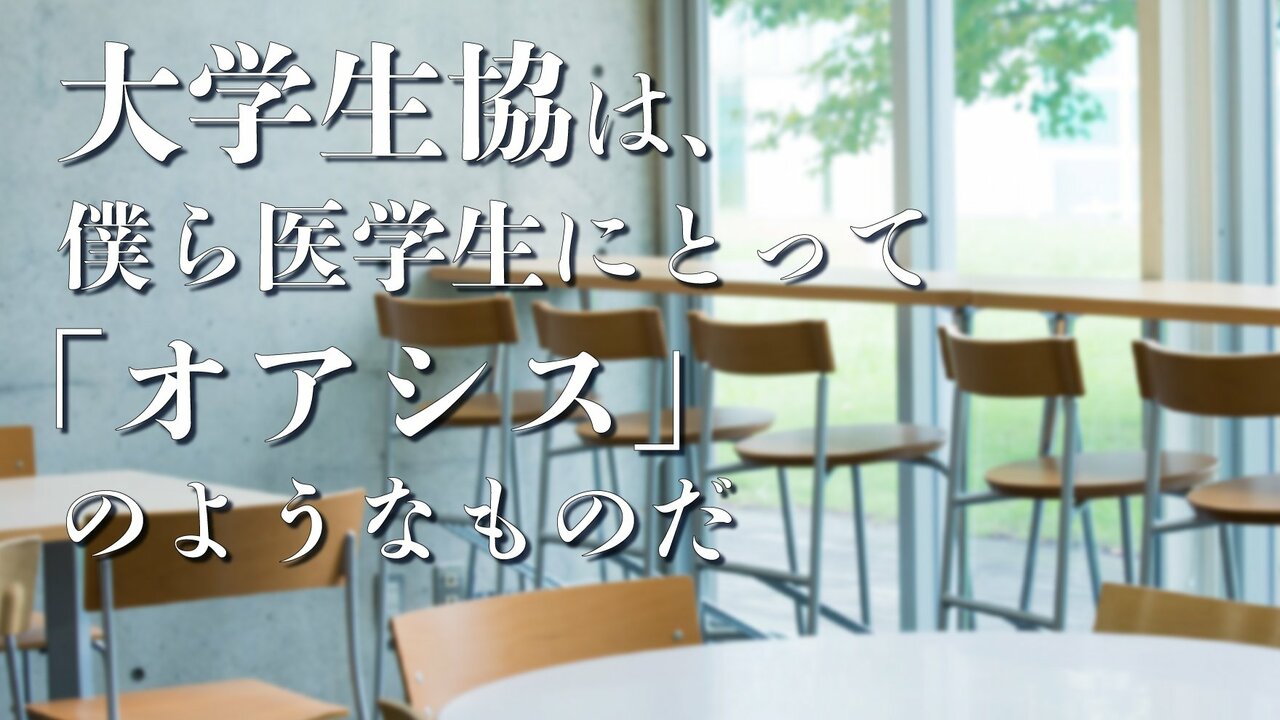生命の崇高と人体構造の神秘を描き切る傑作。
ほぼ100日、約3カ月におよぶ正統解剖学実習。死者と向き合う日々のなかで、医学生たちの人生も揺れ動いていく。目の前に横たわる遺体(ライヘ)は何を語るのか。過去の、そして未来の死者たちへ捧ぐ、医療小説をお届けします。
第一部
もうこれくらいにして、我々も引き揚げようや。疲れを感じて、僕は提案した。
【他の記事も見る】「発達障害かもしれない職場の人」との関係でうつ病になった話
高尾が言った、もうちょっと頑張ろう。その言葉で、みんなは首、胸部、腹部の皮剝ぎを黙々とつづける。
胸部の皮剝ぎを続けるうち、神秘だと思っていた乳房という物が、餅を平たく潰したような白い土台の上の、脂肪の塊を皮膚で包んだものに過ぎず、しかもその土台ごと胸からぽろんと落ちてしまうのだとテキストに予告しているのに気付いた。僕は事実とはいえ、実際にそれを確認するのが、怖い気がした。
もうそろそろ我々も引き揚げよう、と再提案した。
君はあまり勉強熱心じゃないからなあ、高久が揶揄した。
お前には言われたくない、と一瞬思ったが、思い直して他の2人の意見を待った。田上はどっちでも良いといった。高尾は、成るべく進んでおく方が後で楽だし、今日はこの後何も授業がないので、もう少し頑張ろうという意見だった。
結局そうなったが、少し休憩を入れようという事になった。更衣室で実習着を脱いで、着替えていると、この後何回ここでこうして着替える事になるだろう、と思った。脱いだばかりの白衣をふと見ると、水が滴り落ちたような、茶褐色の染みが幾つかできていた。しかし、それはいっこうに乾く気配が無かった。
遺体の脂肪組織の油と血液の混じったものだと気付いた。早く外へ出たいと思った。更衣室の灰色のドアを押し開け、ほの暗い廊下を、色々な感想を銘々が内に秘めて、解放された囚人のように歩く。初めて入った建物なので、どこへ続くのかわからず、皆の行くままに流されようやく外へ出た。