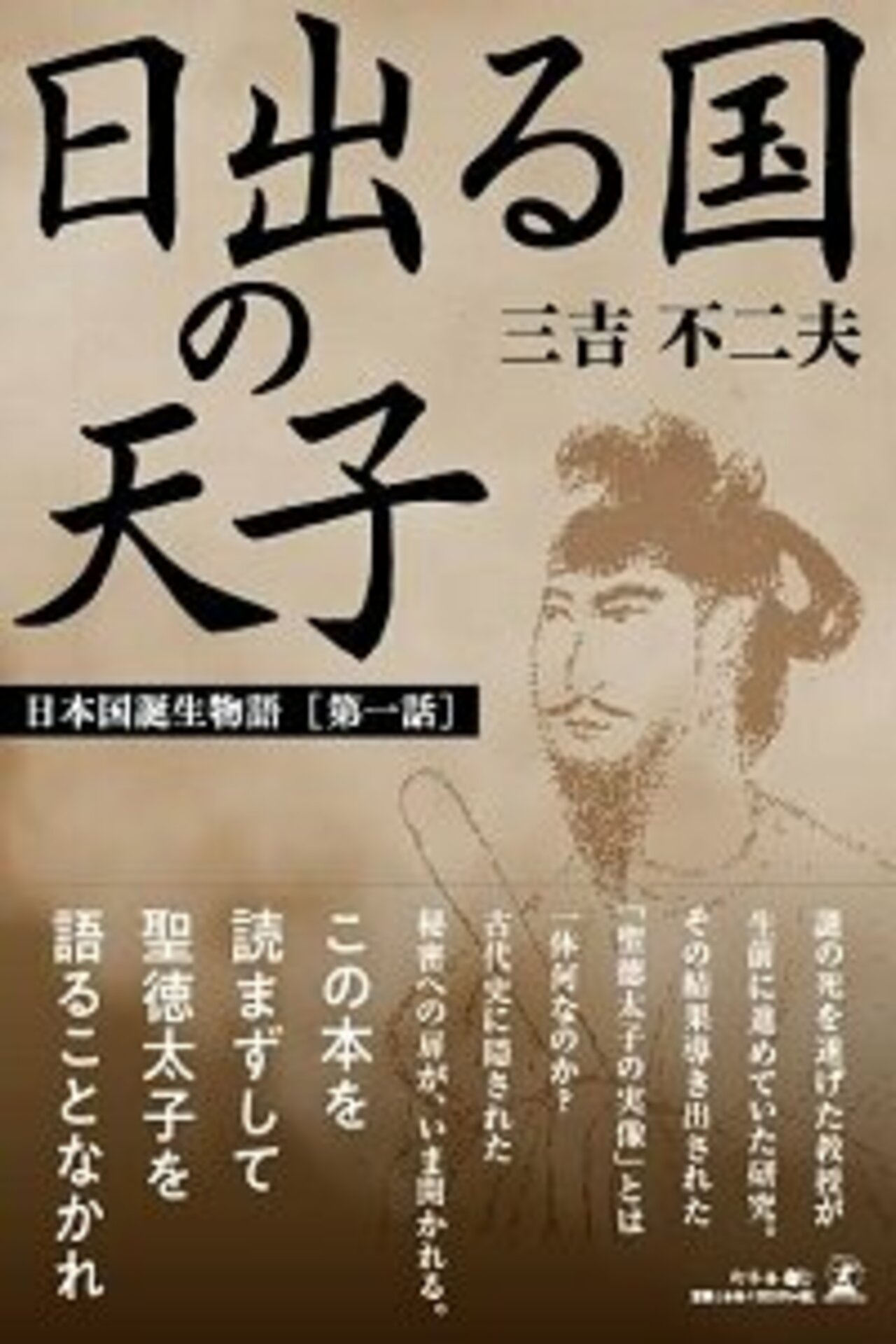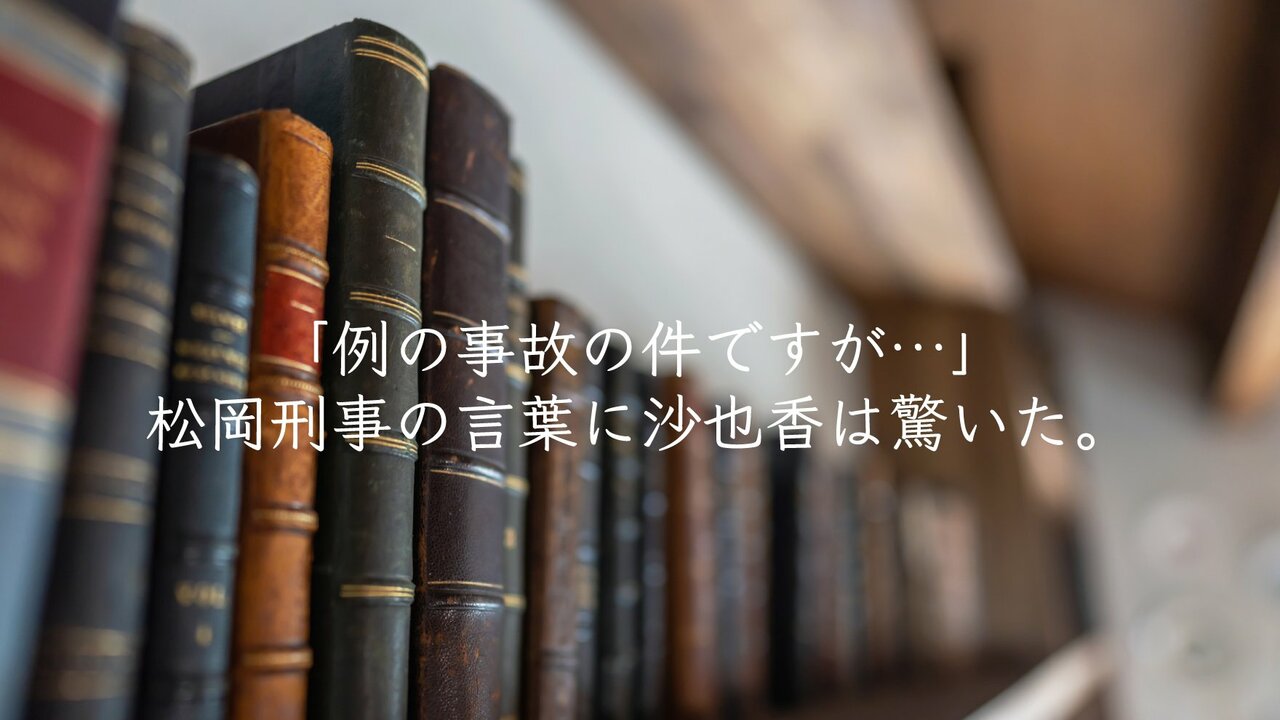──いつまでも学生気分で、こんなキャピキャピした小説を書いていていいのだろうか。
デビューしてからすでに十数年が過ぎ去っている。いつの間にか年齢も三十代の半ばにさしかかろうとしていた。そろそろ歳相応の小説を書くべきではないか。そんなことを考えはじめていた昨今だった。そんなときに思いがけず歴史小説を書いてほしいという依頼を受け、久しぶりに新鮮な刺激に心が揺さぶられていた。
「ふーん、そうなんですか。ならいいんですけど……」
まゆみには、沙也香の心の中がよく見えないことが多い。どうも自分とは違う人種のような気がする。でも彼女は自分のことを好きでいてくれているようだし、まゆみにしても沙也香は大好きな人間の一人だ。だからいつも、ま、いっか!という一言で片づけてしまう。どうもそのあたりが沙也香とは本質的に違うような気がするのだが──。
「でもそれはそれとしてですね」まゆみは今日訪ねてきた目的をようやく話しはじめた。「じつは編集部長が、わが社で高槻教授を紹介したためにこんなことになったのだから、沙也香さんが奈良に行くときに、わたしも同行しなさいっていうんですよ。そしてかかった費用も負担してあげなさいって、いうことなんですけど」
「ああ、そうなの。でもそんなに心配していただくことはないわ。わたしがこの仕事をやりたいと思ったから引き受けたのであって、嫌々することになったわけじゃないからさ」
「ええ、それはいまの話でなんとなくわかりました。でも編集部長の申し出は引き受けていただかないと困ります」
「どうして?」
「だって、わたしが編集部長に叱られますから」
「ハハハ……わかったわ。そういうことね」
沙也香はおなかを抱えて笑った。いかにもまゆみらしい。心の中の思いを言葉で飾らずにそのまま出してくる。見栄や駆け引きという単語は、彼女の辞書にはないのだろう。そんなまゆみの率直な人柄を沙也香は愛していた。
「じゃあせっかくだから、編集部長さんの申し出を遠慮なく受けさせていただくわ。でも、まゆみさんと一緒の旅って、楽しくなりそうね」
「はい。わたしも楽しみです」まゆみも明るい口調で応えた。