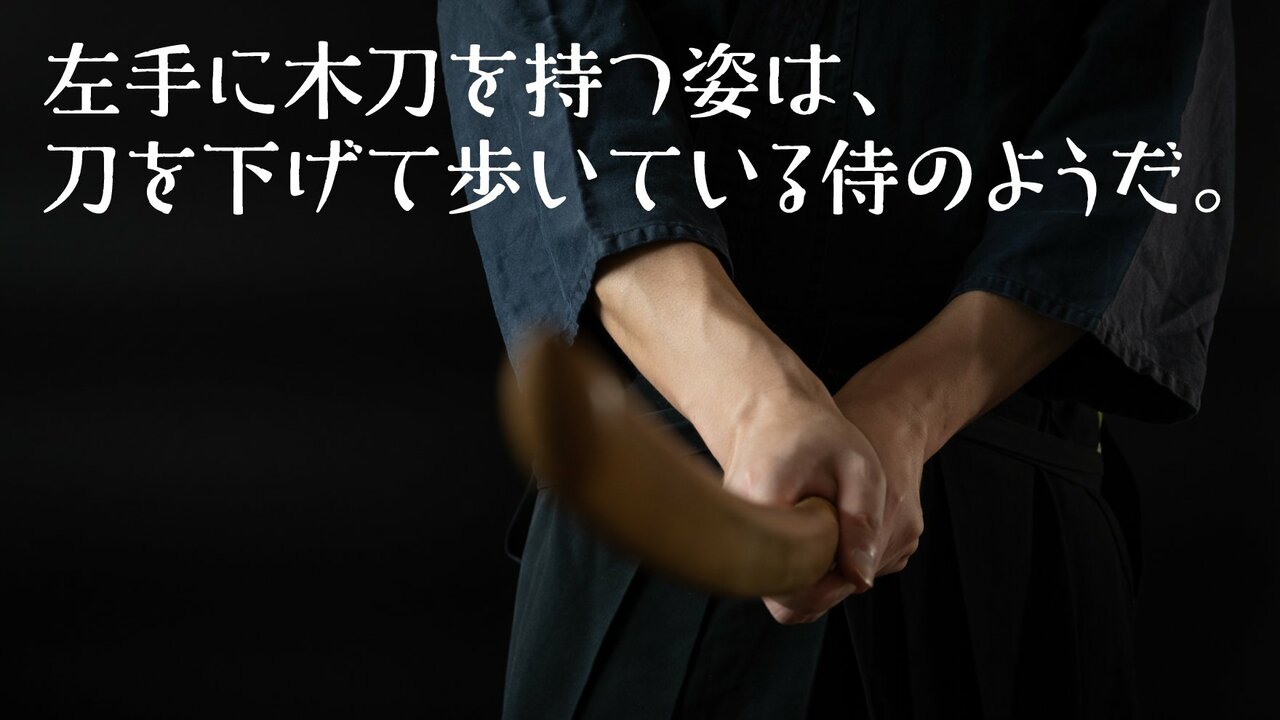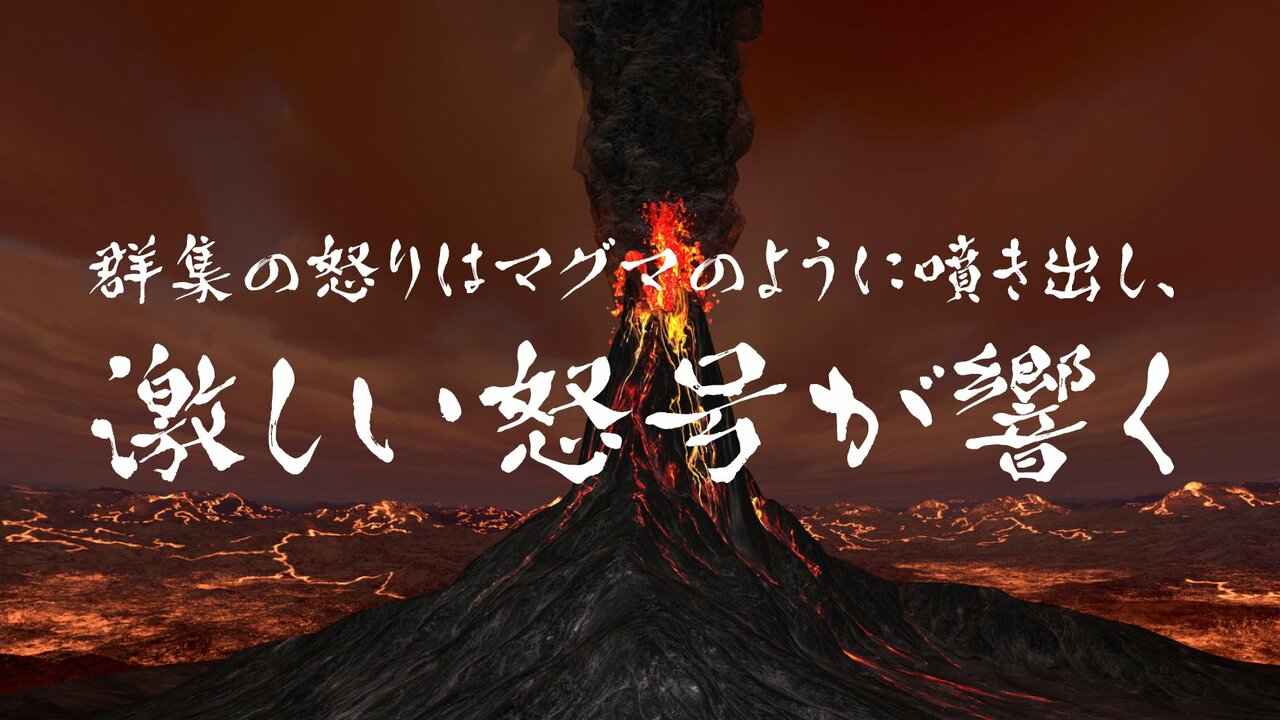この家は、江戸末期に、福岡藩士が幕末の混乱を避けて建てた屋敷であった。危険が迫った時のために逃げ道が造ってあり、地下のトンネルを通って、隣の神社に抜けることができる。
「お父さんがつけた電気のスイッチが、どこにあるか覚えているかな?」
幸子は大きくうなずいた。そして、顔を上げ、声に出して答えようとすると、父親が自分の口に人差し指を当て、声を出さないようにと無言で伝えた。幸子は父親と二人だけの秘密に心が躍った。この家のトンネルのことを知っているのは、父親と幸子だけだ。母親にも内緒になっている。
「トンネルに出る扉の開け方も覚えているかな?」
大きくうなずくと、今度は幸子が自分の口に人差し指を当て、声を出さずに笑った。
ところが、笑った直後に、またしても幸子は不安な気持ちにさいなまれた。父親と自分だけが知る「秘密の抜け道」を使うようなことが起こるのではないかと、恐ろしくなったのだ。
父親に見せないように我慢していた涙が、幸子の目からこぼれた。
涙をこぼして声もなく泣き出した幸子を見て、父親が言った。
「どうして泣くの? 幸子」
幸子は黙って首を振った。不安で胸が締め付けられるような思いを、どう表現していいかわからなかった。今、感じている恐怖は、これから自分の身に起こる悪い予感のような気がしていた。しかし、それはただの気のせいかもしれない。なぜ不安なのかもわからず、小さな心臓から膨らんだ恐怖が行き場をなくし、涙として目からこぼれ落ちたのだ。
「泣かなくていいよ。お父さんがいつも幸子を守ってあげるから」
父親がそっと添えた手を幸子は握りしめた。
このとき、父親は自分が感じている不安を、幸子が同じように感じていることに驚いていた。
急にインドから呼び戻され、短い期間の任務が命じられた。それも、幸子を連れて赴任するよう命令があった。
新しい任地は、国交のない国である。
父親は嫌な予感を覚え、いぶかしんだ。
「日本の警備隊の中に、幼い子供を連れている者がいることは、相手国の警備を信頼している証になる。今回は娘の帯同は命令だ」と言った上官の言葉にもひっかかっていた。
「まるで幸子は『人質』ではないか」という気がしていたからだ。
父親は幸子を新しい任地に連れて行くことに、これまで感じたことのない胸騒ぎがしてならなかった。