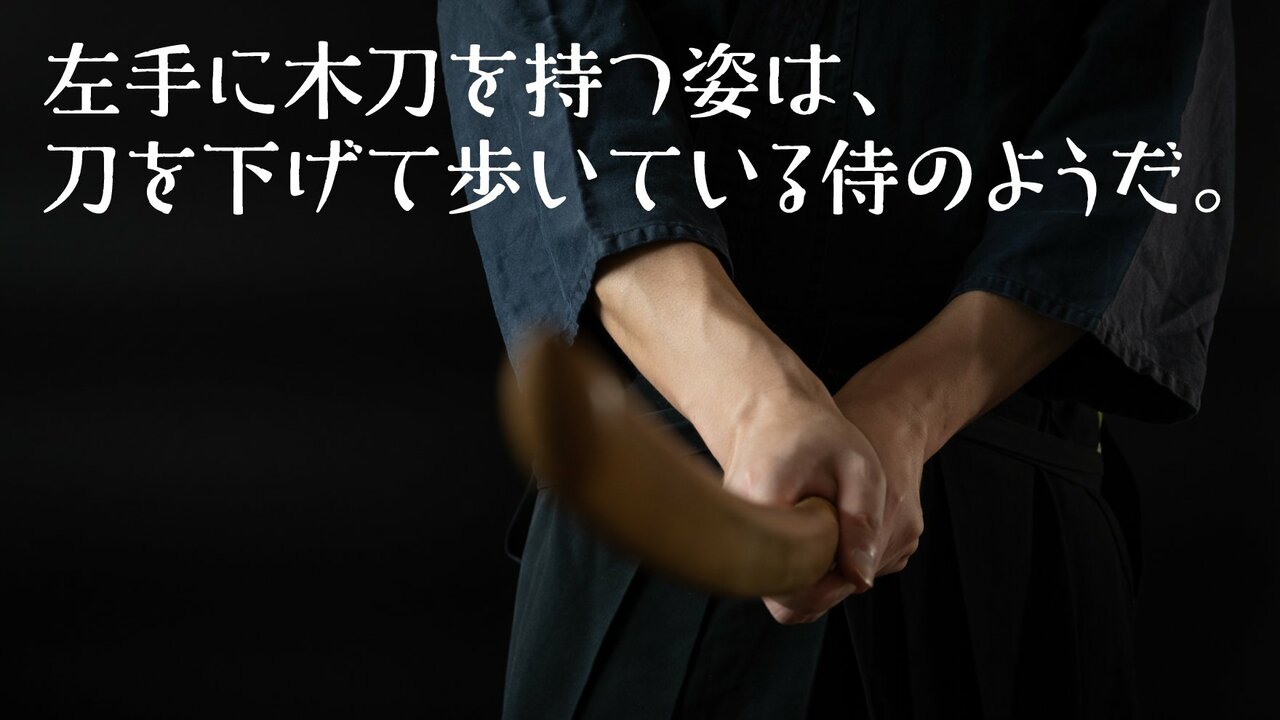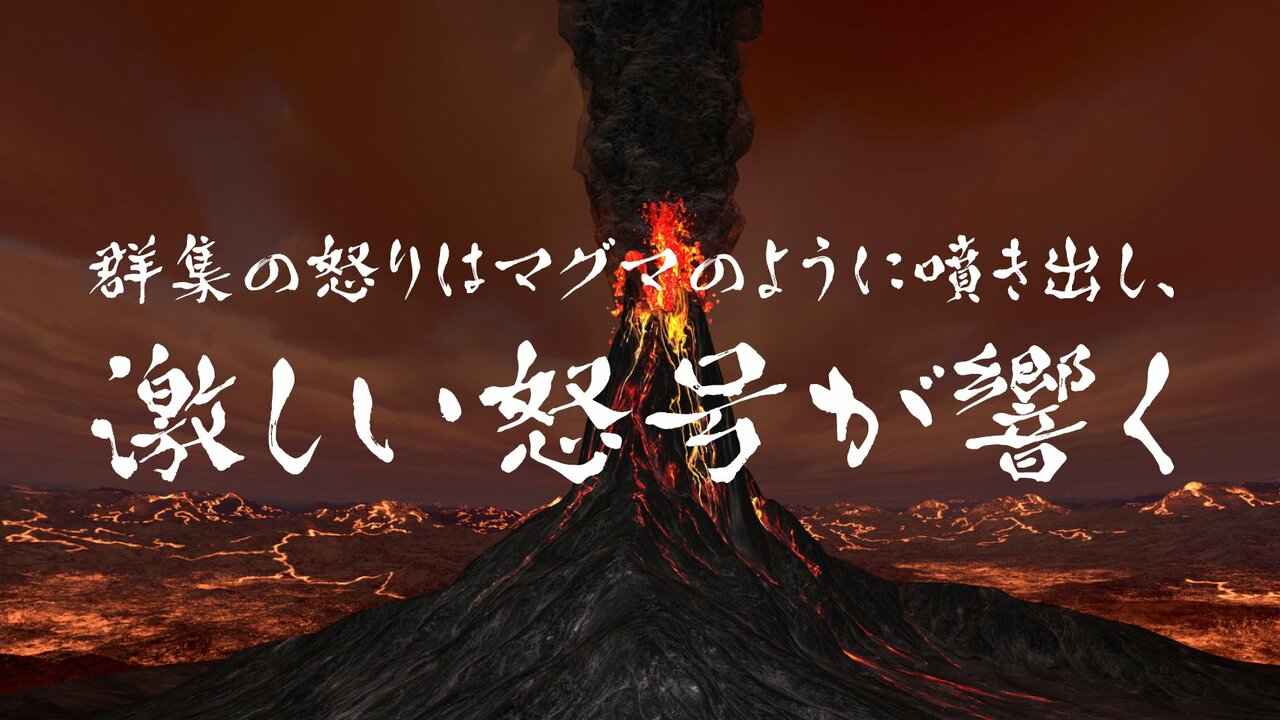コール・サック ―石炭の袋―
父親が空を見上げたまま幸子に語りかけた。
「星はいろいろなことを教えてくれる。明日の天気や、幸子が今、どこにいるかも」
幸子はぶどうを食べながら、空を見上げて聞いていた。
「もし、街で道に迷っても、星がどっちに行けばいいのか教えてくれるよ」
父親の言葉を聞き、幸子は突然、不安な気持ちに襲われた。
幸子は、インドで独りで出かけたことがなかった。東京でも独りで出かけたことがなく、独りではバスに乗ることもできない。独りで自宅の周辺を歩いたこともなかった。
そんな自分が独りで家を出て道に迷ったら、本当に家に帰って来ることができるのだろうか。不安が幸子に重くのしかかった。
「私、本当にここに戻って来られるかな」
幸子はぽつりとつぶやいた。
父親は家の隣にある神社の大きな楠の木を指で差すと、優しく言った。
「神社のあの楠の木を覚えていてごらん。それと、この庭から見える星空を覚えていれば、星が教えてくれる。幸子なら、何年経っても、この街がどんなに変わったとしても、星を見て、あの楠の木を目印に、ここに戻って来ることができるよ」
幸子は不安な気持ちのまま、神社の楠の木を見た。
庭の向こうに、神社の祠と鳥居が黒い陰になって見えている。その向こうには、大きな楠の木の影が星空に浮かび上がっている。楠の木は大木で、大きく枝を張り、星空に浮かぶその姿は森のように見える。
父親は幸子が不安な気持ちを抱いていることを感じて言った。
「戻って来られるよ。お父さんはいつもここにいるから、幸子もここに戻っておいで」
父親は幸子を安心させるためにそう言うと、もう一度、星空を見上げた。
「今日は天の川がきれいに見えるな」