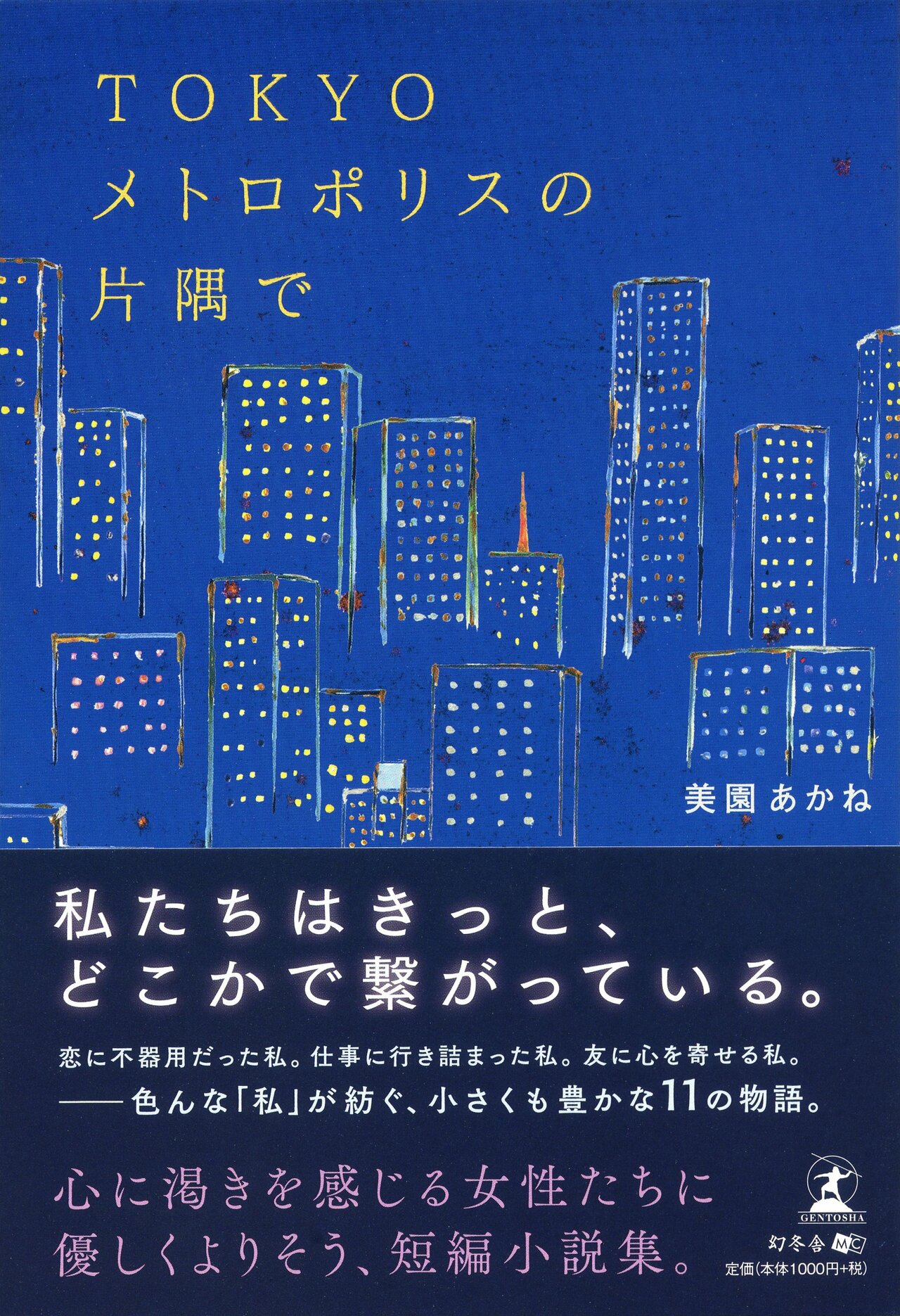さやかは里菜ちゃんと目を合わせながら、懸命に励ましたが、彼女の表情は少し曇(くも)ったままで、あまり変わらないように見えた。
その後、さやかは、自宅アパートに帰ってすぐ、お風呂に入った。バスソルトを入れた熱い湯船(ゆぶね)に浸(つ)かりながら、今日のことを考えていた。
〝自分の言葉は、どこまで里菜ちゃんに届いたのだろうか〟
そして、ふとあることを思い出していた。
*
水泳部だった高校時代のある夏の日の夕方、さやかは、部活が終わったあとも、自主練を三十分ほどするという理由で、ひとりプールで居残りをしていた。そして、午後六時を過ぎても、まだ明るかったが、誰もいなくなったのを確認してから、プールサイドで水着を脱いだ。
裸のままプールに入って泳ぎ続けた。水着を着ているときには味わえない解放感、水の冷たさ、消毒液の匂(にお)いを、全身で感じ取っていた。なんだか自分がマーメイドになったような感覚だった。
その後、水泳部を引退してからは、新しいことに挑戦したくて、水泳からは、しばらく離れていた。おしゃれなさやかは、ファッションについて勉強したくて、都内の女子大の被服学科に進学した。そうして、徐々に頭の中から薄れてしまっていた、マーメイドの記憶。この記憶の中にあるものこそが、
〝うまく泳ぐことよりも、まずは泳ぎを楽しんでほしい。でも、それをどう伝えていけばいいかわからない〟――と、ずっと悩んでいた自分自身への答えになりそうだった。
さやかは次の月曜日に出勤すると、里菜ちゃんの母親に電話をかけた。
「榎戸(えのきど)さんですか? 里菜ちゃんのことなんですが――」
「え、あの子が何か、しでかしましたか?」
「いえ、そうではなく、里菜ちゃん、ちょっと、スランプ状態に陥おちいっているようなんです」
「はぁ」
「そこで、ご提案なんですが、夏休みに一泊二日のサマーキャンプに参加されてはいかがでしょうか。海水浴がありますので、楽しさの中から、スランプを脱するきっかけをつかめると思うんです」