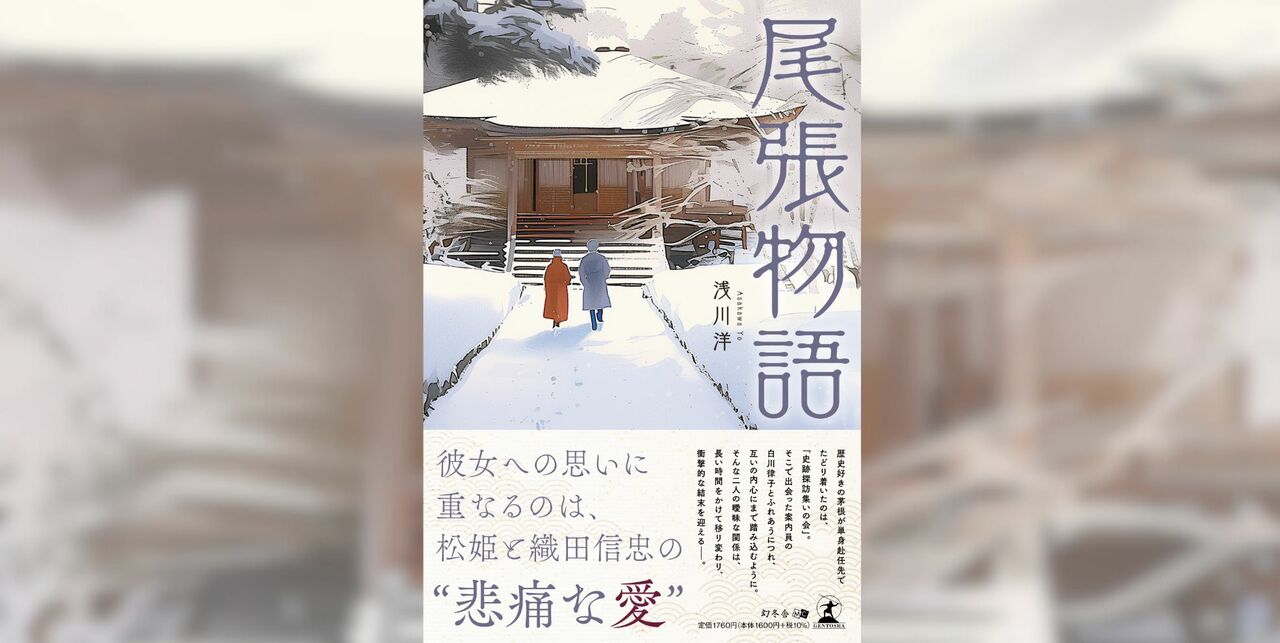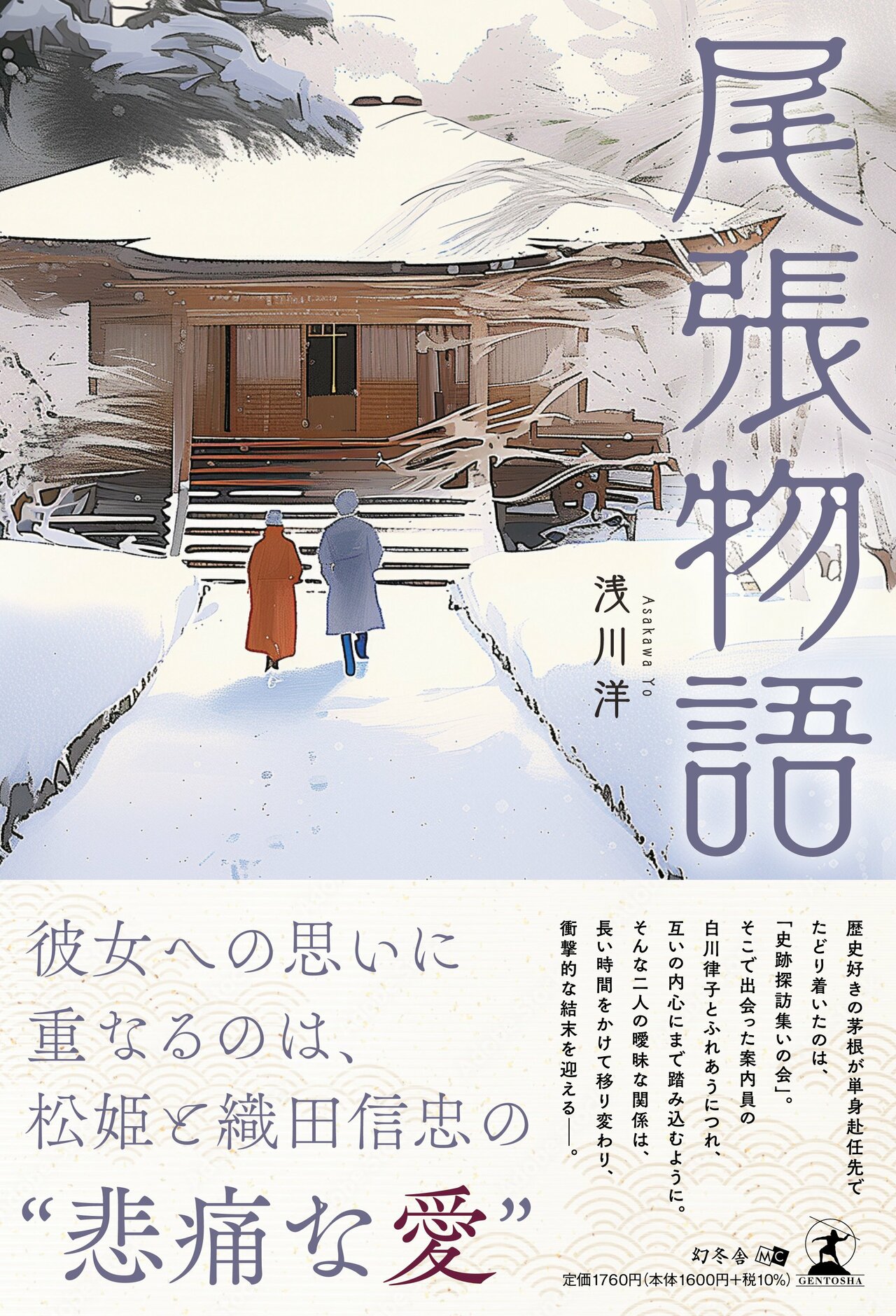【前回の記事を読む】一人旅を終えて帰宅してから約一カ月後、彼女から手紙が来た。そこに書かれていた内容に驚愕した
第二章 分岐点
ベンチを立ちかけた時、植え込みの近くで気ぜわしく動く物体に目が留まった。桜の根元を避けるように蟻が隊列を組んでしきりに往来していた。その隊列の途中に仰向けになった蝉の死骸にたかる蟻の一群があった。蝉は飛翔していて突然息絶える。蟻にとって格好の餌食だった。食いちぎられた羽が群がる蟻に引きずられ運ばれていた。
茅根は四十代前半に名古屋に単身赴任した。
転勤は家族重視となる今の時代は嫌われるようだが、それは家族がバラバラになって生活することも多いためだろう。夫婦や家族は帯同することが好ましいことはいつの時代も同じだが、妻が職業に就いている場合や、子供の教育の問題で単身赴任を覚悟しなければならないことも多い。茅根の場合もそうであった。
茅根は単身赴任は初めてだったが、帰京した場合、手当として往復の旅費が月一回に限り支給された。金曜日の夜帰京すれば土、日は家族水入らずの生活ができる。しかし帰京を予定していても、突然接待ゴルフなどが入ってしまうと帰るわけにはいかないことがあった。それでも茅根は働き盛りだったので単身赴任はそれほど苦にはならなかった。
一番気を使ったのは食事だった。結婚してからは今日何を食べようかなどと悩んだことはなかったが、独身時代のように自炊することになり、休日には近くのスーパーに出かけ、まとめ買いをした。晴れの天気予報を当てにして洗濯物を干したまま出勤してしまい、帰宅して雨に濡れた洗濯物を取り込む時には単身の悲哀を味わった。
休日、話しかける相手もなく一日無言でいることに耐え難いこともあった。ただし読書には最適だった。仕事は残業が当然、接客で飲酒しなければならないことも多く、なかなかハードな生活であった。
転勤は新しい人間関係作りから始まる。茅根は人付き合いはうまいとは言えなかった。というか、人を惹き寄せる魅力を持ち合わせていないと悩んだこともあった。
人との軋轢は仕事をすればそれなりに生ずる。かつての高度成長時代とは違いパイが限られているため、差別化は必要だという。誰もが皆、傷つきやすい環境の中で働いていて、能力主義が浸透してきていた。