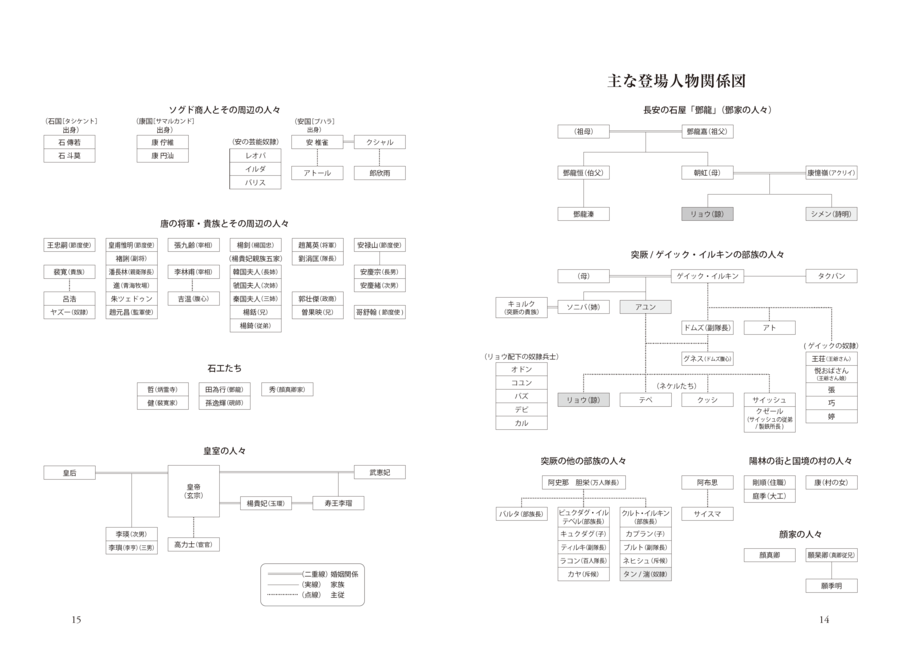第一部 草原の風
一 白昼の襲撃
(一)
草の上にごろりと横になり、手足を大きく広げて空を眺めているリョウの視線の先には、初夏の空が高く澄みわたっている。周りでのんびり草を食んでいる羊の群れを、そのまま天に映したかのような、丸くて白い雲がゆっくりと流れていた。
ついふた月ほど前には、川も沼も氷で固く閉ざされていたのに、短い春はあっという間に過ぎ、これからの三ヶ月はリョウが最も好きな季節になる。
陽は中天を過ぎてしばらく経っていたが、暑いというほどではなく、草原をわたる風がリョウの頬に気持ち良かった。リョウは風に吹かれるのが大好きだ。
もちろんこのさわやかな風は誰だって好きだろうが、リョウは冬の冷たい風でも嫌いにはなれなかった。なぜなら、リョウの本当の名前はソグド語1の〝リョズガッシュ〟で、それは〝風〟という意味だから。
リョウは父親に、自分の名前はどうして〝風〟なのかと尋ねたことがある。父は言った。
「風は空の神の使いなのだ。大空を自由に行き来して、自然と人間とを繋いでくれる。優しく人を包むこともあれば、激して大きな力を振るうこともある。そして誰も風を捕まえることはできない」
ソグド商人であり、武人でもある父は、西域(中国から見た西方諸国)と唐の間を数えきれないほど行き来したという。まだ幼かったリョウは、父が聞かせてくれる冒険譚を聞きながら、いつか自分も西域に行ってみたいと思っていた。
そんな父が、何ものにも縛られない自由な〝風〟を父自身の生き方に重ね、それをリョウの名前にしてくれたのだということを最近になって知り、リョウはなにか誇らしい気持ちになったものだ。
リョウが長安の街からこの草原に移って来たのは、ほんの二年前、十歳のときだ。父の仲間や使用人など数家族で、小川の畔に小さな集落を成している。
そこでは遊牧民が〝ゲル〟と呼ぶテントで生活し、一部の者は季節ごとに羊やヤギを追って移動している。川の向こう岸には、遊牧民が同じようなゲル集落を作っていた。
彼らは、まだ遊牧に慣れていないリョウの家族や仲間たちをときどき手伝っていた。それは、彼らの乳製品などを唐の村で売ってもらうためであり、また、リョウの父たちが交易で得てくる織物や生活雑貨、薬品などを得るためでもあった。