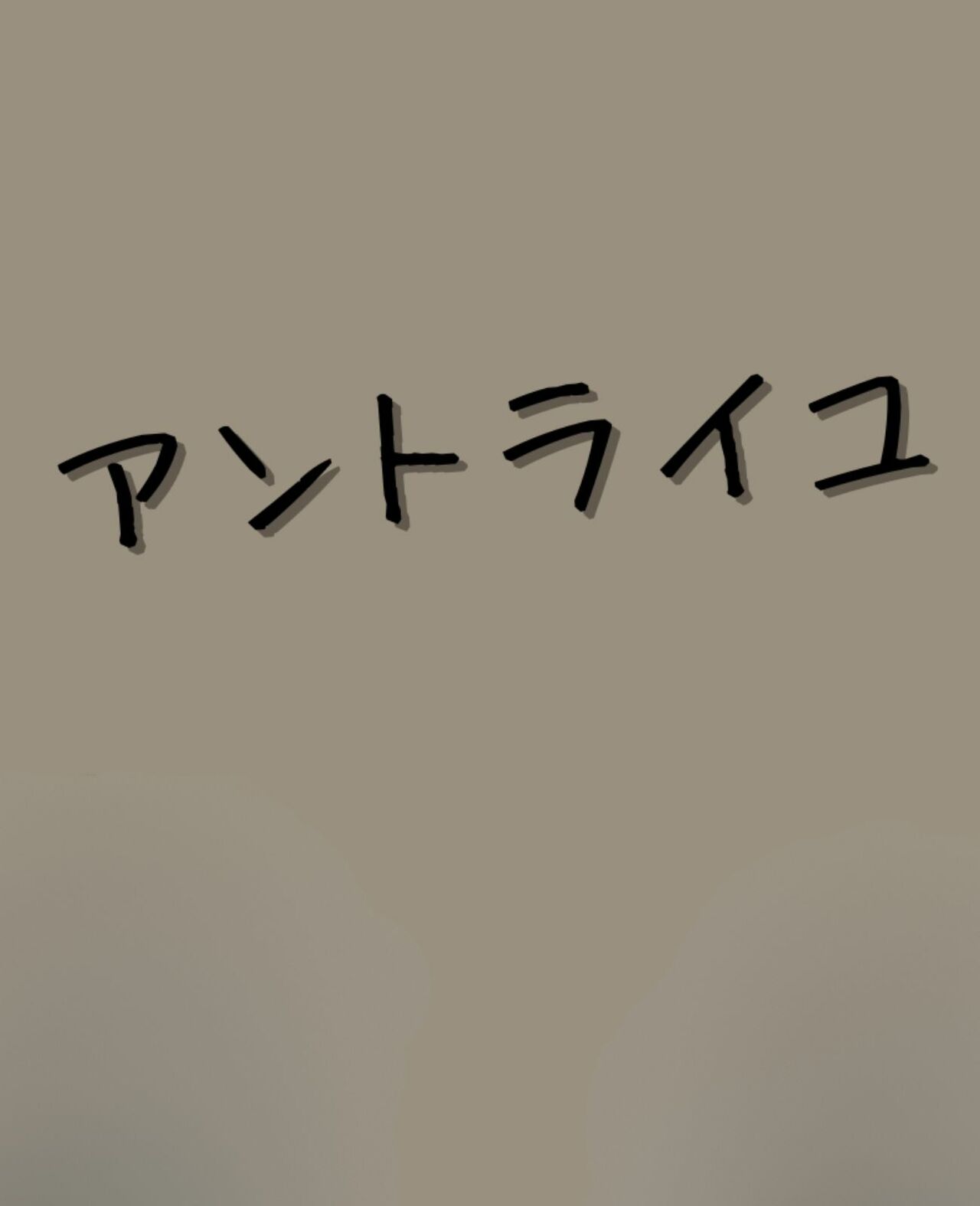【前回の記事を読む】私を真っ直ぐ見つめる彼の目は死を恐れてはいなかった。私の頭の中も心臓も黙ってくれなくて大きく視界を揺らした…
アントライユ
6
「あ」
思わず声が漏れて、千春を抱きしめた。力を込めたら崩れて、壊れてしまいそうな体を必死に優しく抱きしめた。辛い悲しみに打ち拉がれた心を、彼の服を強く握って皺を作ることで誤魔化した。
辛い。息が止まりそうな程苦しい。でも私は、ずっと言えなかったことを口にした。言いたくても、怖くて、言葉が詰まってしまって、いつも嫌な感情が邪魔をする。
「ごめんね、千春。千春、私、千春が好き。ごめんなさい。言えなくて。でも好きなの。大好き。ずっとそう。千春が隣に引っ越してきた時から、今もずっと。今もだよ」
上手く口を動かせないのは罪悪感のせいなのか、それとも拒否をされるかもしれないという恐怖心のせいなのか。視界が熱くなり、歪んだ世界が恐ろしくて思わず目を閉じた。
「好きって言ったらもう一緒に居てくれなくなる気がして、言えなかったの。ごめん。ごめん」
全身が震えて、私の感情に体は耐えられそうにない。全て投げ出して、彼と逃げ出したい。
力なんて残っていないだろうに。それでも、千春は私の頭を撫でた。指にくしゃりと雑に絡まる私の髪は、ずっと一緒に使っていたシャンプーの匂いがする。
「離れたぐない。まだ生きででよ。お願い」
言葉が乱れる程の嗚咽で呼吸がままならない。
口の端が震える。
千春はあの時の様に目を細めて笑って見せた。
私は何も考えられなくなった。感情をぶつける様に抱き締めた。
「痛い」
「ごめん。ごめん」
私は人目も憚らず、子供の様に泣きじゃくった。
その日は、千春が眠りにつくまで側に居た。