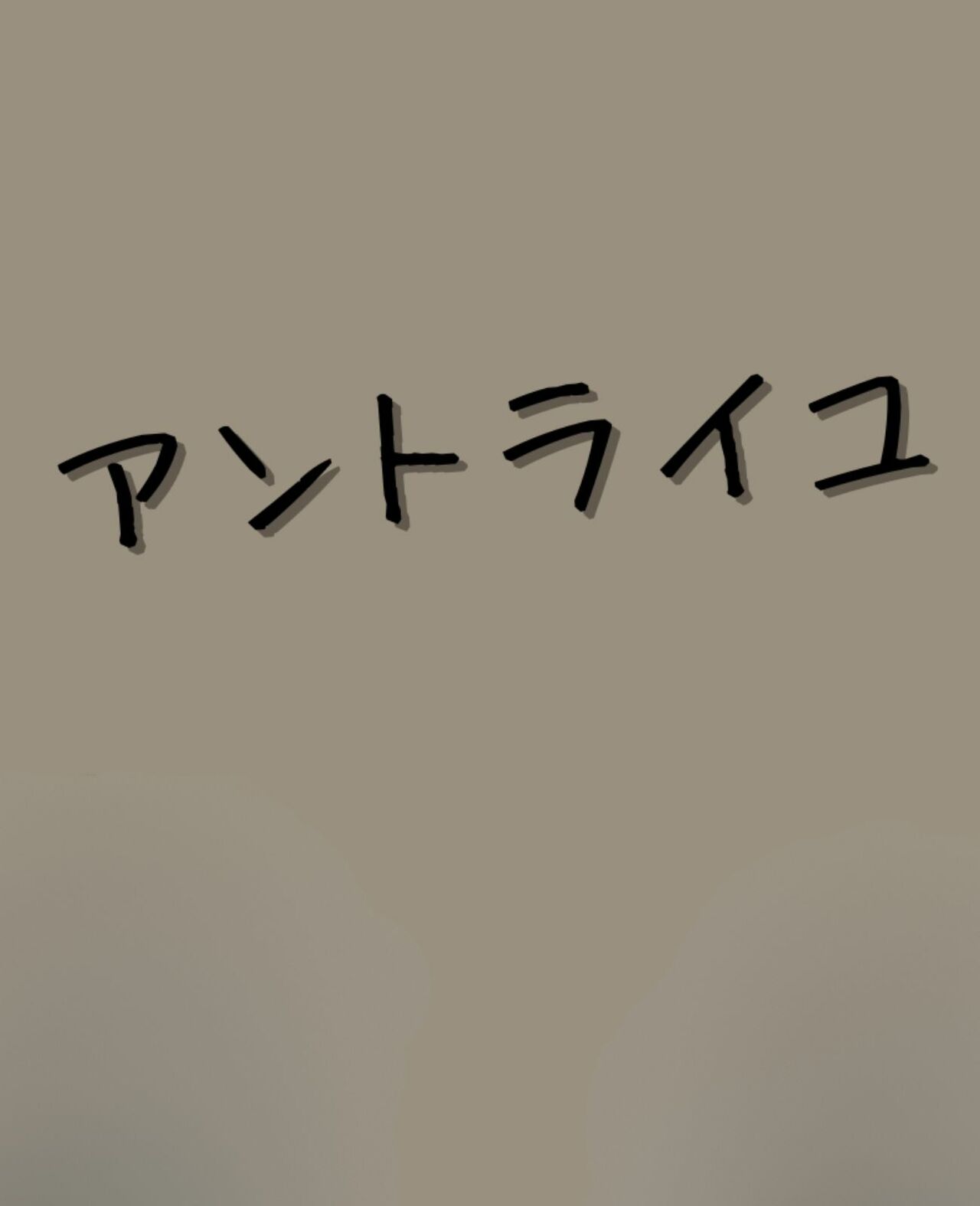千春は私と距離を詰めた。そして私の頭にタオルをかけてワシャワシャと掻き乱す。私も彼の頭にかけてある色違いのタオルで拭こうと手を伸ばした。
「千春、また黒髪増えてきたね」
「そろそろ染め直さないとな」
「何で金髪なの?」
「カッコいいから」
「え? 黒髪の方がカッコよくない?」
千春は黙ってタオルで拭く力を強くした。少し痛かったから私も負けじと力を込めた。やはり、力では男の千春には勝てない。
「いてぇ」
そう言って目を細める千春。私の心臓が体を浮かす程に高く鳴った。
「千春、笑った」
「人間なんだから笑うだろ」
「人間だったんだ」
千春はむすっと不貞腐れて目を逸らす。すぐに手を止めて私の目を真っ直ぐ見た。少しの静寂が私たちの体を覆った。
「なぁ、お前はどうして生きられる?」
「どういう意味?」
「俺たちが生きる意味あんのかなって」
「私が生きてるのは、千春がここに居るからだよ」
こんな世の中だって、千春が居れば何だって良い。
千春は私の涙袋を親指で撫でた。冷たい指先が火照った顔に丁度良い。
私はメイクが崩れている事に絶望感を覚えて逃げようとした。でも彼に腕を掴まれて引き戻された。掴まれた太ももが少し痛んだけど、いつもと違う。