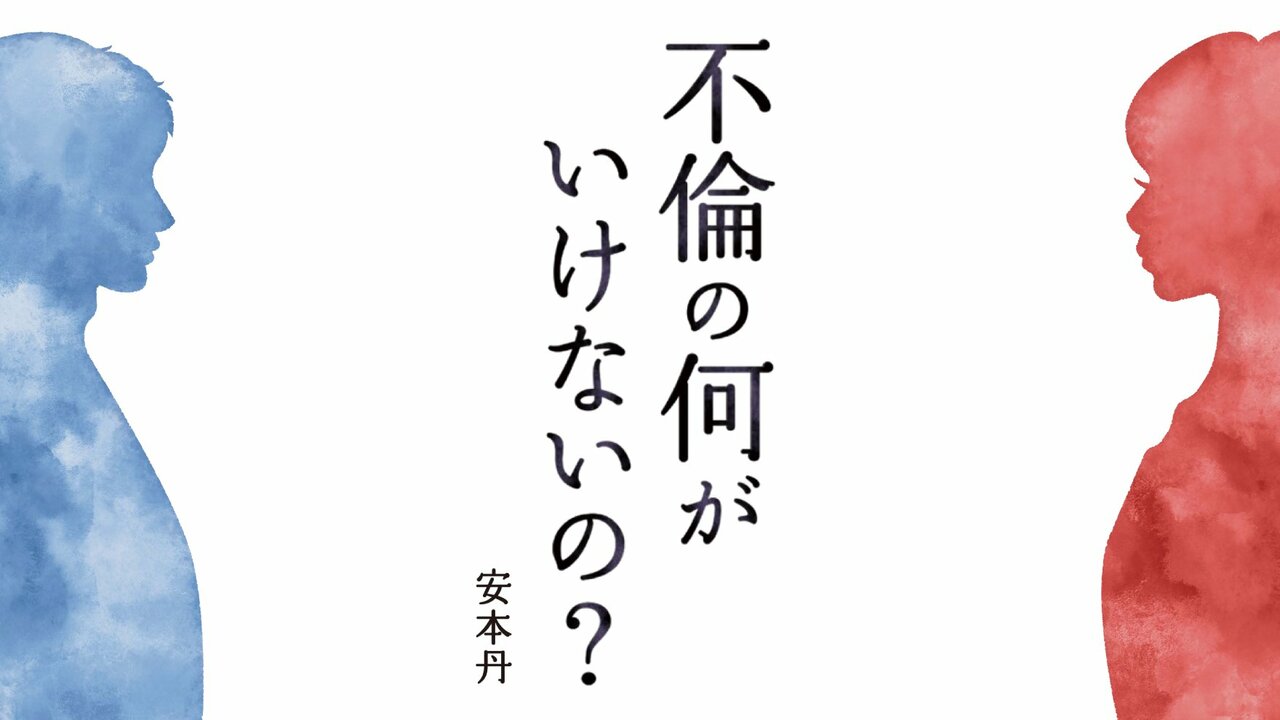プロローグ
とにかく危険みたいだからやめなさい、そう祖母に言われたとき、たまたま私も少しチャットに飽き始めていた為、ちょうど良いタイミングだと思いすんなりとやめた。
たまに思い出してやってみても、結局いつものパターンで終わるだけだ。その頃になるとネットより、現実の学校での恋愛事情が気になり始めた。
事の発端はクラスメートの仲の良い女子との何気ない会話だった。彼女は可愛らしい顔立ちと社交的な性格で、男女問わず皆から好かれていた。私が仲が良いと言えるのは彼女を含めた二、三人なのに対し、彼女は皆と仲良くしていた。
そんな彼女と、ある日の休み時間、教室でたわいもないお喋りをしていた。話の流れで私は彼女に、好きな人はいるのかと聞いた。
すると彼女はすんなりクラスメートの冴えない男子の名前を言った。なぜ彼なのかと疑問に思いつつも、人の好みは千差万別なのだと私は自分を無理矢理納得させた。
その後で、その冴えない彼がたまたま教室に入ってきた。私は彼女の肩を叩いて少しからかうように言った。
「好きって言っちゃえばー?」
そんな私の言葉を聞いていたクラスメートが会話に入ってきた。
「いやもう付き合ってるでしょ?」
私はこの時生まれて初めて『付き合う』という言葉を知った。そして同時に、その言葉の意味をなんとなく理解した。静かに頷く彼女を見て、私は自分だけが子供のようで恥ずかしくなった。
気づけばネット上では異性とあれほど和気あいあいとしていたのに、学校の男子とはほとんど会話をしなくなっていた。男女が仲良く遊べたのも低学年までで、いつしか男子と女子の間には目には見えない隔たりができていたのだ。
ゆうくん、みいちゃんと呼び合い、仲良しだった幼馴染みの男子から、突然苗字で呼ばれるようになったのはいつのことだったか。こちらが昔と変わらない調子でゆうくん、と親しげに話しかけてみると、いかにも不快そうな顔をされたのを覚えている。
それが今度はまた、男女がカップルという形で堂々と話せる年齢になったのだ。中学生になるとカップルの数もさらに増え、また彼らは露骨に目立ち始めた。無論それを見て冷やかす連中などもういない。手を繋いで帰ったり、休み時間の度に廊下で戯れ合ったりする彼らを、私は嫉妬と羨望の眼差しで見つめていた。