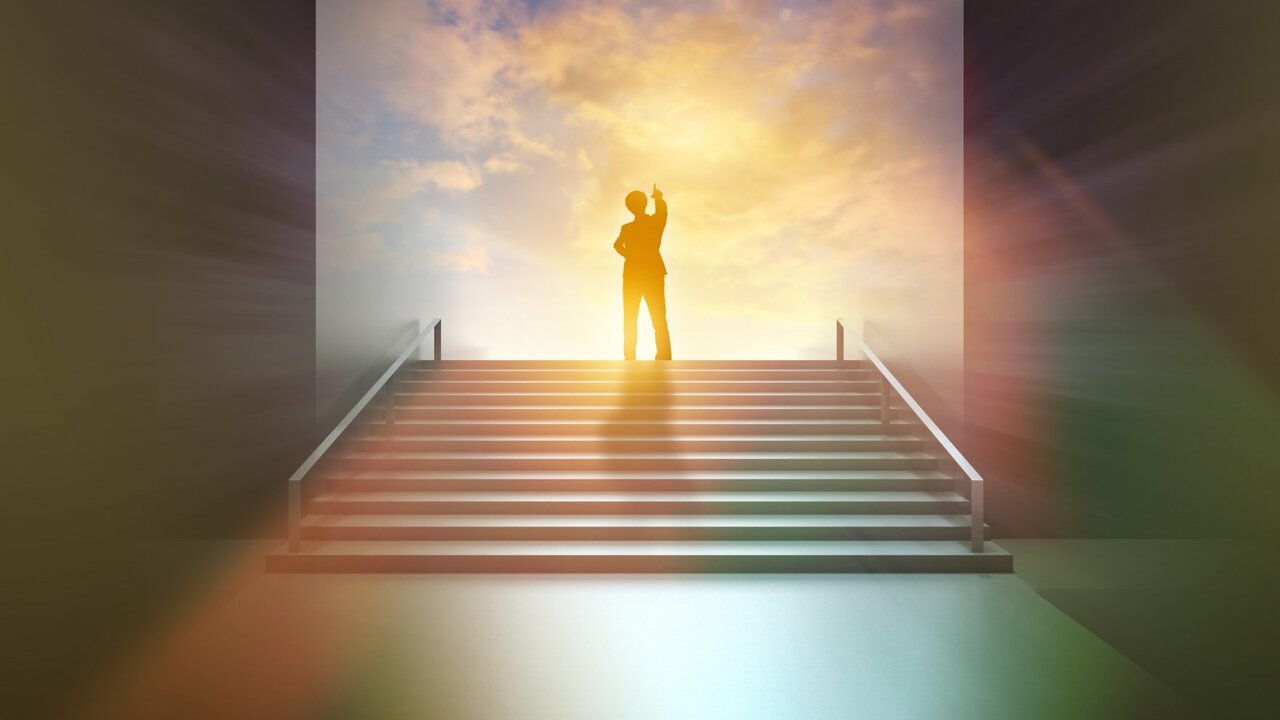第一章 恭やん
過正失神
数日後に豆腐屋の主人が恭平の父元泉を訪ねてきた。名医と評判の高い元泉に敬意を表して、安吉と寺のごたごたに恭平を巻き込んで申し訳ない、と筋違いの詫びを入れてきたのである。恭平から話を聞いていた元泉は苦笑いするしかなかった。
元泉は医療技術が優れているだけでなく、医は仁術の言葉通り、貴賤貧富の別なく施術するので評判だった。ある貧しい修験者の病を治した時には、薬礼を取らないばかりか、養生せよと食糧まで与えた。その翌年の暮れ、馬越家の玄関に大きな雉(きじ)が置かれていた。正月のご馳走に、と修験者からの手紙が添えられており、その慣例は終生続いた。
しかし、この治療方針では忙しいばかりで金にならない。しかも元泉は多趣味で、剣術や弓術に凝り、一方では生花にも手を出した。しかも大酒家である。医家とはいえ貧乏暮らしが続いた。
嘉永四(一八五一)年、七歳になった恭平は窪家を継ぐための第一歩として漢学塾に通い始めた。師は、後に渋澤栄一の推薦で一橋慶喜に経書を講義する阪谷朗廬(さかたにろうろ)である。備中出身の朗廬は七歳で大坂の大塩平八郎に陽明学を学び、十歳で上京して儒学を修めた。嘉永四年、二十九歳で木之子村の隣の芳井村で桜渓(さくらだに)塾を開き、二年後に郷校興譲館に招かれて初代館長となった。漢学者のくせに開国論を説き、各地から教えを乞う者が多数訪れる西国屈指の論客であった。
恭平は桜渓塾から興譲館まで六年間、朗廬に学んだ。しかし、負けずの恭やんである。じっと座って勉強するなど性に合わない。周囲とつまらないことで喧嘩を始める。相変わらず小柄だが、機敏に立ち回って殴り合いも辞さない。どんなことでも自分が正しいと信じて曲げないので、小さな喧嘩も大きくなってしまうのである。
ある日、たまりかねた朗廬は恭平を呼び、目の前で「過正失神」と書いて見せた。
「正しさも過ぎると、己の精神を失う、という意味だ。分かるか」
朗廬は子供にも常に真剣に接していた。この時も恭平の前にぴたりと正座している。師の顔が迫ってくる。黒目がちの小さな眼で真っ直ぐに正面から見つめられ、恭平は動けなくなった。正座した膝の上で、小さな拳が震えている。
「あの、ちいと分かりません」
「そうか。では教えよう。まず、正しいことは大切だ。だが、正しいからといって、相手を打ち負かしてよい、ということではない。ここが肝心だ。お前は激しやすい。激すれば、正しさより、相手を打ち負かすことに気持ちが移る。そこが間違いだ。打ち負かしたいという気持ちは慎まねばならぬ。分かったな」
「はい。ようけ分かりました」
恭平は自分が強情を張っていることが分かっていた。一歳違いの兄は優秀である。身体も大きく気も優しく、恭平は何一つ敵わないと思い続けてきた。幼い弟は素直で可愛らしく、優等生の片鱗を見せていた。父は間違いなく二人を愛していた。だが、父が二人を見る目と自分を見る目は違っているように感じられ た。学業が劣るからか。窪家に行く人間だからか。疑念は尽きることなく、恭平はいつもいらいらしていた。その不安を吹き飛ばすためには、強情と言われても自己主張するしかなかった。