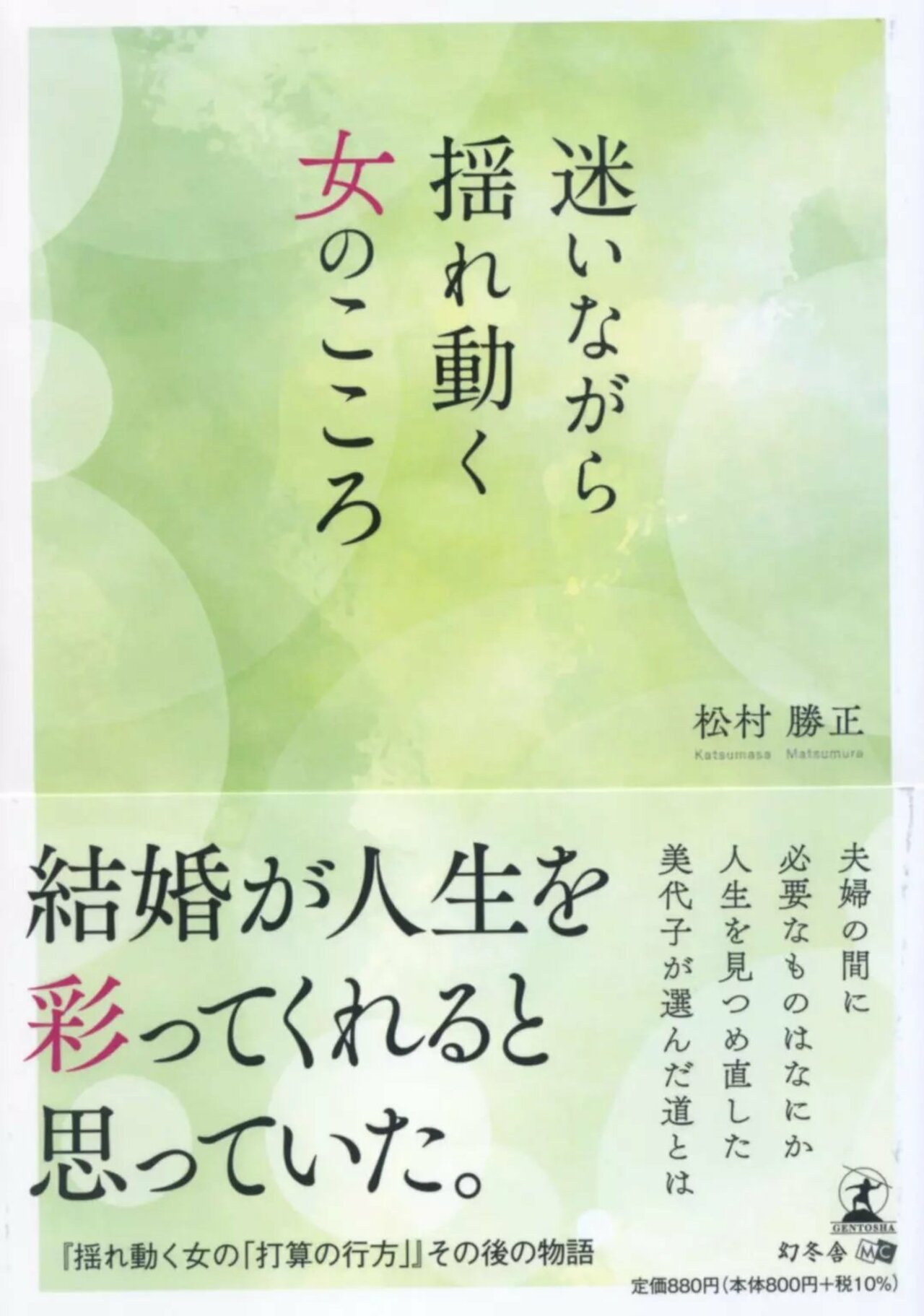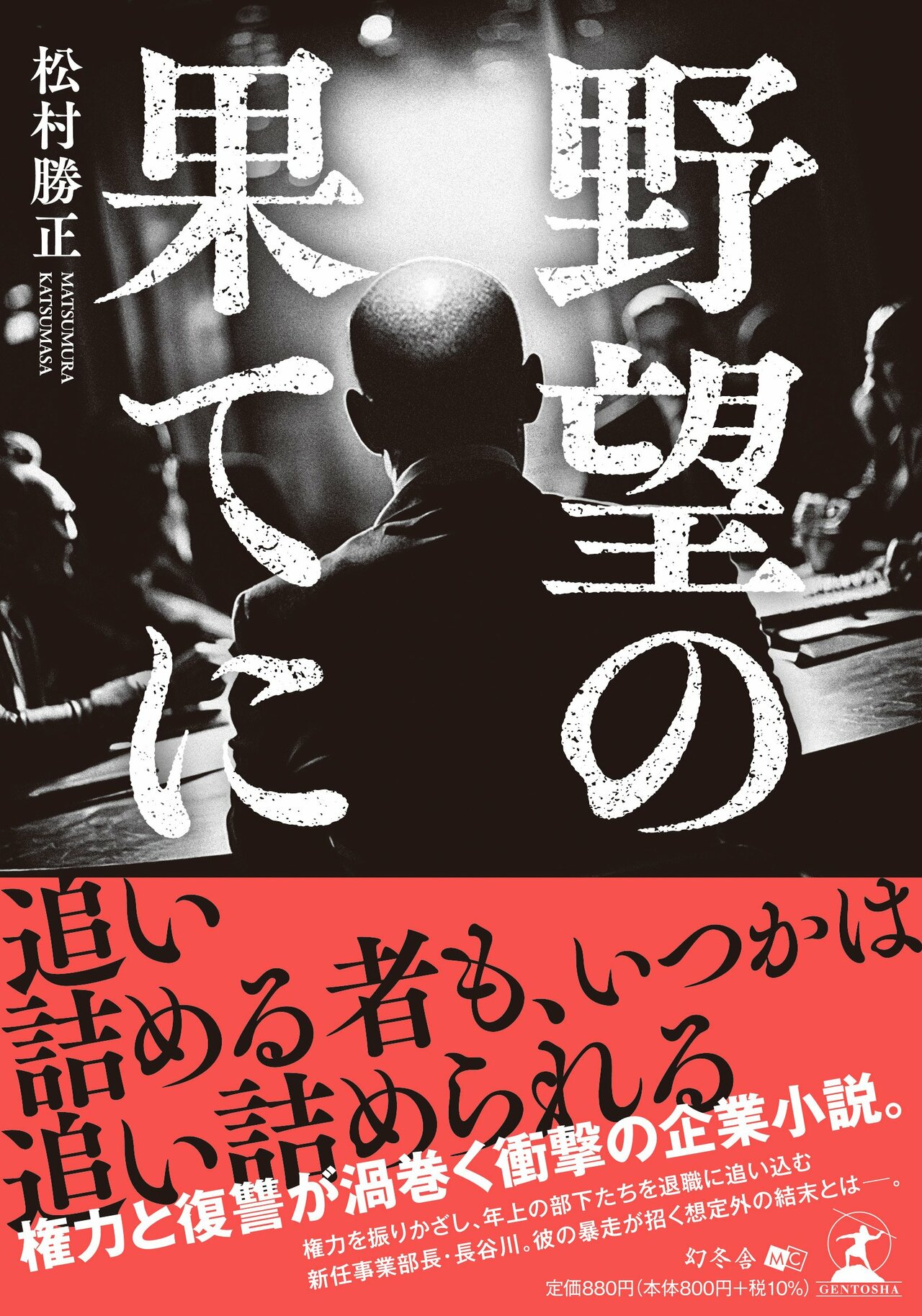「外部の人との往来は無いのですか?」
「今はパソコンさえあれば、外出しなくとも仕事が完結するようですよ」
「ずいぶんと孤独な仕事ですね。精神力が強くないとダメですね。何か学生の時にスポーツでもやっておられたのかしら」
美代子はそこまで探りを入れられると、これ以上主人の病気のことを触れないで済ませないと思った。
「実はね、主人は下半身が麻痺していて、車いすの生活なのです。先ほど指摘されたスポーツ、ラグビーをやっていて事故に遭ったのです。大学四年の時でしたから、就職も他の人たちと同じような勤務が出来ず、在宅で出来る仕事を選んだようです。お父様が健在なときは地元で手広く不動産業を営んでおり、父親が残してくれた資産で食いつないでいます」
「ごめんなさいね。つらいことを言わせてしまって」
「構わないですよ。私は障害を持っていることを承知で結婚しましたから。でも何もしないのですよ。ベテランの家政婦さんが家庭内のこと、夫の入浴介助からリハビリまで全てやってくれますので、私は自由な身なのです」
何の屈託もなく、すらすらと話してくれたことに陽子は少しあっけに取られていた。陽子には到底出来ないかも、ということがすぐ脳裏を駆け巡った。
「美代子さん立派ね。結婚の相手が障害を持っていることを承知で承諾されたのでしょう。どのような生活を夢見ておられたのかしら。あなたほどの容姿なら、引く手あまただったろうに。私には決断出来ない」
「私は、二十九歳の時に恋愛に失敗しているの。それがトラウマになっており、結婚願望が消えうせたの」
「トラウマとは?」