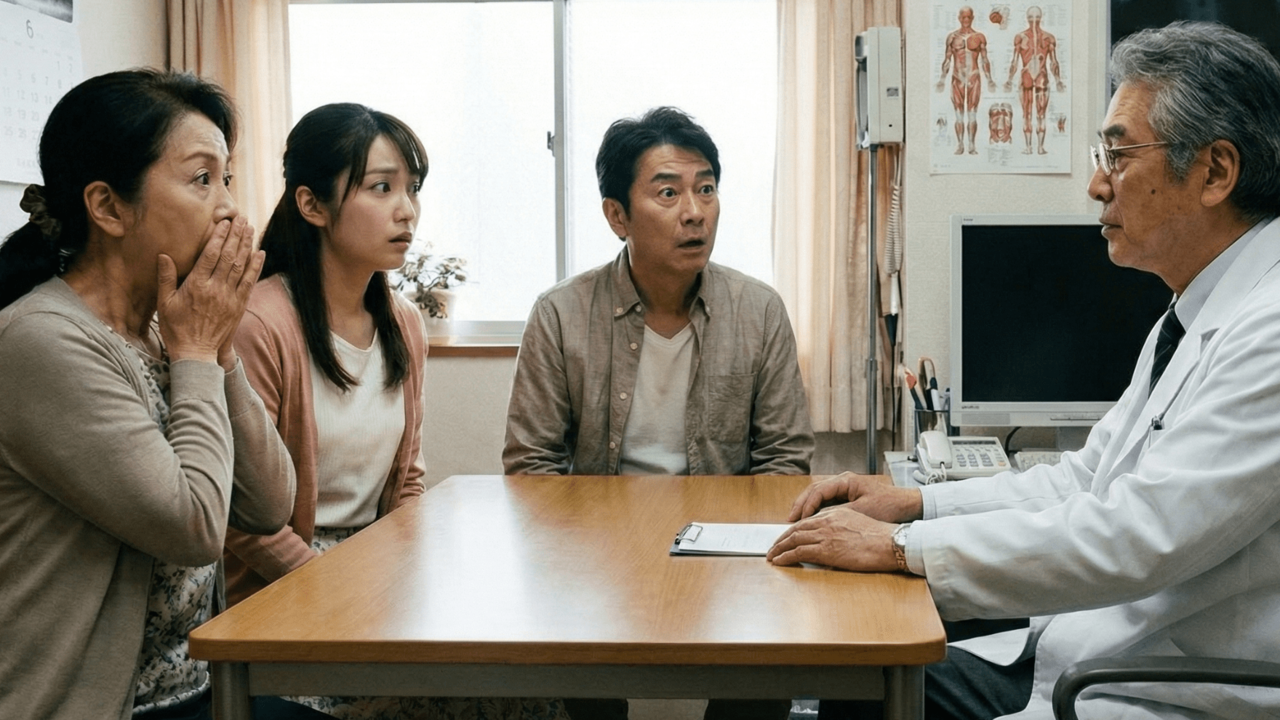午後になると師長が来られ、
「私たちは看護ステーションで計器を見ていますから、ご家族の方はそばにいてあげてください」
と声をかけてくださいました。
『最後の最期の別れのひとときを家族で』とのご配慮なのでしょう。とてもうれしく思いました。私と婿は、ただ黙っていつもと変わらない夫の寝顔を見つめておりました。
わが家の療養室にいるかと錯覚してしまいそうです。時は静かに静かに流れて行きます。
その時いきなり入口のドアが開いて、息せききって夫の大好きな訪問看護師の神石さんが入って来られました。どなたかが今の堀内の状態を教えてくださったようです。
「わあ、お父さん、あなたの大、大好きな神石さんが来てくださったのよ」
私は思わず大声で言いました。どんなにつらかろうが、彼女にはにっこりと笑顔を送る夫なので、(お願い。目を覚まして!)とひたすら心の中で大声をあげていました。
そしてその大、大好きな神石さんがしっかりと夫の手を握ってくださいました。
私は心の中でぱっちりと目を開け、片ほほでにんまり笑う夫の顔を描き、奇跡の起こることをひたすら祈っておりました。
沈黙のひとときは過ぎてゆきます。静かに、そして静かに。
ただ、今までキーパーソンとして《お父さん・命》として昼夜を分かたず仕事の時間の合間に(いや仕事を放り出してといったほうが正解かな?)飛び廻ってきた娘は、ともりゆく命の灯をしっかりと捕まえて引き戻せたらとのほのかな思いからか、どこまでも届けと言わんばかりに声を限りに叫んでおりました。