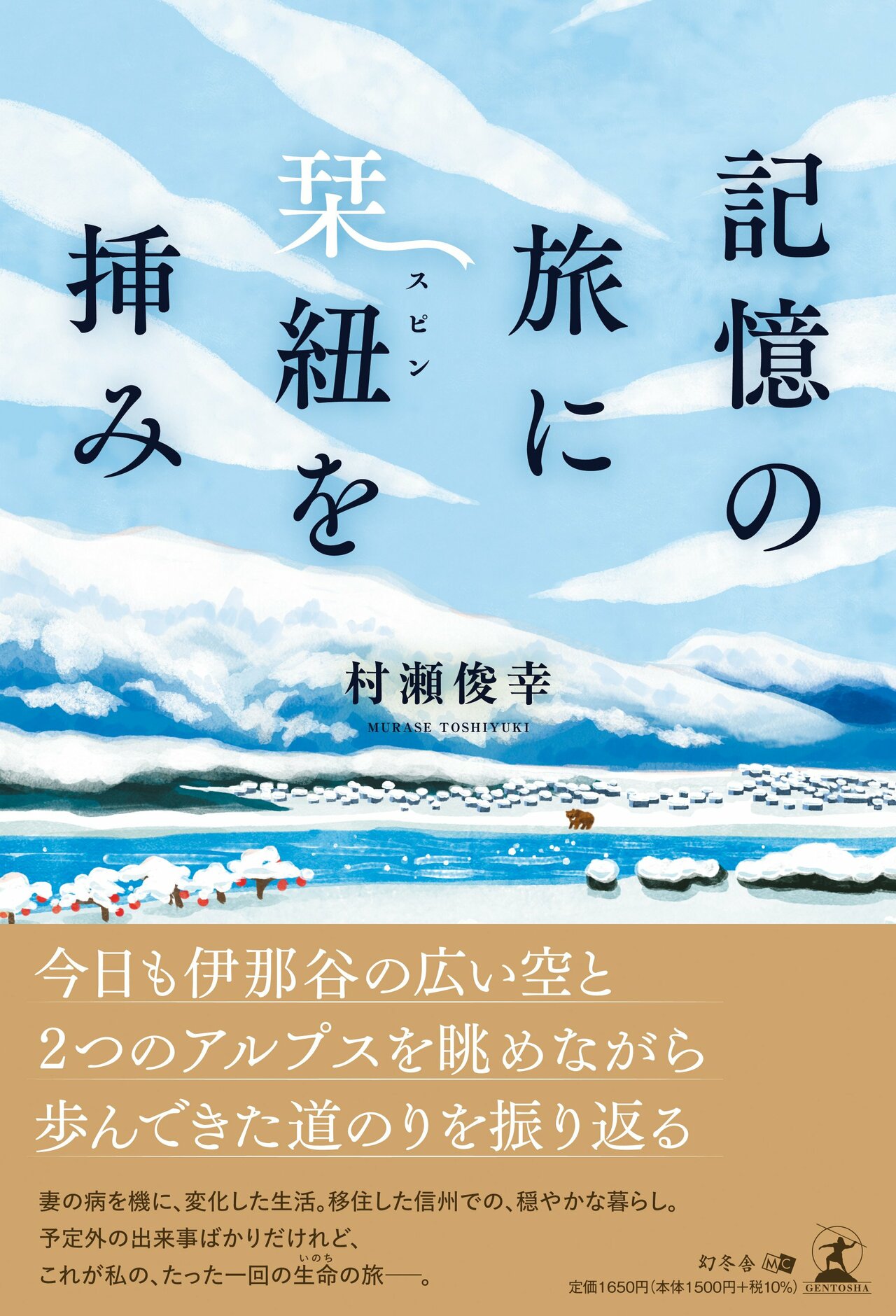第3章 私が知っている私のこと
夫として、父として家族の知らない出来事
児童養護施設は、保護者のいない子どもたちや、それぞれの事情で養護を必要としている子どもたちと一緒に生活をするところです。職員は保母(保育士)も男性職員(児童指導員)も住み込みでした。
結婚してからは宿直明けに帰宅することができましたが、私にとっては二重生活のような状態でした。
施設の子どもたちとの生活はもちろん大変なこともありましたが、楽しかったことも数え切れません。市内の養護施設が集う野球大会での優勝をめざして暗くなるまで練習したこと、海の家では中学生とキス釣りをして宿の庭で火をおこし焼いて食べたこと、みんなで出かけたキャンプでも楽しかったことしか思い出せません。
そういえば子どもたちが学校で問題をおこし、保護者面談に呼び出されたこともありました。中学生がグループで施設を逃げ出し他県の警察から保護していると連絡があり、迎えに行ったことも思い出しました。
そんなことがあっても私はその子らを我が子と同じように心配し、親身になって育てようとしていました。手がかかることを含めたら、我が子以上だったかもしれません。
8年ほど働いたある日、職員の部屋に幼い男の子が緊張した表情で、飛び込むように走りこんできました。
「お兄ちゃんがね。あのね。唇に色つけて、変な顔をしていてね。怖いから来て」
業務記録をつけていた私にちょっと怒ったような表情で訴えます。早く何とかしてほしいと一所懸命です。その子の言うお兄ちゃんというのは、いつもやんちゃばかりしている中学生のことだとすぐ分かりました。小さい子ばかり虐(いじ)めて困ったものだと思いながら、訴えてきた子の肩に両手を置いて言いました。
「後で叱っておくね」
「だめ。それじゃだめ。今すぐ来て。いっしょに来て」その子は眼を大きく開いて、ますます真剣です。
「じゃあ、これが終わったらすぐ行こうね」
私は、事務仕事を気にしながら答えました。
「だめ、今。今すぐ」