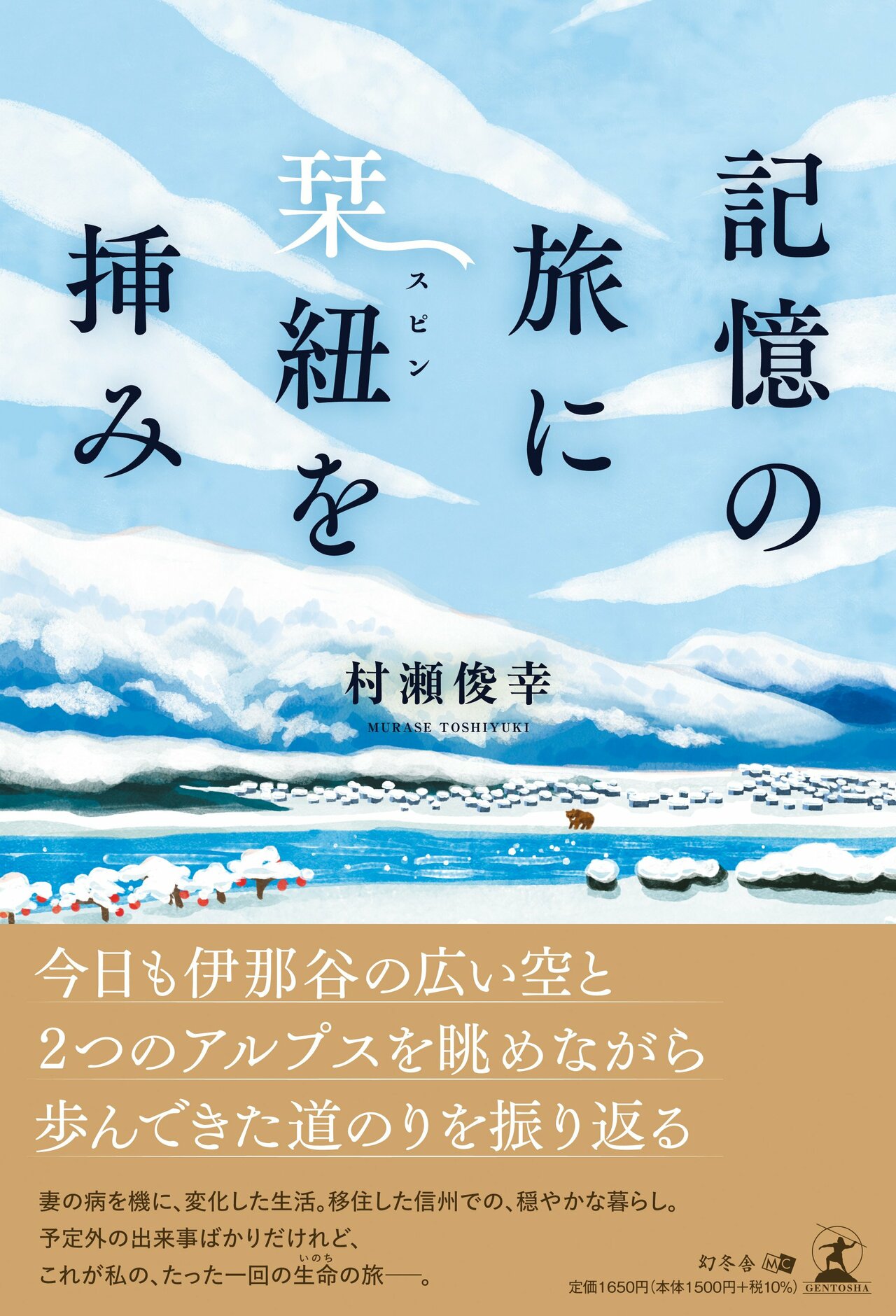第3章 私が知っている私のこと
夫として、父として家族の知らない出来事
私は心配どころか、この子の息が止まったらどうしようと恐怖でした。
寮長は救急車の手配をするため職員室に走り、私はお兄ちゃんを抱きかかえ救急車が着くだろう玄関先に向かいました。
抱きかかえると、彼の腕の皮膚はざらざらしていました。生気が全く感じられません。人の肌とは思えない感触に、一刻を争う事態だと分かりました。お兄ちゃんの意識も薄れていき、それでも、ただ生きようとする呼吸だけが続いていました。ぐったりとした人間はこんなに重いのかという感覚が、私の腕から消えることはありません。
お兄ちゃんは救急車で救急病院に搬送され、私も一緒に向かいました。私は集中治療室の前の長椅子で、ただ時間が過ぎていくのを見守っているしかありませんでした。
かなりの時間が過ぎて病院の方から一命を取りとめたと聞かされた時は、ただ涙が流れるばかりでした。そんな私に病院の方は、数日間はまだ危険な状態が続くと念を押しました。
その同じ頃、施設では警察の事情聴取や管轄する市役所民生局との対応で大混乱だったそうです。
この子の自殺未遂で、私はこの職を続ける資格がないと深刻に悩みました。それからずっと、自分を追い込む生活が続きました。自殺未遂の原因に、私たち職員が何も関係ないとは言えません。いやそんな曖昧なことではなく、私自身に責任がなかったとはどうしても思えなかったのです。
この子は幼児から中学生になるまで、ずっと児童養護施設育ちでした。私がこの職に就いた頃は、小学校低学年でした。今まで私が、この子にしてきたことは何だったのでしょう。この子のすべてを、受け止めてきたのでしょうか。