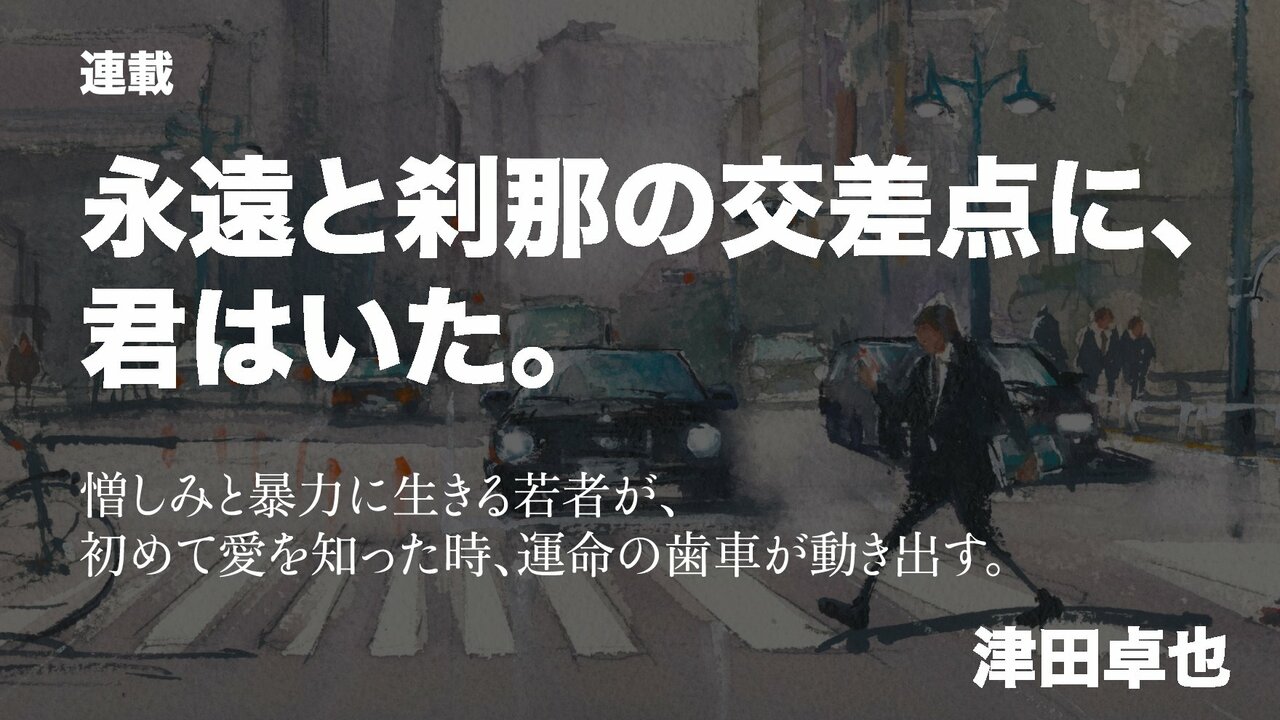第一章
7
少し前屈みになりながら、今日子はひたすら前に向かって歩いていた。あまり長いあいだ歩き続けると、足を引きずるように歩き、場所を選ばず立ち止まる。それから、また歩き出す。先ほどと同じぎこちなさで。
最近になって、今日子は急激に痩せた。食欲がなく、食べるものも流動食のようなものばかり。腹部の膨張感のためよく眠れないことも多い。
朝目覚めると、しばらくぼぉーっとして、病人のように体を動かし、涙を拭った。心のなかに重く冷たい石があるようだった。何かが起こっているのはわかっていたが、それが何なのかはわからなかった。
昼過ぎだというのに電車内は混んでいた。たまたま空いた座席に今日子は腰掛けた。そして物思いに耽った。一種の放心状態。一つの言葉に、脳が引っかかり、重力にひっぱられるように、体も心も暗い穴に落ちていく。
今朝、バイト先の寿司屋に、「体調がすぐれない」と伝え、病院に行った。妊娠ではなかった。医者からは、「痛みの原因がわからないので、再度、精密検査をしましょう」と言われた。
少しほっとはしたが、なんだか残念なような気もした。もし妊娠していたら、河合はどう言うだろう。聞いてみたかった。答えは決まっているけれども、それでも聞いてみたかった。
妻子がいることは最初からわかっていた。いままでは気にもならなかった。たまたま好きになった男が結婚していただけだと思っていた。
それなのに、なぜこんなにも苦しい。結局のところ、河合が結婚しているのが、気に入らないのか。確かに家庭を持つ男との恋愛には不自由もある。土日には基本的に会えないし、お盆や正月にデートするのも難しい。メールのやり取りはできても、今日子から電話をかけることはできなかった。
会えるのは、平日の数時間、あるいは稽古の終わった終電までのわずかな時間だけだ。それでも、今日子は河合に夢中だった。河合と会っている時間は今日子にとって夢の時間だった。
河合の微笑みが、声が、しぐさが、体が、今日子を縛りつけて離さない。それは理屈ではない。心が、体が、細胞が河合を求める。河合のことを思う時、今日子は、運命という言葉を頭に描く。いままでそんな言葉を信じたこともなかったというのに。
妻とはいずれ別れる。その言葉を聞かなくなってどれくらいになるだろう。不安になった今日子は河合に尋ねた。
「私たちの出会いって運命だと思う?」
「思うよ」と河合は答えた。