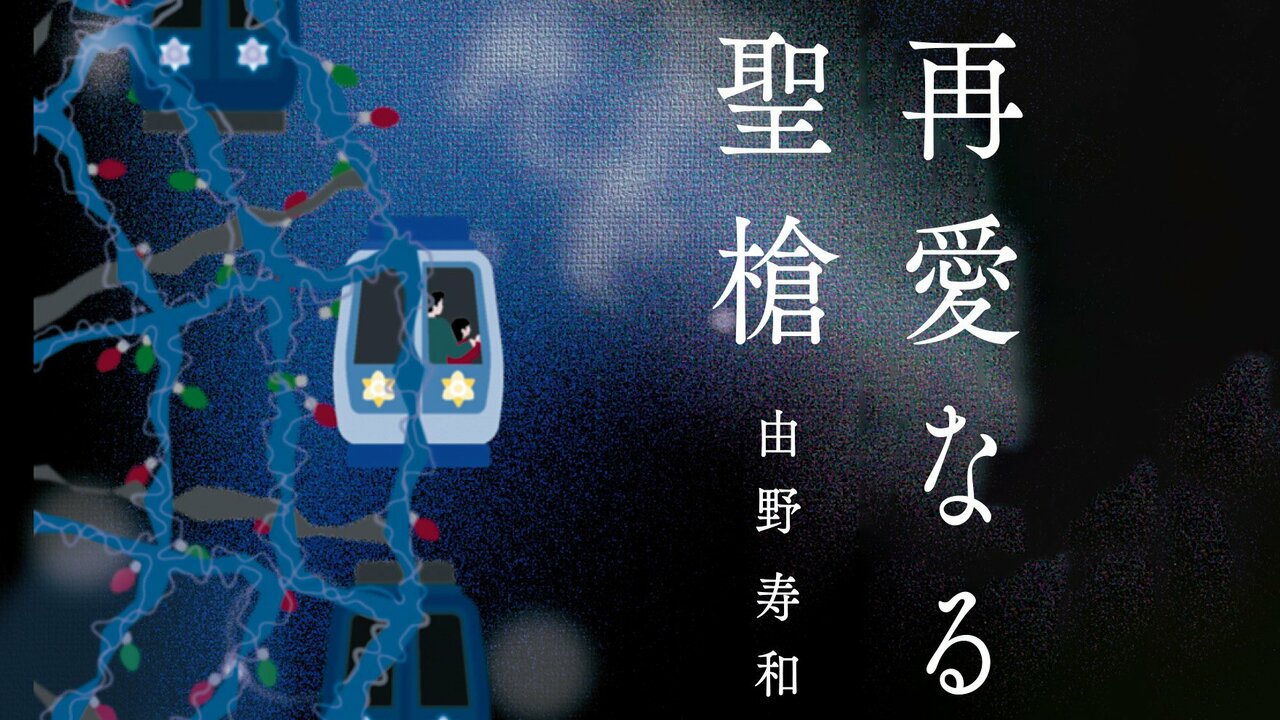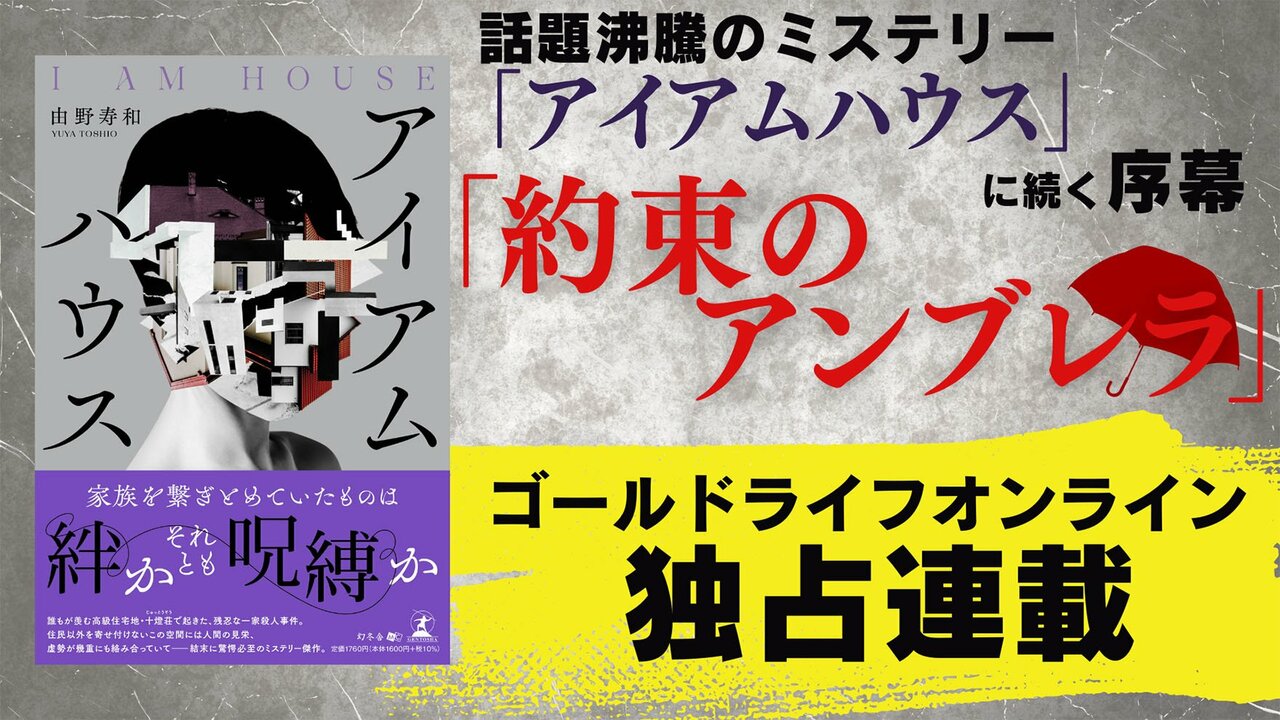五 午後……十二時四十分 ドリームランド内社員食堂
そこで貝崎は、白い紙を茶封筒から取り出してテーブルの上に置いた。
「これ、シフト表ですか? 私の?」
「そうです。この表を見る限り、今日は休憩一時間以外、一日中ずっとドリームアイのゲートにいることになっていますね。この勤務体系じゃあ、一日に数百人を誘導する日もあるんじゃないですか?大変ご苦労な仕事だ。この一件が終わったら会社を労働基準法違反で訴えるといい」
「それは別に……やりがいのある仕事ですから」
「それにしても、たくさんの乗客の中からよくその人のことを覚えていましたね。ほんの一瞬しか接触がないわけでしょう? 元々知っていたんじゃないですか?」
「えっ、初対面ですよ」
「しかし、それなら余計にわからない。なぜ一度会っただけの人間の言葉を信用してるのかが。そのせいであなた自身の信用が崩れそうになっているんですよ?」
「それは……その人が印象に残っていたからです、とても雰囲気のいいお父さんとお子さんでしたし」
滝口は、今度は快活な口調で答えた。
「親子だったんですか」
「そうです。お話ししてみて、信用できる雰囲気でした。それだけです」
「どんなやり取りがあったんですか?」
「私から声をかけさせてもらう前に、ちょうどジュースを溢(こぼ)しちゃって。それで、後ろにいらっしゃったお客様に謝っていらっしゃいました。かけられた方も特に怒っていなくて、クリスマスらしい光景でいいなって思ったんです。そこでゴンドラの順番が来たんですが、ちょうどシルバーゴンドラだったので、申込時に高齢者とわかっている方はそれに乗れるとお話ししまて……」
「つまりそれが亡くなった老人か。転落したゴンドラに乗るはずだったその親子が、観覧車ジャックの証言者というわけだ」
「そうなりますね……」