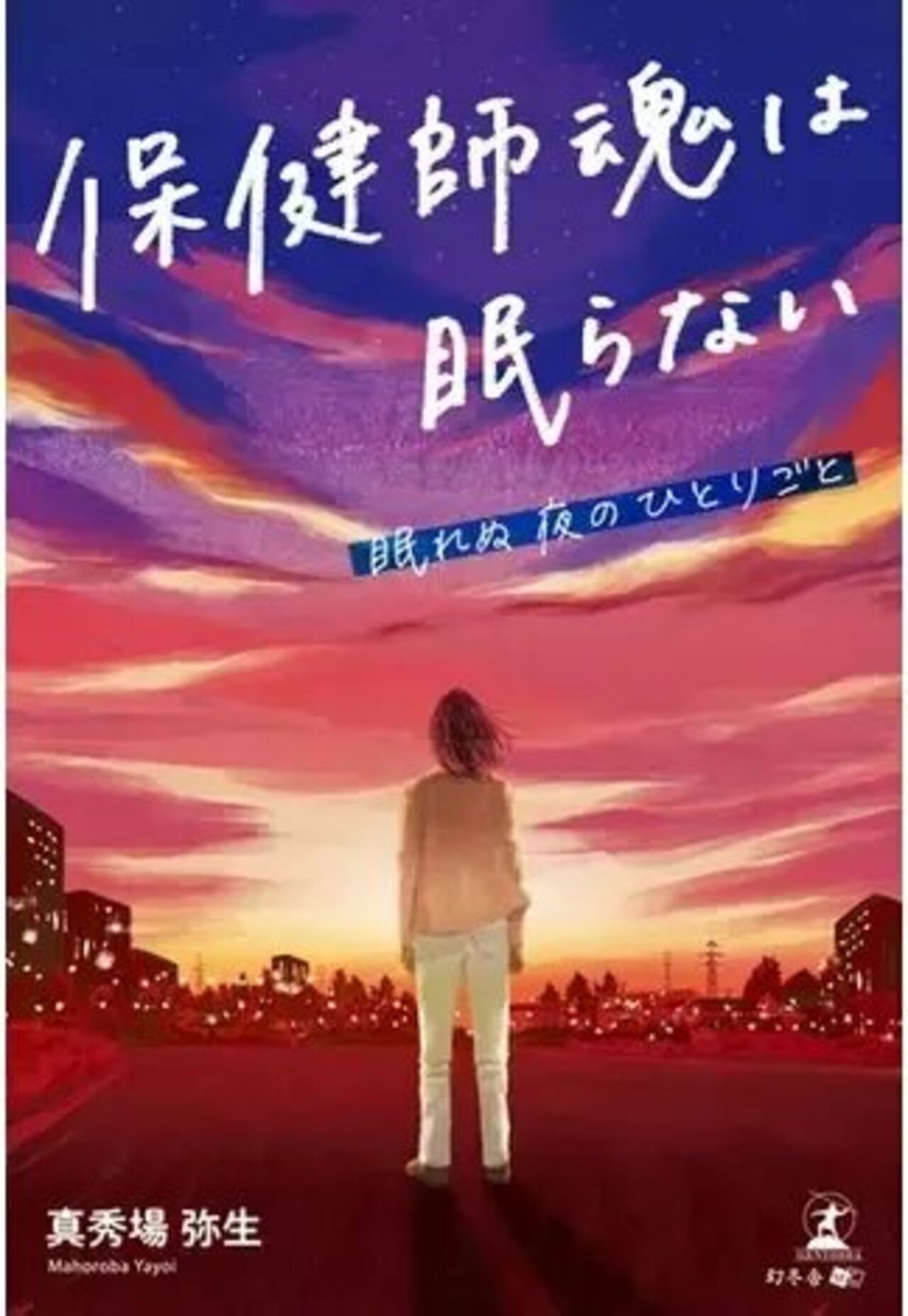再起への兆し
そもそも誰に言われなくても自分の不甲斐なさを自分自身が何より痛感している。けれど、「こうとしか生きようがなかった」というのが私の率直な思いなのだ。来し方を振り返れば振り返るほど、保健師は私にとっては天職だと思えてならない。公職から退いた今も、ふと気が付くと「保健師活動」のこと、「公衆衛生活動」のことを考えていることに驚く。
保健師のDNAは、保健師を辞めてなお私の中で生き続けているのだ。
なりわい
かつて、大学病院の病棟看護師であった頃、私の所属病棟は主には循環器の病棟であったが、その頃にはまだ珍しい病気であった「がんや白血病」などの他、雑多な疾病をすべて受け入れる総合内科的な病棟だった。
私は、いわゆる「あたる」看護師だった。つまり患者さんの最期を看取ることが多い(?)看護師だ。
その頃の勤務体制は3交代制だった。
日勤が終わる時、「この病状では、おそらく準夜帯で亡くなるから、私が今夜、深夜帯にやってきた頃にはもう会えないな」と思う患者さんは、必ずと言っていいほど私の深夜勤務中に看取らせていただく、そんな看護師だった。
その病棟には、脳梗塞の再発、心筋梗塞の再発、糖尿病の悪化による透析者など、生活習慣病の再燃、再発による入院患者が多かった。動脈硬化系の疾患の再発で入院する患者さんの多くは40代以降の男性で、残される遺族はまだ未成年の子ども連れの母親が多かった。
看取りの際の「なぜ私たちを残して逝ってしまうの」と泣き叫んで取りすがる遺族の姿、悲痛な叫び声。その場に立ち会う度に、私はいつも恐ろしいほどの無力感に苛まれた。
だからいつも「自分の生活さえ改善すればこんなことにはならなかったのに。そんな簡単なことすら努力できないから、最愛の家族とも別れ、家族を悲しみと絶望のどん底に突き落とすことになるんだ」と目の前の亡くなった患者さんを心の中で責めた。そうすることで自分自身の無力感、不甲斐無さをごまかしていた。
けれど、そんな残酷で無情な場面が何度も何度も目の前で繰り返され、その度に蓄積される自分自身の無力感が限界に達した時、「予防活動に身を投じよう」と決めた。