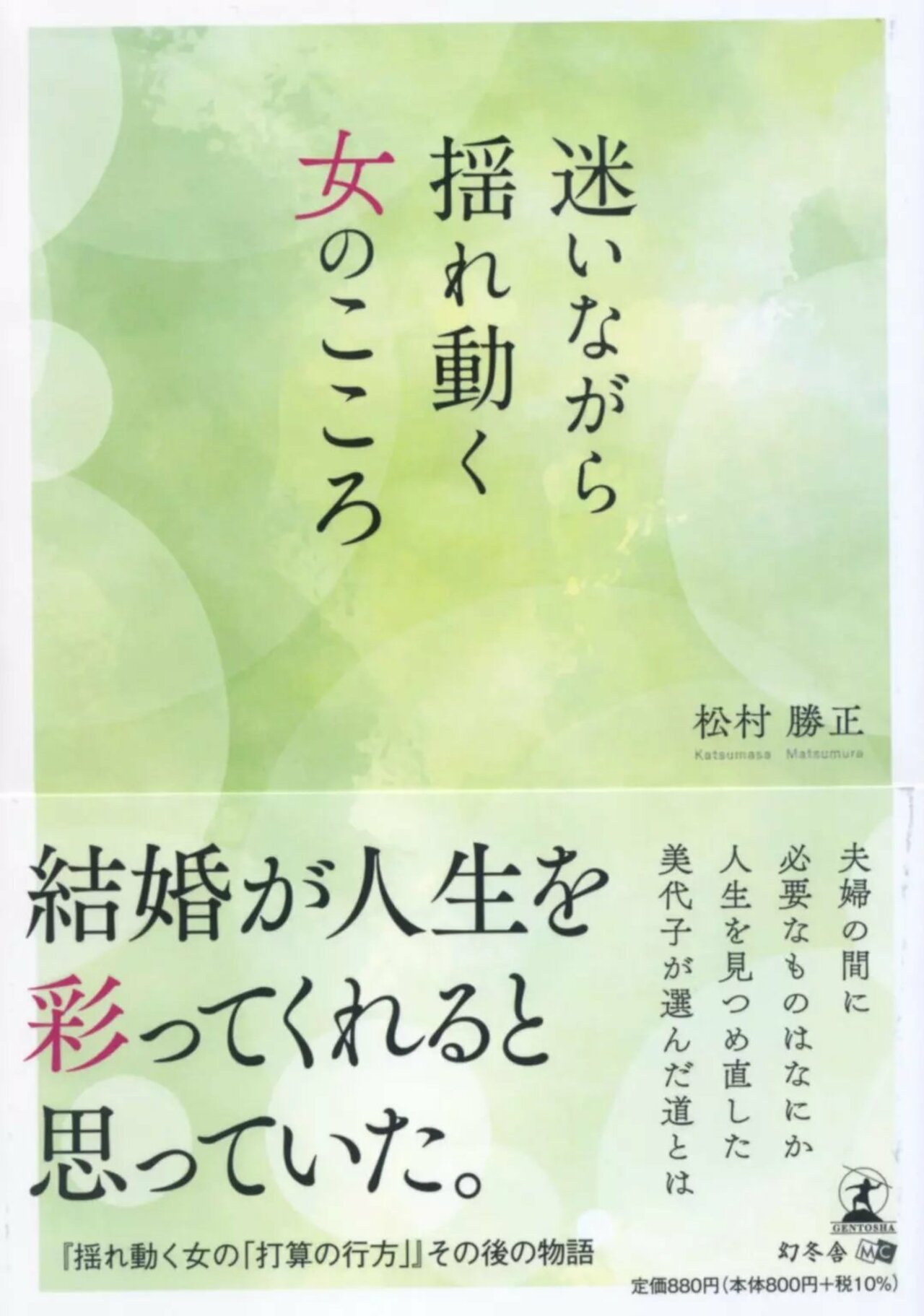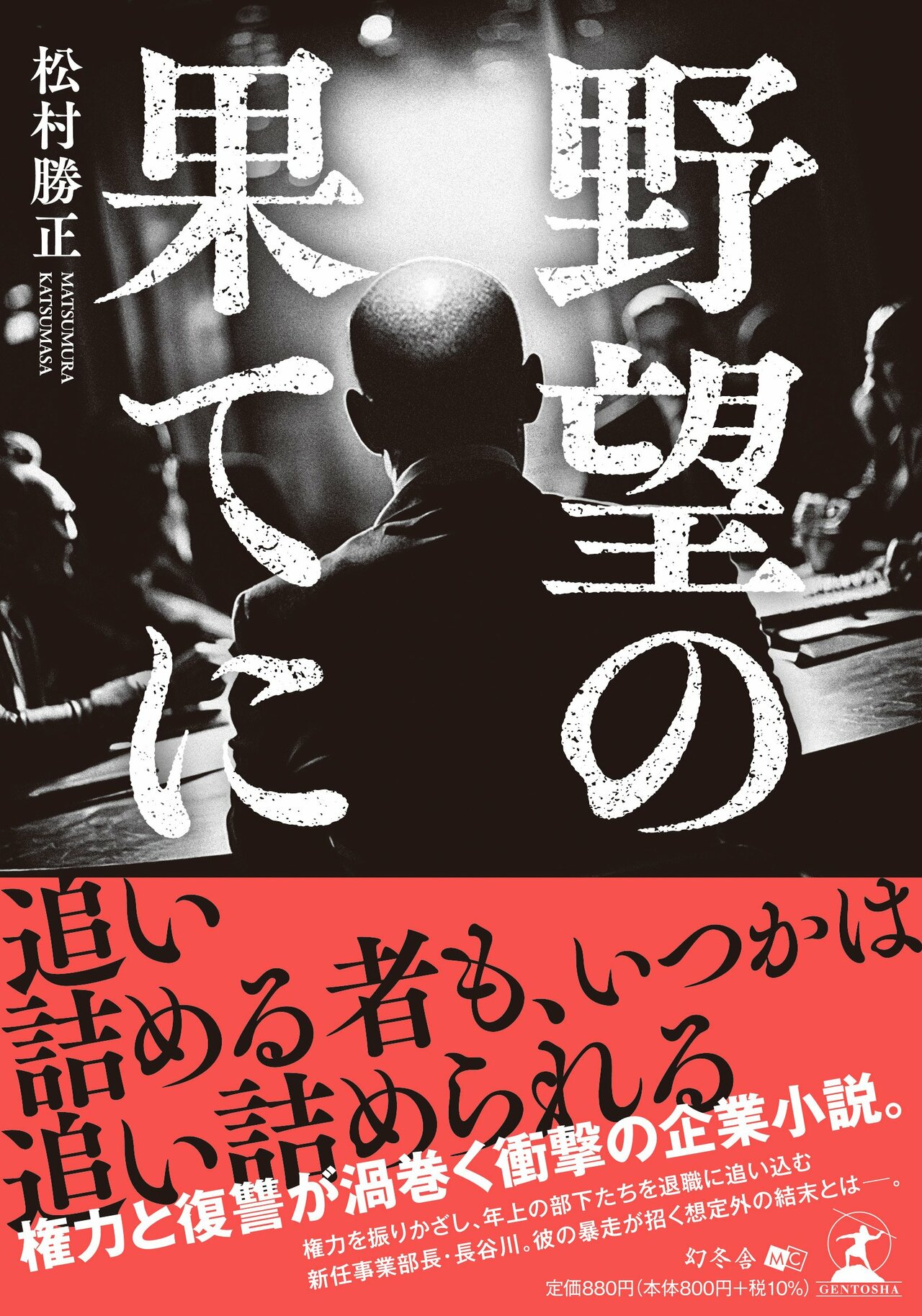「とっくに四十は過ぎてますよ、からかわないでください」
「美月さんは小柄だから私なんかより、若く見えますよ」
「何をたわいもない話をしているんだね、どちらも五十歩百歩だよ。今日のすき焼きのお肉美味しかったよ。特売日でワンランク上の肉を買って来たんだね。やはり物の価値はお金で決まるね」
「悠真さん、良いとこに気が付きましたね、女の価値もお金で決まるの。そうでしょう、美月さん」
「同感です」
美代子は椅子から立ち上がろうとしたとき、食後のすき焼きの匂いが部屋中に籠ったのを感じ取って「美月さん換気扇をしばらくの間、強にしておくといいわ」
「そうですね、私は鈍感だから」
「でも美味しかった。ごちそうさまでした」と満足そうな表情で美代子は食卓を後にした。
自室に戻った美代子は庭に面した窓のカーテンを閉めながら、夏の間に成長した枝を見て、手入れの時期をいつにするか考えていた。
暗くなった部屋のデスク上のスタンドの明かりを点けて、一息深呼吸しながら椅子に深く腰掛けた。しばらく目の前の小さな鏡を覗きながら右手の親指と薬指で目頭を押さえた。いつもの癖で、そうすることで視力が活力を増すような気がするから。
デスク上に閉じられた読みかけの本を手にして、栞を挟んだページを開いた。美代子は最近購入する本は文庫本が主で、かさばらないから好きだ。また堅苦しい内容の本は読んでいて疲れるから、ファンタジーものかラブストーリーを好んで読んでいる。
今、読みかけの小説は「子供のいない中年夫婦が日常の会話も少なく、都内の大手飲料企業に勤務する夫は仕事一筋に打ち込み、取引先の接待を理由に毎晩遅くまで飲み歩いて、妻が寝静まった時間に持参の合鍵で、物音を立てないようにして帰宅。寝室も別にして、家庭を顧みる余裕もない生活の中で、妻も自分の生きる場を探すが、だんだんと殻に閉じこもるようになり、我慢の糸が切れて、ある日の夕方、妻は食卓のテーブルに置手紙を置いて家を出る」という筋書きに共感を抱き、毎晩、寝る前の一、二時間キリの良い所まで読み進む。
入浴後に読むときは、自然と睡魔がやってきて寝つきが良い。
美代子は、小説の中の主人公に重ね合わせるように、現状の生活をこのまま続けていいものか疑問を感じることもあり、我が家の家庭という器には何かが欠けているように、時折思いにふけることが多くなった。