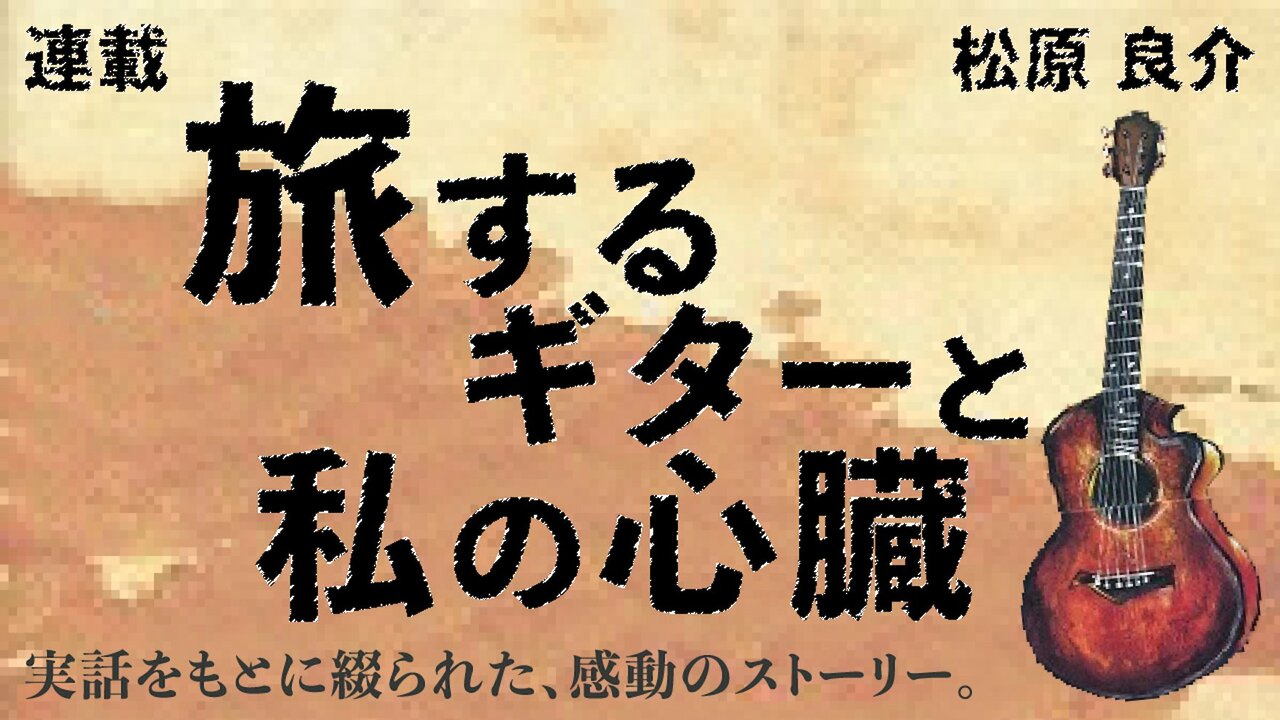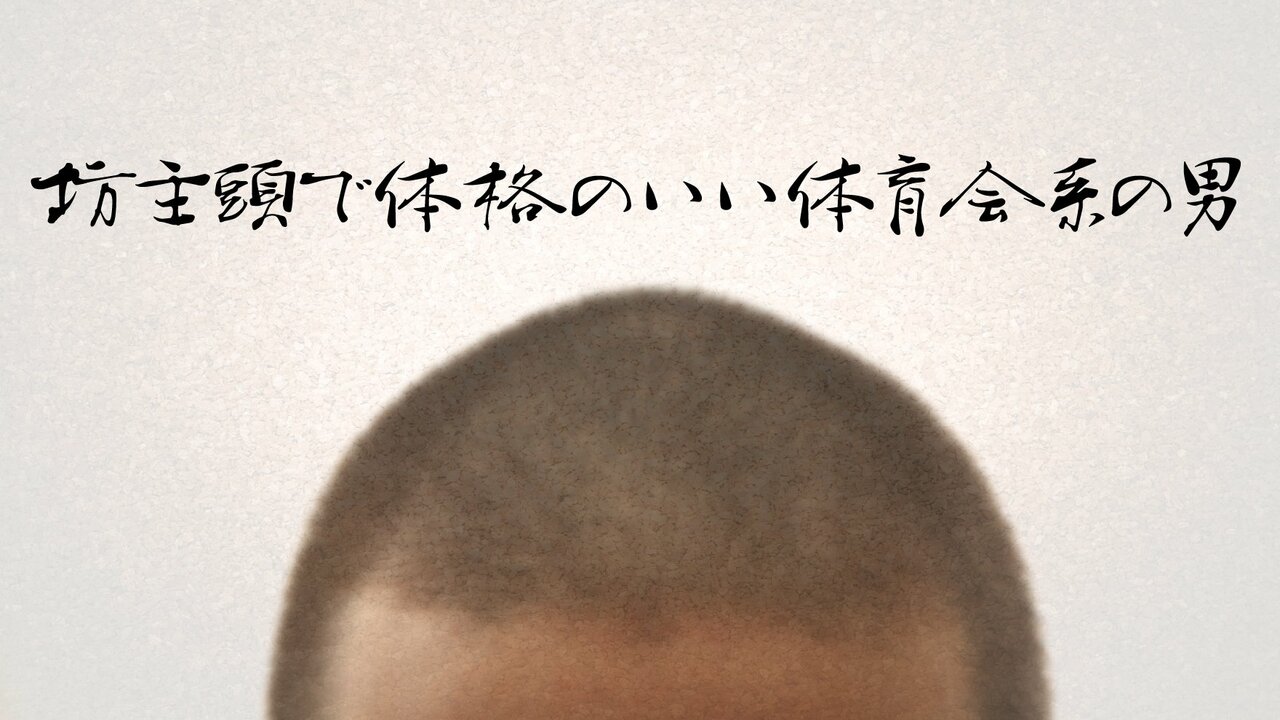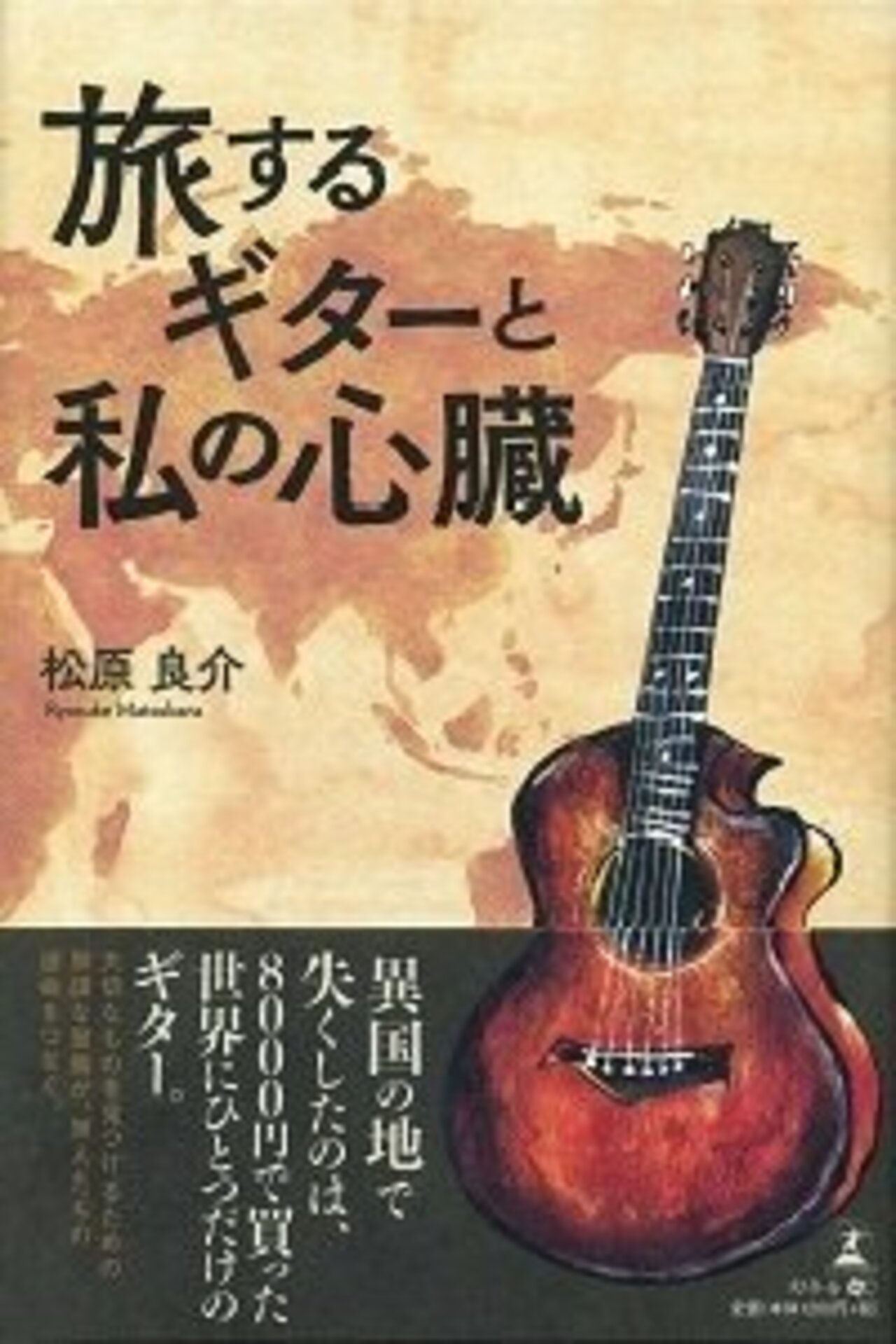2011年4月。
安藤は自宅を出て少し歩き、大通りに出ると、背中に背負った大きなバックパックを地面に置いた。
ずっしりした鈍い音が大地に響くと、安藤は道路に向かって腕を伸ばし、右手の親指を立てた。この親指が様々な出会いと経験を与えてくれる。安藤にとってヒッチハイクは人生そのものといえた。
5分ほど経ったところで軽自動車が目の前で止まり、安藤は窓を開けた若い男性に向かって慣れたように挨拶をした。鳥取に向かっていることを話すと、男性は佐世保まで行くからそこまでなら、と乗せてくれた。
安藤の目的は、鳥取の港から出る釜山行きのフェリーに乗ることだったが、出航は1週間後だったので急ぐ必要はなかった。感覚的には隣町に行くのとそう大して変わらない。安藤はただ、海の向こうに自分の世界を広げることだけを考えていた。
〈野崎哲也の事情〉
失敗の定義 私(野崎哲也)は小さい頃、サッカー選手になりたいと思っていた。
それは漠然とした夢ではあったが、今でもはっきりと覚えている。誰もが同じように幼い頃は夢があったはずだ。“お花屋さん” “先生” “宇宙飛行士” “歌手”……。昔の夢を聞けば皆、当時のことを思い浮かべながら、かつての自分の夢を答えてくれる。しかし、質問を変えて“その夢をいつあきらめたのか”と聞かれると、それを覚えている者は意外と少ない。
2014年2月。
旅人となった私は、バンコク市内のカフェでアイスコーヒーを飲んでいた。
「テツヤさん、いつもその飲み方ですよね」
私がアイスコーヒーを一口飲んでからミルクに手を伸ばすしぐさを見て、最近知り合った日本人の福士智仁は好奇な眼差しを向けた。
「この飲み方が一番うまい気がするんだ」
と返して私はカップを口に運んだ。
私が旅に出て9ヵ月が過ぎた。
序盤は崩しがちだった体調も身体が旅のリズムを覚えてきたせいかだんだん慣れてきたようだ。自分で言うのもなんだが、英語での会話もずいぶんスムーズになった。今ではゲストハウスで出会うさまざまな国の人たちとの会話が楽しみで、自分から話しかけることが多くなった。
これもすべてデイジーのレッスンのおかげだ。
彼女は嫌な顔一つせず、毎日私の勉強に付き合ってくれた。日記や旅の情報を書き留めていたノートはもはや英語の単語帳と化していた。
私が福士智仁と出会ったのは、数日前に宿の近くにある公園で、地元の子どもたちと彼がサッカーをしていたのを見かけたのがきっかけだった。
福士は坊主頭で体格のいい体育会系の男だった。若い頃に本気でプロを目指していたという彼は、市内のショッピングモールで購入したというサッカーボールを持っていた。
福士が言うには、このあたりでは公園でボールを蹴っていれば大人も子どもも関係なく加わってきて、すぐ友だちになれるのだという。消防士という立派な肩書を持つ福士は、長期休暇を利用してよく東南アジアを旅行しているそうだ。
私も昔サッカーをやっていたが、恥ずかしくてそのことは言えなかった。
31歳と自分と歳の近かった福士とは何かと波長が合い、数日だったがバンコクでの行動をともにした。消防の救急隊員である彼は、心肺停止の患者を搬送することも珍しくないらしく、心臓について私よりも豊富な知識を持っていた。
私が自分の病気ことには触れずに、彼に救急現場の詳細を尋ねると、
「いいですけど、そんなに面白い話じゃないですよ」
と前置きしてから話をしてくれた。
「現場に到着してから病院に患者を搬送するまでの間って、予想していないことがたくさん起こるんです。一応、マニュアルとか医師からの指示とかはあるんですけど、結局やるのは自分なんです。だから患者の状況を見て、最も適した決断を瞬時に導き出さなきゃならないことが多いんです。しかも、ドクターと違って救急の人間は、基本的に薬を使うことやその場で手術することはできないんです」
「え? じゃあ、何もできないまま搬送するしかないってこと? 心臓が止まっちゃったらどうするの?」
私が質問すると、
「コレですよ」
と言って、福士は両手を重ねて心臓をマッサージする仕草をして見せた。
「心臓の停止は患者の死に直結するから何としてでも動かします。たとえ肋骨が折れたとしても心臓さえ動いていれば、病院で待機しているドクターが何とかしてくれるので」
と彼は続けた。