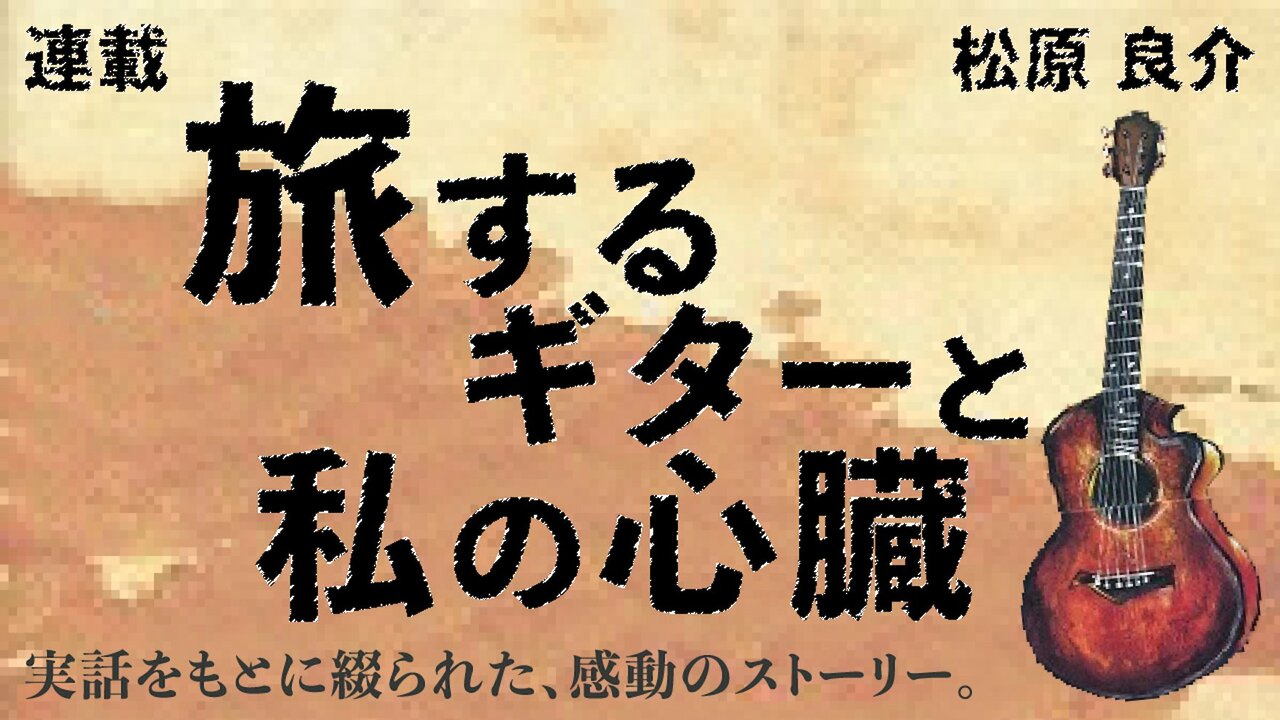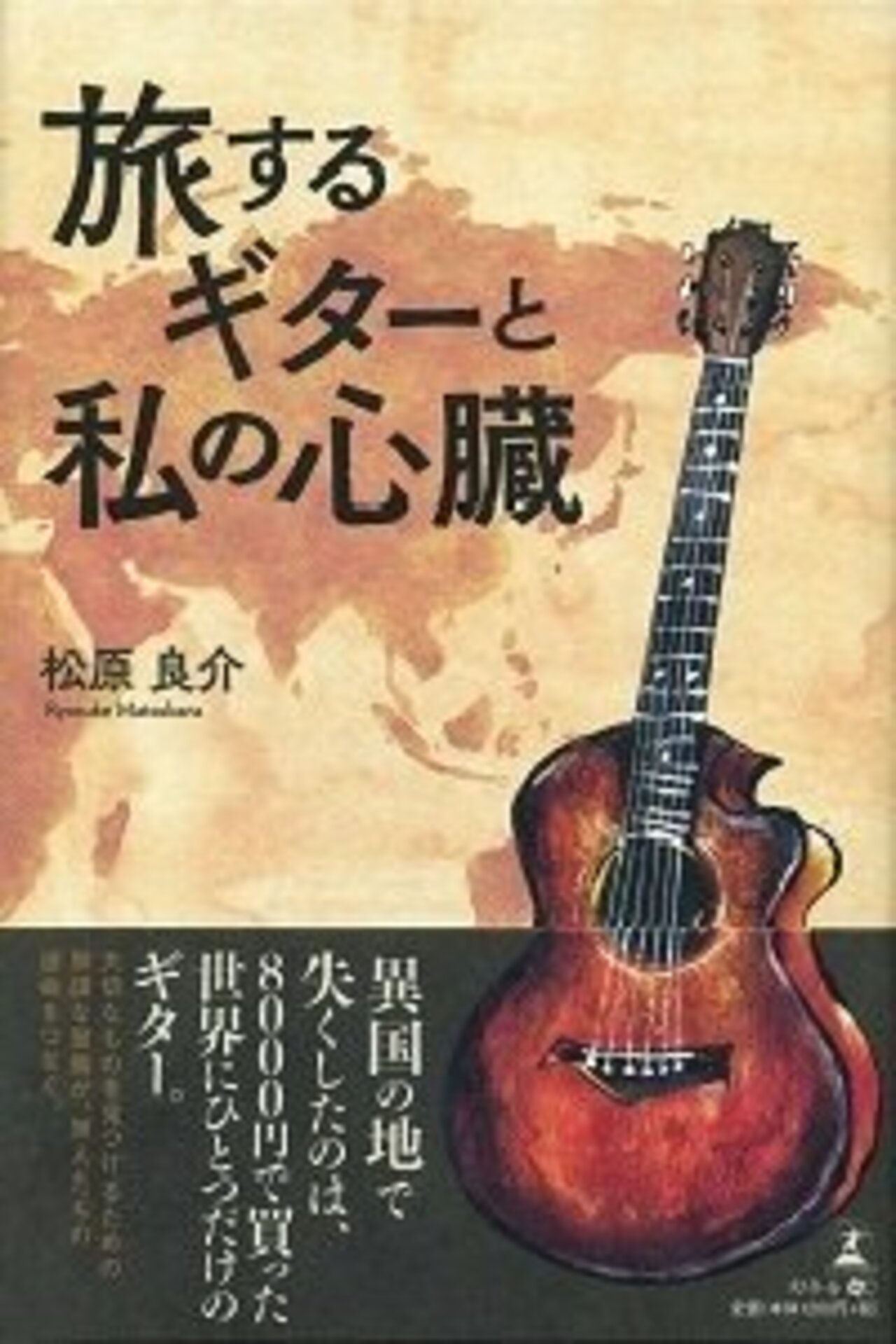2013年7月。
メイコはシェムリアップに移動していた。シェムリアップはカンボジアの北西部に位置し、アンコールワットなど観光地の拠点となる街だ。
バスターミナルから歩いて10分ほどのところにある「シティプレミアム・ゲストハウス」は今年オープンしたばかりのゲストハウスだ。スタッフの気配りが行き届いており、今までメイコが宿泊したどのゲストハウスよりも清潔感があった。
入り口を入ってすぐの庭にはオーナーのこだわりが感じられるバーベキュースペースがあり、そこを通ってレセプションに向かう途中にバーカウンターがある。バーカウンターの柱には少し古くなったハンモックがかかっていた。
メイコの滞在は今日で4日目。
ここである男性を待っていた。メイコはハンモックに身体を預け、スマホをいじりながら落ち着かない様子でいた。
それは2週間前の澤田からのメッセージがきっかけだった。
《そうそう、そういえばその青年はカンボジアに向かうと言っていたな。君もこれからカンボジアに行くんだよね? 会ってみたらどうだろう? 彼は君にとても会いたがっていたよ。もし君が会いたいなら連絡先を教えるけど?》
メイコはためらうことなく澤田に連絡先を教えてもらった。
男性の名前は「野崎哲也」とのことだった。現在、彼とは連絡を取るためフェイスブックでつながっている。プロフィールには北海道出身の33歳の男性と記載されていた。
12時をまわった頃、一人の男性がハンモックに揺られるメイコの横を通り過ぎ、レセプションの前で止まった。この時間、レセプションにはスタッフがおらず、男性はキョロキョロしながら奥に進んでいった。ハンモックから身を起こすと、メイコは裸足のまま彼の後を追った。
「こんにちは……」
奥のスタッフルームに向かおうとした男に向かって、後ろから探るようにメイコは声をかけた。
「あのー、ご予約の方ですか?」
「あ、こんにちは。はい。予約をした野崎です。スタッフの方ですか?」
男はいきなり話しかけられて少し驚いた様子だったが、ニコリとしながら言った。
「いえ、違うんです。スタッフは買い出しに行っていて、今いないんです」
「そうか。いないのか、どうしようかな……」
「あの……ノザキ、ノザキテツヤさんですよね?」
メイコは背の高い男を少し見上げるようにして話しかけた。
「はい、そうです。あっ! メイコさんですか!?」
野崎は年齢よりもずいぶんと若々しく見える男だった。身長は180センチはあるだろうか。メイコは小柄な自分がさらに小さくなったように感じた。
ニュートラル(安藤大輔)
宮崎県の小さな町に生まれた安藤大輔は、12 歳のときに父の影響でギターを始めた。
父がビートルズの熱烈なファンだったこともあって、父の部屋にはギターをはじめ、さまざまな楽器が所狭しと並んでおり、物心がついた頃から安藤にはギターをやる環境がすべて揃っていた。安藤は、身体に染みこませるようにビートルズの曲を練習した。
1年ほど経つとコピーでは満足できなくなり、自分で曲を作るようになったが、気の合う友人もおらず、周囲にバンドを組めるような環境がなかったため、安藤はいつも一人だった。
やがて自分の作った曲を誰かに披露したくなると、時間を見つけてはギターを持って街や公園に出向いた。孤独に始めた弾き語りだったが、だんだん足を止めて聴いてくれる人が現れ、曲のリクエストをされるようになると、それがさまざまなジャンルの音楽を覚えるきっかけになった。
人間観察をしてみると、公園でも、街角でも、どこに行っても決まったルーティンで人は動いていた。毎日決まった時間に同じ顔触れが安藤の前を通り過ぎていくのだ。
もともと安藤は人前に出ることが好きだったわけではなかったが、弾き語りを通じて出会う人たちが、ルーティンから抜け出すように安藤の前で足を止めてくれるのが嬉しかった。
そのうち小銭がギターケースに入るようになり、多いときには1日で3万円も入ることもあった。ときどき警察がきて、演奏をやめて移動するように注意を受けることもあったが、もともとお金を稼ぐために始めたわけではなかった安藤にとっては、居心地のいい場所から離れなくてはいけないことのほうがつらかった。
安藤は20歳のとき、弾き語りで稼いだ小銭とギターを持って、日本全国を旅してまわった。大きな志(こころざし)があったわけではなく、どこに行ってもギターがあれば生きていけることに味を占めた安藤は、隣町にふらりと行くような感覚で旅をしてみたのである。
旅を始めてからあっという間に3年の歳月が過ぎた。とりあえず実家に帰ることにした安藤だったが、これといって旅を終える理由もなかったので、それは一時帰宅するだけの『寄り道』でしかなかった。
安藤は日本各地を旅していたときにさまざまな人たちに出会った。自分も昔は旅をしていたという人や、世界を知る人たちにも出会った。
「旅人は引き寄せあうものなの」
そう教えてくれたのは、仙台で出会った辻本英恵(はなえ)という50代の女性だった。
彼女はヒッチハイクをしていた安藤をつかまえて自宅に招き入れると、好きなだけいてもいいと言ってベッドと食事を与えてくれた。
20年前、南米でジャーナリストをしていたという英恵の話はどれも興味深く、安藤の旅に対する考え方に大きな影響を与えた。仕事を終えて帰ってきた夫の晴典も、この状況に慣れているのか、突然の訪問者を見て驚く様子もなく、あっさりと安藤を受け入れてくれた。
晴典は英恵とは対照的に物静かな人だったが、酒が入ると饒舌になり、安藤にウイスキーの味を教えてくれた。そうして毎晩3人で晩酌をした。
晴典は勤めていた新聞社で英恵と出会い結婚したことや、新婚旅行は二人で世界を一周したこと、旅行中に英恵が女の子を身籠ったこと、娘の美和は現在都内の大学に通っていること、本当は男の子が欲しかったことなど、身の上話を毎晩安藤に語った。
「旅人ってとてもニュートラルな状態なの」
あるとき、英恵がとろりと酔った口調で言った。
「社会に身を置いているようで、そうでなくって、世のなかに存在していないような立場であって……。だから、南米にいた当時は中立的で自由な発想を持てたわ。出会う旅人もそういう感じの人たちが多いから、自然とお互いを認め合うし、求め合うの」
だからヒッチハイカーや自転車で旅をしている人を見つけると、懐かしい感覚を思い出して声をかけるのだと言っていた。