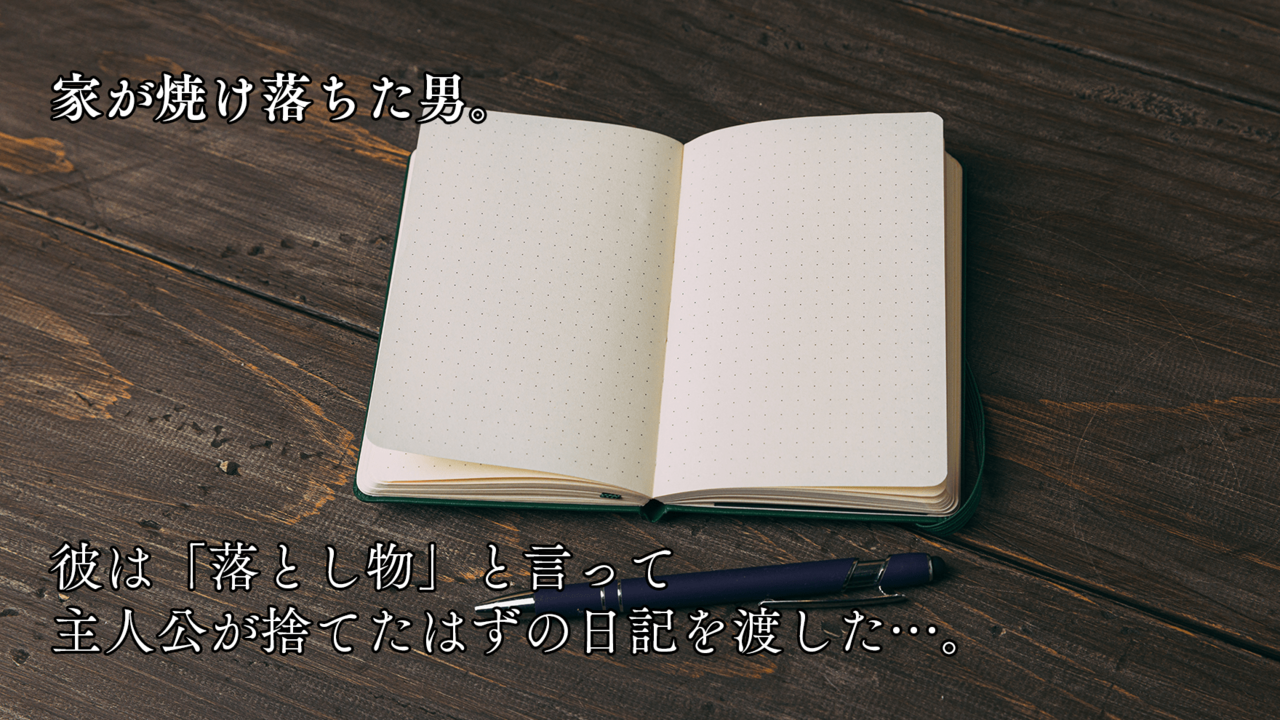第一章
3 サカ
私が自転車で近づいていっても、サカはこちらを無視してゴミをあさっている。まるで毛繕いする猿が捕まえたノミを口に入れるように、サカは飯粒らしきものをこまごまと食っていた。人の目を気にするデリカシーなど、とうに失っているのだ。
けれどサカはなかなかのプライドの持ち主らしく、以前私の父が残り物のパンをやろうとしたら、「オレは乞食じゃねえ」と断ってきたという。サカにしてみれば、他人の施しを受けるほど自分は落ちぶれていない、ということなのだろう。ゴミをあさる行為は乞食ではなく、単に捨てられたものを回収しているにすぎないということか。
他者に依存せず孤高の道を行く、といえば格好いいけれど、私だったら腐っていないパンのほうがありがたい。
そんなことを思いながら自転車で通り過ぎる手前で、私はベルを鳴らしてやった。オレだぞ、オレ、と存在を知らせるように。サカは一瞬動きを止めたものの、こちらを向くことはなかった。
もしベルを鳴らしたのが私だと分かったとしても、彼は無視して食事を続けただろうか? 歳月のせいで私のことなどもう忘れてしまったか、どうでもいい存在になってしまったか、それともかつてのような不毛なさまよいを始めた私を見て、なにか思い出すことなどあるだろうか?
私がこのチャレンジをするきっかけの一つを作ったのは、実はサカである。今から十年前の話だ。